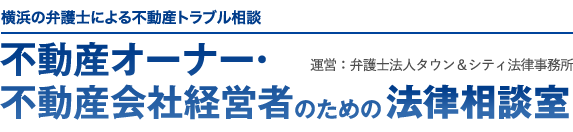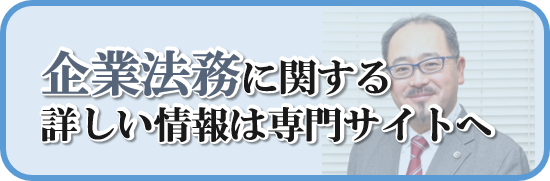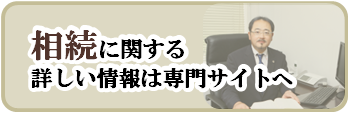遺言書を基とした財産の算定方法
遺言書を基とした財産の算定方法
3 遺留分減殺請求
(1) 計算方法=遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して算定する(民法1029条1項)。
① 遺留分侵害額の算定:遺留分の侵害額は、遺留分額から、遺留分権利者が相続によって得た財産額を控除し、その者の負担する相続債務額を加算して算定する(最判平8.11.26民集50-10-2747)。
② 貨幣価値の換算:遺留分算定の基礎となる財産に特別受益として加えられる贈与財産が金銭である場合、相続開始時の貨幣価値に換算した価額をもって評価するのが相当である(最判昭51.3.18民集30-2-111)。
③ 全部の財産を相続させる場合の債務:相続人のうちの一人に財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には、遺言の趣旨等から相続債務は当該相続人に全て相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、相続人間においては当該相続人が相続債務も全て承継したと解され、遺留分の侵害額の算定にあたり、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない(最判平21.3.24民集63-3-427)。
☆ 加算される贈与の範囲:受贈者が法定相続人→相続開始前1年間に限定されない(民法1044条による同903条、904条の準用)。例えば30年前の婚姻時の贈与なども含まれる。
受贈者が法定相続人以外→相続開始前1年間に限定される(民法1030条第1文)。但し、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年間に限定されない(民法1030条第2文)。
A 「遺留分権利者に損害を加えることを知って」の認定:
家督相続開始約19年以前の贈与が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものと認定するには、当事者双方が、贈与財産の価額が残存財産の価額を超えることを知った事実ばかりでなく、なお将来被相続人の財産に何ら変動がないことの予見の下に贈与があった事実を判示しなければならない(大判昭11.6.17民集15-1246)。
B 特別受益に該たる贈与:民法(1044条により準用される)903条1項の定める相続人に対する贈与は、上記贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化を考慮するとき、減殺請求を認めることが上記相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、本条の定める要件を充たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる(最判平成10.3.24民集52-2-433)。
C 遺留分減殺請求権の法的性質(形成権):遺留分権利者が民法1031条に基づいて行う減殺請求は形成権であって、その権利の行使は受贈者または受遺者に対する意思表示によってなせば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、一旦、その意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力が生じる(最判昭41.7.14民集20-6-1183)。
D 遺産分割事件における主張:遺産分割事件において、分割の前提として遺留分減殺請求権行使の事実及びその効果を主張することは、遺産の範囲を明らかにし、これを明認した上でその分割手続を進めることが必要である以上、当然許される(東京高判昭44.7.21家裁月報22-3-69)。
E 減殺請求した財産の帰属:財産全部の包括遺贈に対して減殺請求した遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない(最判平8.1.26民集50-1-132)。
F 遺留分減殺請求と時効取得:被相続人がした贈与が遺留分減殺の対象としての要件を充たす場合には、遺留分権利者の減殺請求により、贈与は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者が取得した権利はその限度で当然に右遺留分権利者に帰属するに至るものであり、受贈者が、上記贈与に基づいて目的物の占有を取得し、民法162条所定の期間、平穏かつ公然にこれを継続し、取得時効を援用したとしても、それによって、遺留分権利者への権利の帰属が妨げられるものではない=遺留分減殺の対象としての要件を充たす贈与を受けた者が、民法162条の取得時効の要件を充たしたとしても、その物の遺留分権利者への帰属が妨げられるものではない(最判平11.6.24民集53-5-918)。
G 債権者代位:遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができない(最判平13.11.22民集55-6-1033)。
H 保険金受取人の変更:自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は、民法1031条に規定する遺贈または贈与に該たるものではなく、これに準ずるものということもできない(最判平14.11.5民集56-8-2069)。
I 遺贈の減殺の割合:遺贈は、その目的の価額(※)の割合に応じて減殺する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う(民法1034条)※相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合には、その遺贈の目的物の価額のうち受贈者の遺留分額を超える部分のみが、民法1034条にいう目的の価額に該たる(最判平10.2.26民集52-1-274)。
J 贈与の減殺の順序:贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする(民法1035条)。
☆ 同日贈与・同日登記:2個の贈与が同日に行われ、贈与不動産について同日に登記され、登記受付番号に先後を生じても、該贈与が同時に行われたものと推定することができる(大判昭和9.9.15民集13-1792)。
K 受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等:減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない(民法1040条1項本文)。但し、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求できる(同但書)。上記1項は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する(同条2項)。同1項但書の場合には、価額弁償の抗弁(民法1041条)も準用される(同条2項)。
☆ 譲受人に対する減殺請求:受贈者に対し減殺の請求をしたときは、その後、受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対して、更に減殺の請求をすることはできない(最判昭35.7.19民集14-9-1779)。
☆ 譲渡価額による弁償:遺留分減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が遺留分権利者に対して価額弁償すべき額は、譲渡の価額がその当時において客観的に相当と認められるときは、その価額を基準として算定する(最判平10.3.10民集52-2-319)
(2) 価額弁償の抗弁:受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与または遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる(民法1041条1項)。←遺留分減殺請求は、原則対象物に対してが原則だから受贈者等が対象物は返還等したくない場合に備えて。価額弁償の抗弁が優先するので、いくら遺留分権利者といえども、侵害者から弁償される限り、物は手に入らないことになる。
① 個別財産の価額弁償:受贈者または受遺者は、民法1041条1項に基づき、減殺された贈与または遺贈の目的たる各個の財産について、価額を弁償して、その返還を免れることができる(最判平12.7.11民集54-6-1886)。
② 価額弁償の基準時:遺留分権利者が受贈者または受遺者に対し民法1041条1項の価額弁償を請求する訴訟における贈与または遺贈の目的物の価額算定の基準時は、上記訴訟の事実審口頭弁論終結の時である(最判昭51.8.30民集30-7-768)。
③ 現実の履行の必要性:特定物の遺贈につき履行がされた場合、民法1041条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためには、価額の弁償を現実に履行するかまたはその履行の提供をしなければならず、価額の弁償をすべき旨の意思表示をしただけでは足りない(最判昭54.7.10民集33-5-562)。
④ 裁判所の定めた額による弁償:減殺請求した遺留分権利者からの遺贈の目的物の返還請求訴訟において、受遺者が、裁判所の定めた価額により弁償する旨の意思表示をすることは認められる(最判平9.2.25民集51-2-448)。
⑤ 遅延損害金の起算日:遺留分減殺請求を受けた受遺者が、価額弁償する旨の意思表示をし、遺留分権利者が受遺者に対して価額弁償請求権を行使する旨の意思表示をした場合には、その時点において、当該遺留分権利者は、遺留分減殺によって取得した目的物の所有権及び所有権に基づく現物返還請求権を遡って失い、これに代わる価額弁償請求権を確定的に取得する。価額弁償請求にかかる遅延損害金の起算日は、受遺者に対し、弁償金の支払を請求した日の翌日になる(最判平20.1.24民集62-1-63)。
⑥ 弁償額の確定を求める訴え:遺留分減殺請求を受けて価額弁償する旨の意思表示をした受遺者等は、判決によって確定されたときは速やかに支払う意思がある旨を表明して、弁償すべき額の確定を求める訴えを提起できる(最判平21.12.18民集63-10-2900)。
(3) 消滅時効:減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする(民法1042条)。
上記起算を開始させるために、遺言執行者は遺言書の写と遺産目録を法定相続人に送付することは既述。通常は、上記起算点を明確にするため、配達証明付で送付する。
① 目的物返還請求権の不消滅:遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた目的物の返還請求権等は、民法1042条所定の消滅時効に服さない(最判昭57.3.4民集36-3-241)。
② 贈与の無効主張:遺留分権利者が、減殺すべき贈与の無効を訴訟上主張していても、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されたことを認識していたときは、その無効を信じていたため減殺請求権を行使しなかったことにもっともと認められる特段の事情のない限り、上記贈与が減殺できることを知っていたと推認するのが相当である(最判昭57.11.12民集36-11-2193)。
③ 遺産分割協議の申入れ:被相続人の全財産が相続人の1部の者に遺贈された場合に、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれると解すべきである。+遺留分減殺の意思表示がなされた内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、その意思表示は社会通念上受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められた(最判平10.6.11民集52-4-1034)。
(4) 遺留分の放棄:相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生じる(民法1043条1項)。
共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない(同条2項)。
☆従来は、遺留分すらも与えないためには、生前の家裁への遺留分放棄の申述&家裁の許可が唯一の手段だった。
しかし、特例として中小企業者の遺留分の算定に係る合意制度ができた(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律3条以下)。これにより、民法上の遺留分どおりでない分割案でも、法定相続人間で合意すれば可能となった。但し、上記家裁への申述&許可制度を潜脱しないために、この合意についても、家裁の許可は必要とされた(同法8条)。
投稿者プロフィール
- 弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。
最新の投稿
- 2022.01.14夫婦の離婚に伴い、夫婦共有不動産の妻の単独取得に成功した事例
- 2021.12.29夫婦間の離婚において住宅ローンに適切に対処し、相場より高い養育費の支払等を実現できた事例
- 2020.07.08夫婦間の共有不動産の共有物分割請求
- 2020.07.08担保権が設定されている不動産の共有分割請求