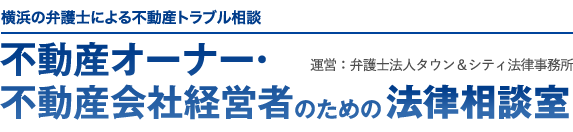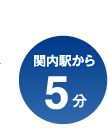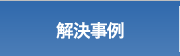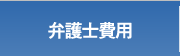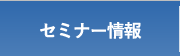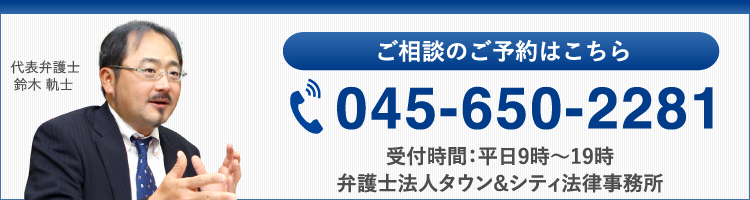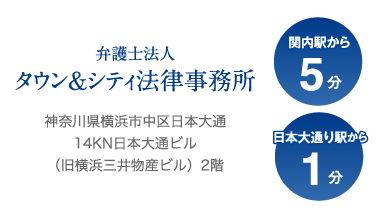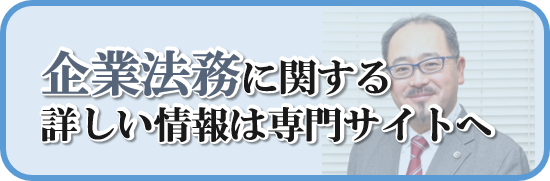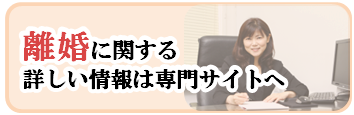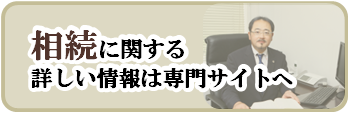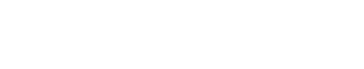所有者不明土地の解消 ~「特別代理人の選任」による解決方法~
Contents
1.はじめに
近年、我が国では、人口の減少や高齢化の進展、地方から都市部への人口移動等を背景として、特に地方等において「土地」への所有意識が希薄化しました。これに伴い、または地震や津波等の大規模な自然災害が起きたことによっても所有者が不明な土地が多くあり、この対応が課題となっています。
このような「所有者不明土地」とは、一般には、不動産登記簿(=土地についての権利関係が記載された公の記録です)を確認しても所有者が直ちに判明しない土地や、仮に所有者が判明したとしても、その所在が不明で連絡がつかない場合をいいます。
そして、所有者不明土地は、一説には、その面積は九州本島の大きさに匹敵するともいわれており、今後、高齢者の死亡後の相続関係の不明瞭等により、更に多くなることが予想されています。
所有者不明土地では、土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となったりしますので、公共事業や復興事業が円滑に進まなかったり、また、一般の不動産取引等による土地の利用の阻害要因となったりするなど、問題が山積みとなります。
こうした状況から、平成30年には「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が制定されたほか、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」などが制定され、近年、所有者不明土地の発生の予防とそれの対処に関する法整備がなされています。
所有者不明土地を占有する方からのご相談は多いですが、一例として相続をきっかけに被相続人の所有者不明土地の所有権を取得できた方の事例をご紹介します。
2.不在者財産管理人による解決
一般に、相続が開始した場合で、特に被相続人の残した遺言等もない場合には、被相続人の財産を取得するために、相続人間で被相続人の個々の財産について権利関係を確定させるための、遺産分割協議等を行う必要があります。
その際、被相続人の財産について遺産調査を行うこととなるのですが、調査に際して、相続人の中に行方不明でその生死すらも不明の者がいたり、生死や所在は判っても相続人と連絡が取れない場合もあります(「所有者不明土地」も、その一場面です)。
この場合にも、その者との間で遺産分割協議をしなければならないのが原則なのですが、この解決方法としてよく使われる手法としては、不在者財産管理人の制度となります(民法25条1項)。
これは、上記の例でいうと相続人の一人が「利害関係人」として不在者財産管理人の選任を裁判所に請求し(民法25条1項)、同選任された管理人との間で、上記の相続人が単独でも行える「保存行為(民法103条)」等の範囲外の行為として、家庭裁判所の許可(民法28条)を得て、遺産分割協議を行うこととなります。
このような方法によって解決を図るのが通常なのですが、手続的に若干煩雑であり、時間もかかります。また、管理人に支払う費用もある程度(管理に要する手間や時間・管理対象の経済的価値等に基づき、裁判所によって決められますが、通常、30万~100万円位)は準備が必要です。
不在者財産管理人だと、このような不利益がありまので、むしろ「特別代理人の選任申立て」によることで所有者不明土地の問題を解決することを考えました。
3.解決事案のご紹介
<事案の概要>
相続財産として父親から居住不動産を相続したはずのところ、見ず知らずの人物が登記上の所有者になっていました。相続人は誰一人(依頼者の方複数名)は、この人物に心当たりがなく、親戚一同も同じくです。登記上の記載された住所に照会をかけても該当者は見付かりません(既に住民票も移転されていました)。
登記上記載された不動産取得時は昭和の初期の頃で、仮に当該人物が生存していたとしても非常に高齢となっており、移住先で既に亡くなっている可能性も充分にあり得る事案でした。
この点、依頼者の方は、被相続人(父親)の代からずっと(20年以上)当該不動産に住んでいましたので、取得時効の成立は容易に認められると思われました。しかし、これを認めてもらうために訴訟を提起するとしても、そもそも被告をどのように特定すればよいのかが問題となります。
<解決方法=特別代理人の選任申立てによる解決>
上記の「不在者財産管理人」の制度や、失踪宣告(民法30条)を裁判所に求める方法などで処理は可能ではあります。
しかし、上記事案に関してだけであれば、当該不動産に対して、その所有が認められればよく、上記の「遺産分割協議」等を行わなくとも取得時効の主張・立証により解決できそうです。
以上から、訴訟において被告になってもらうために「特別代理人」を選任してもらうことを裁判所に申立てることにより、事案の早期かつ比較的安価な解決が出来ました。
4.「特別代理人の選任申立て」について
民事訴訟法35条1項によれば、以下のように定められています。
| 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。 ⇒この規定を、相続等の場面で行方不明者がいる場合とかに流用できるのでしょうか? |
この点、大審院昭和5年6月28日決定(民集9巻640頁)によれば、以下の判示がされています。
| 相続人不分明による相続財産法人に代表者がいない場合に、相続財産に関して民事訴訟を提起しようとする者は、特別代理人の選任を申し立てることができる。 |
したがって、この判例に基づくと、相続人の存否が不明である等により相続財産法人が成立する場合(民法951条)に、訴訟提起をしようとする場合には、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明することで、特別代理人の選任申立てをすることが出来ます。
すなわち、①「相続財産法人の成立」=「相続人のあることが明らかではない」こと、②「遅滞のため損害を受けるおそれがあること」を疎明すること、③ 相続財産法人に対する訴訟提起、の3点を準備することで、特別代理人の選任申立てにより、当該不動産に関して、取得時効を原因とする所有権移転登記請求を認容する判決を得ることができ、解決できます。
ちなみに、この訴訟(③)では、訴訟係属後の審理等が通常の訴訟と同じように予定されているわけではないので、訴えの提起時において請求認容判決が得られるほどの十分な証拠を準備はあります。しかし、上手く上記の「特別代理人」制度を活用すれば、費用や時間等を大幅に節約することができます。
5.「特別代理人の申立て」に必要な費用や注意点等
民事訴訟費用等に関する法律3条1項別表第一17「イ(イ) 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、…(略)」により、③ 訴えの提起(訴状)の印紙代の他に、特別代理人の選任申立書にも500円の収入印紙を貼付することが必要となります。
また、「選任の申立て」ですので、この申立書自体から、民訴法35条1項が定める上記要件を充足していると裁判所が判断するに足りる資料の疎明が必要で、慎重な準備が必要となります。
そして、特別代理人の候補者(通常は弁護士)にはあらかじめ内諾を得ることが必要不可欠です。また、当該特別代理人は、候補者に選ばれた際、裁判所に対して、本件において利害関係が無いことの説明などが必要となります。
ちなみに、全ての事案において上記のような特別代理人制度を利用した解決が出来るわけではありません。
しかし、所有者不明土地の解消に向けては、上記の「特別代理人の選任申立て」も含めた多彩な解決方法の検討が重要です。
当事務所では、事案の解決のために、ご依頼者様に最善の利益となるよう、適切な解決方法を提案致します。お困り事がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
投稿者プロフィール
- 弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県で約30年にわたり弁護士として活動しており、特に不動産分野に注力してきた。これまでの不動産関連のご相談は2,200件を超え、550件ものご依頼を受任。豊富な経験と知識で、常に依頼者にとって最良の結果を追求している。特に、不動産の共有関係や借地関係の解決には強い関心を持ち、複雑な問題も粘り強く解決に導く。
最新の投稿
- 2025.08.06不動産トラブルのセカンドオピニオンを検討中の方へ
- 2025.04.19建物明渡請求訴訟における占有移転禁止仮処分
- 2025.04.18所有者不明土地の解消 ~「特別代理人の選任」による解決方法~
- 2025.04.18所在不明等共有者の持分取得または第三者に譲渡するための手続【令和3年民法改正】について