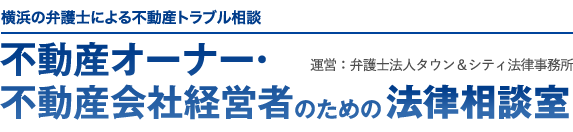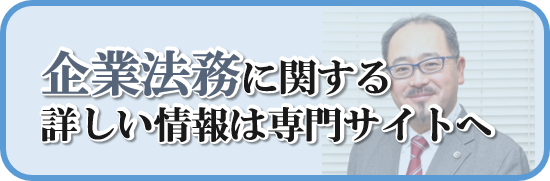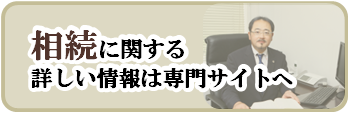借地上の建物の建替えでよくあるトラブルとは?増改築禁止特約を弁護士が解説
借地上の建物を建替えたい。そんなときはどうすればよいのでしょうか?
借地上の建物も時間が経てば経年劣化してくるので、建替が必要となる場合があります。しかし、借地契約上では、借地人による建物の建替えについては、地主の承諾(書面による承諾)を要するとされていることがほとんどです。この場合、万が一、地主の承諾を得ずに無断で建替えをしてしまうと、契約違反として地主側から借地契約を解除されてしまう恐れがあります。仮に承諾を得られる場合でも、承諾の条件として承諾料の支払いを求められることが通常です。なお、仮に地主が正当な理由なく承諾しない場合には、借地非訟の申立てを行い、裁判所に対して地主の承諾に代わる許可を求めることができます。但し、この場合でも、承諾料の支払いは必要となることが通常で、その金額は裁判所が決定します。
このような借地上の建物の建替えについて、以下では当事務所の弁護士が解説します。

1.借地上の建物の建替えと増改築禁止特約とは?
(1) 借地上の建物の建替えを巡る問題について
借地上の建物の建替えについては、借地契約上、通常、「増改築禁止特約」が定められていることから問題となります。この定めがあることにより、借地上の建物の建替えをする前に、地主から、(通常は「書面」で)建替えについて承諾してもらう必要があります。この承諾をもらうためには、通常は地主に対して「承諾料」を支払う必要があります。
仮に建替え前の地主の承諾なしに、建替えをすると、借地契約を解除される可能性が生じてしまいます(*1)。
そこで、地主が承諾してくれない場合に、借地人は、裁判所に申立てをして、地主の承諾に代わる許可(決定)を求める必要があります。この場合、裁判所は承諾料を決めてその支払と引換の建替えの許可決定を言い渡してくれます。
(*1) 増改築禁止特約があるのに、建物を取り壊して新しく建物を建てる場合、事前に地主の承諾を取らないと解除が認められる可能性が高まります。しかし、建替えではなく、修理の場合はどうなのでしょうか。問題は「修理」が「増改築」に該たるか、ということです。「修理」にも色々な程度がありますが、「通常の修理」の範囲を越えると「改築」になる場合があります。
(2) 増改築禁止特約について
増改築禁止特約とは、借地契約上、地主の承諾なしに借地上の建物の建替えをすることを禁止し、建替え等をする場合には、事前に地主の承諾(通常は書面で)を必要とする規定です。元来、法律は、借地上の建物の建替え自体には地主の承諾を要求しておりません。そのため、本来建替えは「自由」でした。しかし旧借地法が立法された結果、借地人が過剰なまでに保護されることになりました。その保護に対して地主側がいわば「対抗策」として生み出したのがまさに増改築禁止特約だったのです。そのため、契約書上に「特約」として上記を規定する必要があり、規定して初めて、その効力が認められることになります。
近年においては、借地契約書では、通常、「増改築禁止」の特約が規定されています。相当に古い契約書には規定されていないものもありますが、昭和30年代以降になれば大概、契約用紙に、予め書かれて(定型の書式であれば印刷して)あります。
「増改築」とは、建物の増築と改築のことです。
①「増築」は、現在の建物に追加して建物を建てること(これは、例えば、一棟の建物の床面積を増やすことも、現在の建物の横に新しい建物を建てる(但し、当然、「別棟」ではなく「同棟」として。仮に「別棟」の場合には、「増改築禁止特約」とは別の問題が生じます。すなわち、これに対しする「承諾」や「許可決定」の問題だけでなく、そもそもの借地契約の範囲や対象(=複数棟の建築まで許された1つの借地契約なのか、それとも各棟ごとに別々の借地契約なのか)が問題となります)ことです。
②「改築」は、 建物の建替えのことです。現在の建物を取り壊して新しい建物を建てる(再築もしくは新築)のが典型的で、建物の主要構造(屋根、外壁、柱等)の変更による建物の同一性の変更(単なる同一性の問題というよりは(更新と同様に)借地期間の延長を招きかねないことが問題とされることから、建物の耐用年数の変更(通常は伸長)をもたらす場合と解釈されています)も、これに含まれます。
増改築禁止特約は、「土地の賃借人が借地上の建物を建替えたり、建て増したりする場合には、予め(書面で)賃貸人(土地所有者)の承諾を求めなければならない」という規定が一般的です。(*1)
この特約が契約書上あるのに、地主に無断で建物の増改築をすると借地契約違反になり、信頼関係の破壊の程度によっては、地主から契約を解除されることになります。(*2)
つまり、建替えの前に地主の承諾をもらう必要があります。
(*1) 契約書により、微妙に書き方が異なります。「増改築を禁止する」としか書いていない場合もあります。前記のとおり、別に法律で禁止されている訳ではないので、地主が承諾さえすれば、当然、「禁止」されない、ということになります。
(*2) 通常の修理は、地主の承諾なしに行うことができます。これは仮に増改築禁止特約があってもそうで、承諾は不要です。ただし、通常の修理の範囲を越える大修繕や大規模なリフォームなどは承諾が必要になる場合があります。
(3) 増改築禁止特約がない場合について
増改築禁止特約が定められていない場合(そもそも契約書がない場合も含みます)には、借地権者が建物の建替えをするために地主の承諾は不要です。 (*1) (*2)
(*1) 増改築禁止特約はあくまでも契約上の特約です。契約書がない場合には、増改築禁止特約はないものと判断されるのが通常です。しかし、「契約書がない」と言っても、一度も作成したことがない、というわけではなく、例えばかなり昔に契約書は作ったのに、現在は紛失して見当たらなくなってしまっただけ、という場合もあります。この場合、借地権者は契約書がないと思っていたのに、地主側は保管していた、ということもよくあります。「契約書が手元にないから、増改築禁止特約もないだろう」と安易に考えて、地主の承諾を得ないで建物の建替えをしてしまった結果、契約を解除される可能性まで出てきてしまいます。従いまして、少なくとも、契約書があるかどうかだけでも地主には確認する必要があります。明確でない場合(地主が回答しない場合を含めて)には、再三催促してでも建替えについての地主の承諾をもらうか、裁判所に、地主の承諾に代わる許可の申立てをして許可決定をもらった上で建替えをするのが無難です。契約書の有無に関わらず、そもそも「増改築禁止特約」がなければ、この特約の不存在が明らかになった時点でこの申立ては却下されます。この場合、裁判所の決定書には、「増改築禁止特約がないので却下する」と記載されます。よって、取り敢えず、借地人と地主間のトラブルは一旦、回避されることになるものと思われます。
(*2) 契約書があって、そこに増改築禁止特約がない場合でも、その契約書があまりにも古い(=おおよそ昭和30年代よりも前の)場合には注意が必要です。借地契約の更新があっても契約書を新しく作成しない場合もあり、その結果、何十年も前の契約書しかない場合もあります。このような場合に、この契約書を作成したずっと後になってから、契約書とは別に「増改築禁止の特約」をする場合もあり得ます。特に、最初の契約や更新の後に、現実に増改築をしている場合にはより注意が必要です。この増改築の時に、地主に何らかの金銭を払った場合には、「建替承諾料」として払った可能性もあるからです。これは増改築禁止の合意をした上で、増改築の際に承諾料を払ったものと解釈される可能性があります。上記のように金銭を支払った場合には、その趣旨について地主に確認して書面化しておいた方が無難です(金銭が「更新料」である可能性も考えられます)。大げさな書面でなくても、例えば領収証の摘要欄に「立替承諾料として」等一筆入れておいてもらうだけでも構いません。

2.裁判所の(地主の)承諾に代わる許可裁判(決定)(借地非訟)について
(1) 裁判所の許可決定と承諾料について
増改築禁止特約があり、増改築をしようとしているのに地主が承諾してくれない場合や承諾料の金額について合意が成立しない場合、借地人は裁判所に対して、承諾に代わる許可を求めることができます。なお、必ず着工前に許可を求めなければなりません。工事が着工後や、ましては完成した後で許可を求めることはできません。借地権の譲渡の許可等と手続は同じ借地非訟手続です。ちなみに「非訟」というのは「訴訟でない」(=簡単にいうと、裁判所は、認知した事実に法を解釈し適用するという「訴訟」判断以外の行政裁量的な判断もできる手続である)という意味です。
裁判所の許可が出れば、地主は借地人に対して「無断増改築」を理由とする契約の解除はもちろん、損害賠償請求等もできません。
この場合、裁判所は、地主に承諾料を払うことを条件に借地人に対して増改築の許可をします。
この承諾料の相場ですが、前の建物を取り壊して新築建物を建てる場合やほとんどそれに近い場合には、更地価格の概ね3%です。ただし、借地の満期が迫っている場合、建物の床面積を増やす場合、建物の用途を変更する場合(自宅に賃貸部分を追加するなど)は増額されます(最大5%といわれています)。
逆に、建物の新築とまでは言えない程度の増改築の場合は、承諾料は安くなります。増改築の規模にも応じますが更地価格の2%前後といわれています。
承諾料をいくらと決めるのかについては、まず裁判所の内部で構成される鑑定委員会(主として不動産鑑定士等が指名されます)が鑑定結果を明らかにします。その上で当事者双方からこの結果に対して主張ないし意見が出され、これらを総合的に考慮した上で裁判官が決めます。ここでの鑑定費用は、国が負担してくれます。借地権者や地主はこの鑑定費用は支出する必要がありません。(*1)
借地権者は、「増改築には当たらない」と思っている、しかし、地主は「増改築に当たる」と主張し、承諾もしないと言っている場合も、裁判所は申立てを受け付けます。このような場合、通常は工事の程度の評価の争いなので、裁判所は工事の程度に応じて承諾料の算定をして許可決定します。
これに対し、裁判所がそもそも「増改築に当たらない」と判断して終わらせる(=申立ての却下)こともあります。この場合、終わり方は「申立ての却下」ですが、却下理由の中で「(そもそも)増改築に当たらない」と裁判所が判断してくれるので、当事者間の争いは一応解決します。よって、申立て自体をする意味はあります。
承諾が必要かどうか微妙な場合や、地主が強硬に反対しているため、工事を強行すると工事終了後に紛争になる場合は、必ず工事前に裁判所の許可を求めることをお勧めします。無断で工事をした結果、地主が解除を主張して正式な裁判(=建物収去土地明渡請求訴訟)を提起した場合、土地の明渡まで認容されてしまうリスクもあるからです。また、仮にここまでの認容はされないまでも明らかに増改築に当たらない場合を除けば、同訴訟は結局、建替承諾料に相当する和解金を支払って和解成立で終了するケースが多いと思われるため、このような訴訟を地主から提訴される前に相場の承諾料の支払と引換に増改築の許可決定をもらっておけば、少なくとも上記明渡訴訟分の時間・費用・手間は節約できるものと考えられるからです。逆に、仮に判決になり、万が一、地主の主張が認められて敗訴すると、借地契約は解除されて借地権(評価の仕方によっては更地価格の60%程度の財産権と見る見方もあります)を借地人は失ってしまうことになります。
(*1) 通常の裁判や、家庭裁判所の遺産分割調停などで、不動産の鑑定を裁判所が行う場合(裁判所が不動産鑑定士に鑑定させる場合)には、その費用は、当事者が負担します(遺産分割調停の場合には、相続分に応じて各相続人が支払うことになります)。ところが、借地非訟の場合には、国が負担してくれるので、当事者は支払う必要はありません。借地非訟手続の性質上、「承諾(に代わる許可決定)」を求めざるを得ない社会的弱者である借地人に配慮した結果、公平上、地主にも負担を求めないことにしたものと言われております。ただし、基本的に全件鑑定となり、手続に時間はかかります。両当事者の合意に基づいては進められなくなったことが申立ての前提であることから、裁判官によって少々の時間をかけても公明正大な判断を期待することにした手続といえます。
(2) 許可申立て(借地非訟)の手続及び裁判(決定)
ア.申立書とその後の手続
裁判所に許可の申立をするためには、申立書を裁判所に提出します。申立書の書式は、裁判所のホームページからダウンロードできます。一般の方でも、自分で書いて裁判所に出せるように、というのが建前です。しかし、実際には、簡単なものではありません。何も経験もない普通の人が書けるものではありません。少なくとも法律の知識はもちろん、建築や不動産に関する知識も必要となります。
また、申立後ですが、書面審査だけで裁判所が許可をすることはまずないです。非公開(関係者以外の傍聴はできません)ではありますが、ラウンド法廷に近い部屋で、手続(=審尋といいます)をやります。地主側も呼ばれて、相手方の席に着き双方、事実や法律解釈に関する主張を交わします(通常、審尋は複数回開かれます)。この場合、弁護士に依頼すれば、他の訴訟事件等と同様に、当事者本人は法廷に出頭する必要はありません。
実際に、自身でできそうだと思って、申立書を自分で書いて提出したものの、裁判所(裁判官だけでなく、事務官や書記官も含めて)から「やっぱり弁護士に相談して下さい」と言われて、当事務所に相談に来られた方もいます。
イ.建物の設計図面の必要性
また、増改築の許可の申立の場合には、新しく建てる建物の図面(配置図、平面図、立面図、断面図)が必要になります。許可の対象となった(増改築後の)建物を特定するためです。
許可決定が出される場合には、別紙として上記の各図面が添付されて特定されます。そこで、この特定されている建物と違う建物を建てると、「無断建築」ということで解除される可能性が高まります(むしろ裁判所で許可決定された建物の増改築の内容を敢えて守らないことになり、より「悪質だ」と判断されるでしょう)。このため、諸々の食い違い等が生じないよう、新しく建てる建物の図面は、後で工事を依頼する予定の業者や建築士に作ってもらうのが無難になります。申立ての段階で、どんな建物を建てるのか、ほぼ、決めておかなければならないということになります。建築費用の目処をつけた上で申立てをした方が経済的にも間違いが少ないものと思われるため、むしろ、完全に決めておいた方がより良いものと思われます。前記した建物の「耐用年数」に格別影響がないものであれば、申立時に特定した建物と若干仕様が異なっても(例えば内装など)、「許可決定違反による解除」等は認められないだろうと思われます)。
ウ.決定までの手続の流れ
申立をすると、1か月半くらい後に、第1回の手続(審尋)の期日が入ります。そこで、ラウンド法廷のような部屋で当事者双方主張(書面)を交わしたりします。
ある程度手続が進むと、鑑定委員会が現地に行き、鑑定をします。そして、承諾料や増改築後の賃料(増額されることが多いです)等の鑑定を求められた点についての意見書を書きます。現地調査から通常1ヵ月~1ヵ月半後位に提出されたこの意見書を見て裁判官はそれを参考に承諾料をいくらにするかとか、賃料を上げるかどうか、上げる場合はいくらにするのか等を決めます。もちろん、意見書提出後(意見書は両当事者にも渡されます)に裁判官から通常は各当事者に対しても主張や意見を求め、裁判官はこれらを総合的に判断して決定します。
なお、以前は、増改築許可の決定をするとそこから借地期間(木造などは20年、堅固建物は30年)も決めていました(つまり、借地の期間を延ばしていました)が、今は、借地の期間は延ばさないのが取扱いです。例えば、借地の期間が残り5年の場合は、5年後が更新の時期になります。これは、増改築許可ないしその承諾料の問題と更新時の更新料の問題とは、法律上は一応区別することを明確にしたことに他なりません。(*1)
申立てをしてから、決定が出るまで平均8か月と言われています。全件鑑定をすることや、相手方(地主)側からも反対意見が出たりするからです。「建替」をしたい申立人としてはできるだけ早くしてほしいのですが、最低でも8か月はかかると思った方がいいです(平均だからもっと短くならないかと言われる方もおりますが、8か月はかかると思って頂き、そのため、申立て自体も時間的余裕をもってして頂いた方が無難だと思われます)。(*2)
(*1) ちなみに、増改築時に増改築の承諾料を支払っていれば、更新の時に借地人側が不利益に扱われることはありません。増改築の承諾料は、建物が再築されるなどして建物の寿命が延びて、その分、借地の期間が延長されることに対する対価の意味があることから経済的には「更新料」と重なる部分があるものと解釈されているからです。しかし、借地非訟の時からそもそも借地契約(や更新)の有効性が争われている場合などは、借地非訟ではなく正式裁判の判断が優先されます。借地非訟は、そもそも前提となる借地権の有無等について判断する(訴訟)手続ではないからです。
(*2) 承諾料等の金額に開きがあった場合でも、双方弁護士が就いて借地非訟手続になった場合、承諾料や増額賃料額等について、裁判官と協議して通常認められると思われる(いわゆる相場)額で同意して、和解が成立して早期に解決できる場合もあります。東京地裁、横浜地裁には専門部があり、借地非訟を担当する裁判官も経験が豊富ですから、決定で予想される場合とほぼ同じ額が提示されます。当事者双方がこれに納得できれば、和解で解決できます。この場合、双方当事者の弁護士の見極めと当事者を説得できるかどうかが重要なポイントになります。通常、早期解決したいのは借地権者です。よって借地人側がある程度妥協(=承諾料や賃料の各増額に応じること)しなければならない場合もあります。しかし、依頼者の中には、裁判所が決定を出せば従うけれども、和解では納得できないという方もいます。この場合には和解での解決はできません。いずれにせよ、両代理人の経験や人格等も含めた総合力が試される場面です。
エ.確定までの手続の流れ
地方裁判所で許可の決定が出ても、相手方が即時抗告(決定から2週間以内に高等裁判所に対して、決定の取消を求めること)をすると、高裁で審理することになります。地方裁判所のときと同様に改めてラウンド法廷のような部屋で審理することは余りありませんが、そもそも高等裁判所に事件記録等が送られるまででも一定の時間(1~2ヵ月)を要することから、高等裁判所での決定までは少なくとも数か月はかかります。
ただし、高等裁判所で抗告棄却(例えば地主側の即時抗告等が棄却される)になると、地方裁判所の決定が確定します。その結果、借地人は承諾料を払えば建物を建てることができることになります。これに対して、仮に地主側が最高裁判所に高等裁判所の決定の取消を求めても、その判断を待つ必要はない、という意味では、通常の訴訟以上に実質「二審制」といえます。

(3) 申立てが裁判所に許可されない場合について
申立書に必要なことが記載されてあり、必要な証拠を出して、特段の問題(増改築によって地主に特別な不利益が生じるおそれ等がなければ)、申立ては許可されます。許可は通常、承諾料と引換となります。なお、承諾料は、原則として、更地価格の3%です。
ただし、申立てが許可されない場合もあります。たとえば当初の借地条件で、そもそも堅固建物が建てられない借地に、堅固建物を建てる場合です。このようにそもそもの借地条件の変更が必要となる場合には、裁判所に別途、借地条件変更の許可の申立が必要になります。
①借地の期間満了が迫っている場合には許可されないのでしょうか?
おおよそ3年前後が目処となりますが、期間満了時に、地主側から借地の更新に異議が出て、それに正当事由があることが予想できる場合(期間満了で借地契約が終了する可能性がある場合)には、許可されないことがあり得ます。裁判所の借地非訟の担当部としても、あと数年で、借地の更新が認められるかどうか争われるなら、この前提問題が片付いてから申立てをしてもらわないと、前提から覆されかねないので困る、というわけです。
これに対し、地主に更新拒絶の正当事由がないことが明らかな場合や緊急性がある場合(居住していた建物が火事で焼けてしまい、すぐに建て直す必要がある場合など)は例外的に扱われ、許可が出されます。
決定の時点で期間満了まで3年のケースで、許可が認められなかった事案があります。この事実は、そもそも3年後に更新が認められるかどうかについて微妙な事情がありました (東京高裁平成12.7.28決定。地裁では許可が出たのに、高裁では不許可にしたケース)。
②建物の朽廃が迫っている場合には許可されないのでしょうか?
朽廃というのは、建物として使い物にならない状態(単に古いというだけでなく、柱はあるものの、雨風を遮る屋根、壁が無くなったために人が住めなくなったような状態)です。また、建物を建ててからの時間の経過で、このような状態になった場合を指し、地震や火事のような突然起きた災害で、このような状態になった場合は含みません。
この点、朽廃により借地権が消滅する場合があります。
すなわち法定更新のように期間の合意がない場合や法律が決めた期間よりも短い期間の合意をした場合には、法律が定めた期間が借地期間となり(更新後の場合、堅固建物は30年、非堅固建物は20年)、この期間内に建物が朽廃したときは、その時点で借地権は消滅します。
このため、上記の法定借地期間の場合には、申立ての時点で既にすでに建物が朽廃したことにより借地権が消滅しているため、建替えの承諾に代わる許可を求めての申立てはできません。
また、上記の法定借地期間の場合には、申立ての時点ではまだ朽廃こそしていない場合でも、既に朽廃に近い状態で、上記の法律が定めた期間内に建物が朽廃することが十分に予想できる場合もあります。このような場合には、申立ては棄却されます(なお、この場合、仮に借地人側が建替えをしても、元の建物が存続していれば朽廃したであろう時期が来ると借地権が消滅する扱いをされます)。なお、「朽廃」の状態や「朽廃」時期などについては鑑定委員会の意見を聞いた上で裁判官が判断します。
この点、元々、借地人が建替えをしたい理由の多くは、建物が古くなったからです。ですので、上記のように、建物が古いとそれを理由に許可されないというのでは理不尽です。そこで、現実に人が住んで使っている場合には、相当、古い建物でも(例えば雨漏り等が少々あっても)「朽廃」している、とか「朽廃」が迫っている、とは認定されません。
これに対して、期間を合意している場合(=法定期間よりも長い、すなわち堅固建物の場合は30年以上、非堅固建物の場合は20年以上の期間を合意した場合)には、この期間内にたとえ「朽廃」しても借地権は消滅しません。言うまでもありませんが、合意された借地期間中の残期間中に建替をすることが予想されるからです。よって、たとえ建物の「朽廃」が近いと判断された場合でも、建替を求めて申立てられた増改築許可の申立てを棄却する理由にはならないとされます。
③2つの土地に借地上の(建替後の)建物が跨がる場合
跨がり(またがり)建物というのは、複数の土地の上に建っている一つの建物のことです。同じ土地所有者が所有する複数の土地の上に建っている場合には問題はありません。問題は、所有者が異なる複数の土地の上に一つの建物が建っている状態です。借地の場合には、借地の隣に例えば、借地権者が所有する土地があって、2つの土地の上に1つの建物を建てようとする場合が問題となります。
この場合、将来、地主が借地を返してもらおうと思っても、建物が別の権利者の土地(上記のケースでは借地権者の所有する土地)の上にもあるため、紛争にまで至らなくても複雑な権利関係になる可能性があります。一度建てた建物を、その敷地の区分に応じて分離することは不可能または著しく困難です。そのため、建替え前から元々「跨がり建物」だった場合を除いては、増改築の許可は認めない、というのが裁判所の扱いです。(*1)
ただし、増改築許可申立てをする場面はこれから建物を建てる場合ですから、設計の段階から跨がり建物だとしても例外的な取り扱いが認められるような建物の設計をすることは可能です。その場合は認めるべきではないかという議論もあります。例えば、境界に跨がって(ちょうど境界線部分で分離できるような)専有部分が2つの区分所有建物にしたり、同様に土地の境界に合わせて物理的に分離が可能な建物にしたりするなどです。
しかし、問題になった時(将来、借地を返す時等)に紛争となったら最終的に裁判所の判決などで建物の切断ができるのかとか、区分所有建物の共用部分の管理はどうするのかなど諸雑多な問題が起こる可能性があります。ただし、これらの問題は、将来、 借地権が消滅する場合に起こる問題で、一般的には、生じる可能性は低いものと思われます。また、「承諾料」「跨がり建物」に限らず増改築の承諾に絡んだ若干特殊な問題については、承諾料の増額をして和解で地主に認めてもらうという形で解決することもあり得ると思います。地主が話し合いでも承諾してくれない場合は、建替前に明らかになるわけですので、時間・費用・手間は二重にかかってしまうことになりますが、設計を変更して「跨がり建物」でない建物を建てる建築計画に変えた上で地主の許可(または裁判所の許可決定)をもらうことも検討すべきかと思います。
(*1) 借地権の譲渡について、地主の承諾に代わる裁判所の許可の手続の中で、「跨がり建物」がある場合、地主が介入権を行使したしても、原則として介入権は認められないとされています。言うまでもありませんが、介入権行使の結果、譲渡の対象となる「建物」を巡る権利関係が複雑になり過ぎるからです。
④建替えにより分譲マンションを建設する場合
分譲マンションの場合、マンション内の戸数に応じて、マンション各部屋(専有部分)の売却が予定されます。そして、借地上に建つマンションの場合、各部屋ごとに借地権が成立することになります(*1)。つまり、分譲マンションが建つと、 地主は、多数の借地権者を相手に複雑な問題を抱えることになります。そのため、地主が反対している場合には、借地人が増改築許可の申立をしても、裁判所は分譲マンションへの建替は許可しない扱いです。 (*1) 借地上に分譲マンションを建てる場合、業者が借地権者としてマンションを建てて分譲します(借地権の(準)共有持分の譲渡です。譲渡のときに地主の承諾が必要になります)。このため、一個の借地権を区分所有者が(準)共有することになります。この場合でも、結局は各区分所有者ごとに借地契約が成立している場合と同じ問題が起こります。また、開発業者が借地権者になり、各区分所有者に転貸する方法もあります(転貸するのにも地主の承諾が必要です)。しかし、借地権者である分譲業者(デベロッパー)が、わざわざ上記のような借地権者と地主との紛争含みとなる開発を行うのかどうかについては疑問が残ります。開発業者は、どちらかと言えば、開発・販売だけして、結局、言葉を悪く言えば「売り逃げ」したいだけでしょう。

投稿者プロフィール
- 弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県で約30年にわたり弁護士として活動しており、特に不動産分野に注力してきた。これまでの不動産関連のご相談は2,200件を超え、550件ものご依頼を受任。豊富な経験と知識で、常に依頼者にとって最良の結果を追求している。特に、不動産の共有関係や借地関係の解決には強い関心を持ち、複雑な問題も粘り強く解決に導く。
最新の投稿
- 2025.08.06不動産トラブルのセカンドオピニオンを検討中の方へ
- 2025.04.18不動産の使用貸借の終了に伴う立退きについて
- 2025.04.15定期借家契約の活用術
- 2025.04.15Q.自身が所有している不動産が競売にかけられているが、どうにかしたいです。
- 借地の更新の際に支払う金銭トラブル
- 借地上の建物の建替えでよくあるトラブルとは?増改築禁止特約を弁護士が解説
- 借地権の譲渡におけるトラブルとは?地主の承諾が得られない時の対応方法を解説
- 借地への抵当権設定においてよくあるトラブルとは?
- 借地の共有持分の譲渡におけるトラブルとは?
- 借地権の遺産分割の適切な方法とは?
- 借地の更新拒絶が認められる正当事由とは?立退料の設定金額について弁護士が解説
- 借地からの立ち退きに関わる問題を横浜の弁護士が解説
- 借地人が立退きを求められた時、弁護士に相談すべき理由とは?
- Q&A | 「借地権の買取などとんでもない。借地契約を終了させるならすぐに更地にして返してもらいたい!」強硬な地主のために窮地に陥った借地人…借地人側としては何か対抗する手段はないのでしょうか?」
- Q&A | 借地人による「借地権の譲渡」を承諾することの対価として「承諾料」520万円を受け取った地主…譲渡契約が白紙になったことで「支払った承諾料を返して欲しい」と返還を求められましたが、地主は返金する必要があるのでしょうか?