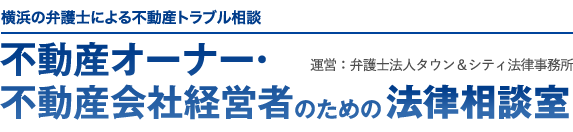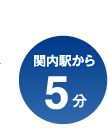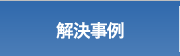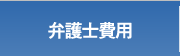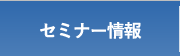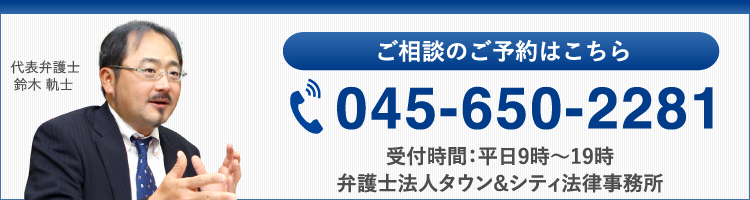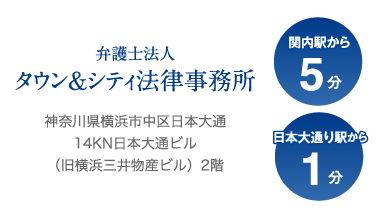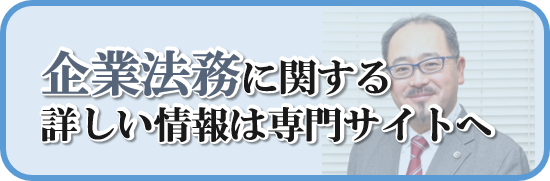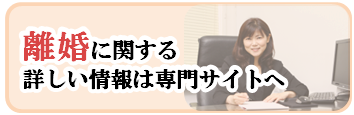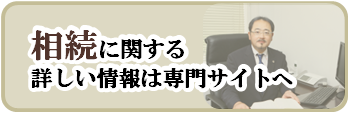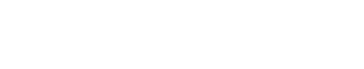共有物分割~共有関係の「解消」と共有者間の「清算」~
Contents
そもそも「共有」とは何か
1 共有とは
「共有」とは、複数人で1つの物を所有している状態をいいます。動産か不動産かを問わず、「共有」は成立します。この複数人で所有している1つの物を「共有物」、所有している複数人をそれぞれ「共有者」といいます。
なお、「共有」はあくまで複数人で1つの物を「所有」している状態のことをいうので、例えば、「所有してはいないがその物を使わせてもらっている」という状態は共有には該当しません。この場合は、その物を使わせてもらうことに対して対価を支払っていれば「賃貸借」、支払っていなければ(=ただで使わせてもらっているのであれば)「使用貸借」に該当し、「共有」の前提である「所有」はしていない法律関係になります。
2 複数人で1つの物を「所有」しているとはどういうことか
複数人で1つの物を「所有」しているというのは具体的にどういうことなのか、イメージしにくいかもしれません。結論からいうと、その物を所有している複数人が、それぞれ一定の割合で1つの「所有権」を分け合っている状態です。つまり、「共有者」は、「共有物」について100%の所有権を有しているのではなく、それぞれが一定の割合で所有権を有しているに過ぎません。
その結果、後述のとおり、「共有物」の利用や管理に様々な制約を受けることになります。そして、この、共有者それぞれが有する所有権の一定の割合を「共有持分」といいます。
例えば、ルームシェアをしているABCDの4人がお金を出し合って冷蔵庫を買ったとしましょう。この場合、通常、冷蔵庫はABCDの共有になると考えられます(4人で利用する前提で全員がお金を出し合って購入した物だから)。つまり、ABCDはそれぞれこの冷蔵庫の「共有者」ということになります。そして、ABCDが有する所有権の割合が平等だとすれば、共有者ABCDの「共有持分」はそれぞれ25%(4分の1)ということになります。つまり、ABCDはそれぞれ、この冷蔵庫に対して4分の1の「共有持分」を有する共有者、ということになります。
3 共有者の有する所有権の割合=「共有持分」はどのようにして決まるのか
上の例では、ABCDが冷蔵庫に対して有する所有権の割合=「共有持分」を平等であるとしましたが、必ず平等であるわけではありません。では、「共有持分」はどのようにして決まるのでしょうか。これは、基本的には共有者間の合意によって決まります。例えば、上の例で、ABCDが購入した冷蔵庫について、それぞれの共有持分をA:70%(100分の70)、B:20%(100分の20)、C:5%(100分の5)、D:5%(100分の5)とすることも、共有者であるABCD全員が合意すれば可能です。もし、「合意」がない場合には、各共有者が平等に持分を有するものと推定されます(上記の例だと各100分の25ずつ)。
ただ、この冷蔵庫のように複数人で1つの物を購入したことにより「共有状態」が発生する場合、各共有者の共有持分はそれぞれが購入のために支払った金額に応じて決められるのが一般的です。例えば、上の例で、ABCDがお金を出し合って購入した冷蔵庫の金額が100万円だったとしましょう。この時、Aが50万円、Bが30万円、Cが10万円、Dが10万円をそれぞれ出したとしましょう。この場合、各自が出した金額に応じ、その「共有持分」についてもA:50%(100分の50)、B:30%(100分の30)、C:10%(100分の10)、D:10%(100分の10)と合意することが一般的です。
このように、「共有持分」は基本的には共有者の合意によって決めることができます(一般的な決め方は前述のとおりです)。なお、共有持分の割合は、共有者間の合意や法律上の定め等がない場合には、上記のとおり、それぞれ平等であると推定されます(民法250条)。
しかし、例外的に「共有持分」が法律の定めによって決められる場合もあります。それが、相続によって共有状態が発生する場合です。例えば、土地を(単独で)所有していたEが死亡し、その相続人が配偶者であるF、子であるG、同じく子であるHであるとしましょう。この場合、死亡したEが所有していた土地については、相続人であるFGH全員の合意による遺産分割が成立するか、家庭裁判所による遺産分割審判が確定しない限り、その所有権を誰が取得するのか決まりません。
しかし、それでは、FGHの間で遺産分割が成立するか、家庭裁判所による遺産分割審判が確定しない限り、いつまでもEが所有していた土地の所有権がどうなるのか決まらないことになってしまいます
そこで、このような場合には、FGHの間で遺産分割が成立するか、家庭裁判所による遺産分割審判が確定し、土地の所有権がどうなるか決まるまでの間、暫定的にこの土地は相続人であるFGHの共有状態になるとされています。この共有状態は、相続に伴い暫定的に発生しているもので、未だ確定しているものではないため、純粋な「共有」と区別して、「遺産共有」(状態)と呼ばれます。
そして、この「遺産共有」(状態)については、遺産分割が完了していない段階の話であり、共有者(=相続人)間の合意に基づいてそれぞれの「共有持分」を決めることができないので、その「共有持分」は民法で定められた「法定相続分」に応じて決められます。具体的には、上の例でいうと、相続人Fは被相続人Eの配偶者であるので民法上50%(2分の1)の法定相続分を有しています。相続人GHは共に被相続人Eの子であるので民法上それぞれ25%(4分の1)の法定相続分を有しています。そこで、遺産分割が成立するか、家庭裁判所による遺産分割審判が確定し、土地の所有権がどうなるか決まるまでは、Eが所有していた土地については、FGHの「遺産共有」状態となり、その共有持分はFGH各自の「法定相続分」に応じてF:50%(2分の1)、G:25%(4分の1)、H:25%(4分の1)とされます。
このように、相続に伴う「遺産共有」状態における「共有持分」については、共有者間の合意ではなく、法律(民法)の定めによって決められることになります。ちなみに、令和6年4月1日に改正不動産登記法が施行され、不動産について、相続に伴う「相続登記」を一定期間内に行うことが義務化されました。この「相続登記」は、遺産分割が完了しているか否かに関わらず行わなければならないとされているため、遺産分割が完了していない段階で行う場合には、上記の「遺産共有」状態を前提に、各相続人の「法定相続分」に応じた「共有持分」に基づいて行うことになります。そして、その後に遺産分割が完了し、相続人各自の「共有持分」に変動が生じた場合には、再度、「遺産分割」を原因とする登記手続を行うことになります。
共有者の権利
1 共有物の利用
共有者は、共有物に対して所有権を有しています。そのため、当然、「所有権」に基づいて共有物を利用する権利を持っているはずです。しかし、前述したとおり、各共有者の有する所有権は100%の完全なものではなく、各自の「共有持分」に応じた一定割合のものに過ぎません。
そうすると、各共有者はどのように共有物を利用することができるのでしょうか。
この点、各共有者は、それぞれ、自己の共有持分に基づき、共有物の「全部」を利用することができます(民法249条1項)。例えば、IJKの3人がお金を出し合って車を買い、各自の共有持分をそれぞれ3分1にしたとしましょう。この場合、IJKが3人一緒に車に乗れば、一度に全員が共有物である車を利用できるので、問題はありません。しかし、Iが1人で車を使いたい場面もあるでしょう。このときIは1人で車を利用することができないのかというと、そうではありません。Iは自身の共有持分3分の1に応じて車を全部利用できる、すなわち1人で利用することができます。但し、後述のとおり、共有物の利用を各共有者の全くの自由にゆだねると、共有物の管理上の問題が生じてしまうことから、共有物を各共有者がそれぞれどのように利用するのかについては、共有物の管理に関する事項として民法252条1項に基づいてあらかじめ定めておく必要があります。つまり、共有者は、民法249条1項に基づき、自身の共有持分に応じて共有物の全部を利用する権利を有していますが、全く個人の自由に利用できるわけではなく、民法252条1項に基づいて共有者間で定めたルールに従って利用しなければならないのです。
本来、単独所有であれば所有者自身が個人の自由にその所有物を利用することができますが、複数人で1つの物を所有しているという「共有」の性質上、他の共有者も共有物を利用できるよう調整が必要になり、その結果、各共有者の利用は「民法252条1項で定めたルールに従わなければならない」という形で制約を受けることになるのです。もう少しわかりやすく言うと、共有者全員に共有物を利用する権利があるので、特定の共有者が好き勝手に共有物を利用することは許されない、ということです。
このように、「共有」であることの性質上、一定の制約は受けますが、各共有者は各自の共有持分に応じて共有物の全部を利用することができます(民法249条1項)。一方で、共有者は、他の共有者の同意なく共有物を変更することはできません(民法251条1項)。ここでいう「変更」は共有物の現状を変えてしまう行為を指します。建物を共有している場合にこれを増改築する行為や畑である土地を共有している場合にこれを宅地に造成する行為などが該当します。また、上のように物理的に別の物に変更してしまう行為だけではなく、共有物を売却する行為(=処分する行為)などもこの「変更」に含まれるので、他の共有者の同意がない限り、行うことはできません。例えば、上の車の例でいえば、IJKはいずれも他の共有者全員の同意を得ない限り、車を改造して全く違う性能を有する車に造り変えたり、車を売却したりすることはできません。この民法251条1項に定める他の共有者の同意を得ない共有物の変更の禁止は、各共有者が各自の共有持分に応じて共有物の全部を利用する権利を有していることからすれば(民法249条1項)、当然の規制といえるでしょう。本来、自分が単独で所有していれば、その所有物を「変更」することも個人の自由ですが、複数人で1つの物を所有する「共有」の性質上、このような制約を受けることになるのです。つまり、共有者全員に共有物を利用する権利があるので、特定の共有者が好き勝手に共有物を利用することが許されないのと同じように、特定の共有者が好き勝手に共有物を変更することは許されないということです。
2 共有物の管理
共有物の管理とは、共有物の利用や、改良のための行為を指します。例えば、共有物の利用のための行為として各共有者が円滑に共有物を利用するためのルールを定める行為、共有物を改良するための行為として宅地を共有している場合にこれを整地する行為や建物を共有している場合にこれを改装(但し、増改築や改造に至らない程度)する行為などが挙げられます。このような「管理行為」については、共有者の共有持分の価格に従い、賛成が過半数を超えていなければ、行うことができません(民法252条1項)。
つまり、各共有者は民法252条1項に基づく限りにおいて、共有物の管理行為を行う権利を有していることになります。本来、物を単独所有していれば、そもそも利用のためのルールを定める必要などなく、「改良」行為も所有者個人が自由に行えます。しかし、ここでも複数人で1つの物を所有する「共有」の性質上、このような制約を受けることになるのです。
共有物の「利用」のためのルールを定める行為がここでいう「管理」に含まれるのは少しわかりづらいと思いますので、上の車の例を使って説明します。上記のとおり、IJKは、共有物である車について、各自がその共有持分(3分の1)に応じて車の全部を利用する権利を有しています(民法249条1項)。そのため、IJKはそれぞれ1人で車を利用することができますが、一方で、IJKが1人で車を使いたいタイミングが重なってしまうと、揉め事になりかねません。仮に、揉め事にならないとしても、各自が自由に1人で車を使えるということになると、「今誰が車を使っているのか」「今車がどこにあるのか」等をIJK=各共有者が把握できないことにもなりかねず、共有物としての車の「管理」という点で問題があります。
そこで、共有者の間で、共有物の利用に関する事項=ルールを共有物の「管理」に関する事項としてあらかじめ定めておく必要が出てきます。このことから、共有物の利用のためのルールを定める行為については、民法252条1項の「管理」に含まれるものとされているのです。
そして、各共有者は、このあらかじめ定められたルールに従い、共有物を実際に利用することになります。具体的には、IJKはその共有持分の価格に従い、過半数の賛成に基づき車の利用に関するルールを定め、そのルールに基づいて各自が車を利用することになります。例えば、IJKが1週間ずつ交代で使う、というようなルールをあらかじめ定めておくことになります。なお、共有物の管理に関する事項は、共有者各自の共有持分の価格に従い、その過半数で決めることになりますので、各自が3分の1ずつの共有持分を有するIJKの間では、3人のうち2人の賛成により具体的な利用のルールを定めることになります。
なお、前述したとおり、各共有者はそれぞれ自身の共有持分に応じて共有物の全部を利用する権利を有していますので(民法249条1項)、たとえ、各共有者の共有持分の価格に従い、過半数の賛成を得ているとしても、特定の共有者に共有物を一切利用させないような形で共有物の利用についてのルールを定めることはできません(定めたとしても無効となります)。
3 共有物の保存
共有物の保存とは、共有物の現状を維持するための行為をいいます。例えば、共有物を修繕する行為などが該当します。このような保存行為については、上記の管理行為とは異なり、各共有者がその共有持分にかかわらず単独で行うことができます(民法252条5項)。つまり、各共有者はそれぞれ単独で共有物の保存行為を行う権利を有しています。
これは、共有物が壊れている等、各共有者の利用自体を妨げる事情があった場合に、各共有者が迅速に修繕等の対応をできる必要があり、かつ、この修繕等については共有者全員の利益になるので、他の共有者の同意を事前に得ておく必要はないからです。
なお、例えば、共有となっている土地について、第三者が不法に占有しており、各共有者の利用が妨げられている場合に、当該第三者に対して明渡請求を行うことも共有物の現状を維持するための「保存行為」に含まれるので、各共有者は当該第三者に対して「単独」で明渡請求ができます。
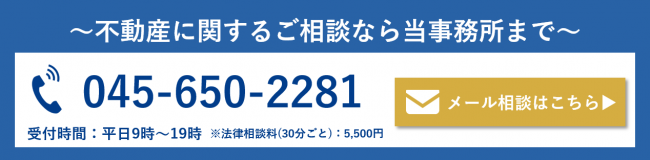
共有者の義務
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負います(民法253条1項)。これは、複数人で1つの物を所有している以上、いわば当然の義務といえます。
共有者同士の関係
1 特定の共有者が独占的に共有物を利用している場合
共有者同士の関係を考える場合に、最も問題となるのが、特定の共有者が独占的に共有物を利用している場合、すなわち他の共有者に共有物を利用させない場合に、他の共有者から当該共有者に何ができるのか、という点です。上の車の例でいうと、IJKが共有している車について、Iが1人でずっと利用しており、他の共有者であるJKに全く車を利用させない、という場合に、JKはIに対してどのような請求ができるのかという問題です。
まず、Iは、自身の共有持分に応じて、民法252条1項に基づいて定められる共有物の利用のルールに従い、共有物としての車の全部を利用する権利を有していますが、当然、他の共有者であるJKに全く利用させない形で独占的に利用する権利はありません。そうすると、IJK間で民法252条1項に基づく利用のルールが定められているにせよ、まだ定められていないにせよ、このようなIの車の利用は、他の共有者であるJKの権利(各自の共有持分=一定割合の所有権に応じて、共有物の全部を利用する権利)を侵害していることになります。
このように、Iの独占的な共有物の利用により、自身の権利を侵害されているJKはIに対してどのような請求ができるのでしょうか。
まず、考えられるのが、JKからIに対して共有物である車の引渡を求めるという方法です。
これが認められれば、Iから引渡を受けた共有物としての車をJKがそれぞれ利用することができるようになり、JKの権利が侵害されている状態は解消されます。
しかし、判例の考え方からすると、この請求は認められないものと考えられます。
具体的には、最高裁判所 昭和41年5月19日判決(最高裁判所民事判例集20巻5号947頁)において、最高裁判所は、共有物である建物を単独で占有(利用)している共有者に対する他の共有者からの明渡請求を否定しています。事案は、純粋な共有ではなく前述の「遺産共有」に関するものですが、概要は次のとおりです。相続によって共同相続人の遺産共有(状態)となった建物について、共同相続人(=共有者)の1人(その共有持分は全体の過半数に満たない)が、他の共同相続人ら(=共有者ら)との協議を経ることもなく、当該建物に単独で居住しこれを占有したことから、他の共同相続人ら(各共有持分の合計が全体の過半数を超える)が当該共同相続人に対し、当該建物の明渡を求めた、という事案です。
この、他の共同相続人ら(=共有者ら)からの建物の明渡請求について、最高裁判所は、「思うに、共同相続に基づく共有者の1人であって、その持分の価格が共有物の価格の過半数に満たない者(以下単に少数持分権者という)は、他の共有者の協議を経ないで当然に共有物(本件建物)を単独で占有する権限を有するものでないことは、原判決の説示するとおりであるが、他方、他のすべての相続人らがその共有持分を合計すると、その価格が共有物の価格の過半数をこえるからといって(以下このような共有持分権者を多数持分権者という)、共有物を現に占有する前記少数持分権者に対し、当然にその明渡を請求することができるものではない。けだし、このような場合、右の少数持分権者は自己の持分によって、共有物を使用収益する権限を有し、これに基づいて共有物を占有するものと認められるからである。従って、この場合、多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡を求めることができるためには、その明渡を求める理由を主張し立証しなければならないのである。」と判示した上で、本事案ではこの点についての主張・立証が何らなされていないことを理由に、否定しました。
この判例の趣旨は、たとえ共有者の1人が共有物を独占的に利用している場合であっても、当該共有者は自身の共有持分に応じて共有物の全部を利用する権利を有しているので、他の共有者らからの共有物の引渡(共有物が不動産であれば明渡)請求が当然に認められるものではない、というところにあると考えられます。
つまり、共有者の1人による共有物の利用が他の共有者の権利を侵害する独占的なものであったとしても、当該共有者自身も民法249条1項に基づき自身の共有持分に応じ共有物の全部を利用する権利を有しているので、その利用自体が当然に否定されるものではない、ということになります。
判例がこのような見解を採る根拠としては、次の点が考えられます。すなわち、上の車の例に当てはめて考えますが、仮にJKからIに対する車の引渡請求が認められると、Iは車をJKに対して引き渡すことになります。しかし、そうすると、今度はIが車を全く利用できないことになりますので、理論上、IからJKに対して車の引渡を請求できることになってしまい、以後、JKとIの間で相互に車の引渡請求が繰り返されてしまう可能性があります。このように、共有物を独占的に利用する特定の共有者に対する他の共有者からの(共有物の)引渡(明渡)請求が認められてしまうと、以後、各共有者の間で、相互に(共有物の)引渡(明渡)請求が繰り返されてしまうおそれがあります。
上記判例は、この点を懸念して、他の共同相続人ら(=共有者ら)(上記判例内でいう「多数持分権者」)から当該建物を単独で占有している共同相続人(=共有者)(上記判例内でいう「少数持分権者」)に対する建物明渡請求を、「当然に認められるものではない」として否定したのだと考えられます。
以上のことからすると、JKからIに対して、共有物である自動車の引渡を求めることはできないものと考えられます。
では、JKはIに対してどのような請求ができるのでしょうか。この点、前述のとおりJKはIに対して共有物である自動車の引渡を求めることはできないと考えられますが、Iによる車の独占的な利用により、JKは共有物=車に対する共有持分=一定割合の所有権に基づく利用権(民法249条1項)を侵害されていることは事実ですので、共有物である車を利用できなかったことにより発生した損害の賠償を求めることはできると考えられます。
また、JKは現実に共有物である車を利用することができない状態にある以上、そもそも車をIと共有している意味はないと考えられます。そこで、Iに対して後述の「共有物分割請求」を行うことも考えられます。詳細については後述しますが、この「共有物分割請求」は共有物を分割することで、問題の根本的な原因である「共有関係」そのものを解消するとともに共有者間の関係を「清算」するための制度です。なお、ここでいう「分割」は「共有関係をどのように公平に清算するか」という観点からの概念なので、共有物を物理的に分割して分け合うという方法だけではなく、共有物を共有者の1人に単独取得させる代わりに当該共有者から他の共有者に対してお金(代償金といいます)を支払わせる方法(「代償分割」といいます)や、共有物を売却してお金に換えた上で分け合う方法(「換価分割」といいます)も含まれます。
むしろ、共有物は、そのほとんどが物理的な分割になじまないので(例えば、土地、建物、車、冷蔵庫やテレビ等の家具類等)、実際の分割の場面では、単純に物理的に分割して分け合うという方法が採られることはほとんどなく、上記の2つの分割方法のうちいずれかの方法が採られることになります。
2 共有持分の譲渡
前述したとおり、共有者は、各自が共有物に対して共有持分を有し、この共有持分に応じた一定割合の所有権を有しています。そして、この共有持分=一定割合の所有権に応じて、共有物の全部を利用する権利を持っています(民法249条1項)。
通常、物の所有者はその物=その物の所有権を第三者に譲渡できます。そして、各共有者も共有物に対して共有持分=一定割合の所有権を持っていますので、これを第三者に譲渡することができます。なお、共有者は、共有物に対して「共有持分」という形で一定割合の所有権を有しているだけなので、自身の共有持分を超えて共有物そのものを第三者に譲渡したりすることはできません。
共有者の1人の共有持分が第三者に譲渡された場合、当該譲渡した共有者は共有持分を失うので、共有者ではなくなり、共有関係から離脱します。その代わりに、当該共有者からその共有持分の譲渡を受けた第三者が新たな共有者となります。
つまり、共有持分の譲渡により共有者が入れ替わることになります。例えば、上の車の例でいえば、共有者の1人であるIが第三者であるLにその共有持分(3分の1)を譲渡した場合、Iは共有者ではなくなる一方、Lが新たな共有者となり、車はJKLの共有となります(共有持分はそれぞれ3分の1ずつ)。
「共有物分割請求」が共有者としての立場を前提に、他の共有者に対して共有関係の解消と清算を求めるものであるのに対し、「共有持分の譲渡」は共有持分を譲渡した共有者のみが共有関係から離脱するものの、共有持分の譲渡を受けた第三者と他の共有者との間で共有関係自体はその後も継続されるため、共有関係の解消と共有者間の清算を伴わないという点で全く異なります。
以上のことからわかるとおり、「共有持分の譲渡」は自分だけが共有関係から離脱したいときに使われます。この「共有持分の譲渡」が認められている以上、「共有物」については、常にその「共有者」が入れ替わる可能性を孕んでおり、各共有者同士の関係は強固であるとはいえません。そのため、場合によっては、全くの第三者が共有持分の譲渡を受けることにより共有者となることがないよう、各共有者間であらかじめ「他の共有者の承諾なく共有持分を第三者に譲渡することを禁止する」旨の合意をしておくなどの対策を講じておく必要がある場合も考えられます。
3 共有者の死亡
共有者の1人が死亡した場合には、その共有者が有していた共有持分は遺産として相続の対象となります(共有持分は共有物に対する一定割合の所有権だから)。
死亡した共有者に相続人がいる場合には、当該共有持分を相続した相続人が新たな共有者となります。例えば、上の車の例で、共有者であるIJKのうちJが死亡し、Jの相続人であるMがJの共有持分を相続した場合、車はIKMの共有となります(共有持分はそれぞれ3分の1ずつ)。
つまり、共有持分が第三者に譲渡された場合だけではなく、共有者が死亡した場合にも、当該共有持分が相続されれば、共有者が入れ替わることになります。
なお、当該死亡した共有者に相続人がなかった場合には、その共有持分は他の共有者に帰属します(民法255条)。例えば、上の例で、死亡したJに相続人がいなかった場合、Jが有していた共有持分3分の1については、原則として他の共有者であるIKに帰属することになります。具体的には、IK間に特別の合意等がない限り、Jの有していた共有持分をIKで平等に分け合うことになり、車についてはIKともに共有持分2分の1ずつ(元々のIKの各共有持分3分の1=6分の2に、Jが有していた共有持分3分の1×2分の1=6分の1を加えた6分の3=2分の1)の共有となります。
このように、共有者の1人が死亡し、相続人がない場合には、その共有持分は原則として他の共有者に帰属するので、この場合には共有者の人数が減る(=その分、他の共有者の共有持分が増加する)だけで、共有者の入れ替わりはありません。
共有物分割請求
1 共有物分割請求とは
先程、少し触れましたが、「共有物分割請求」は、文字どおり共有物を分割することで、問題の根本的な原因である「共有関係」そのものを解消するとともに共有者間の関係を「清算」するための制度です。
共有関係それ自体の「解消」と共有者間の「清算」を伴うので、共有物の分割を求める共有者は他の共有者「全員」に対して共有物分割請求をしなければなりません。なお、後述の「共有物分割請求訴訟」を提起する場合も、共有者全員を原告あるいは被告のいずれかに含める形で「当事者」にしなければなりません(なお、あくまで参考ですが、このように関係者全員を当事者にしなければならない訴訟を「固有必要的共同訴訟」といいます)。
2 共有物分割請求が認められるのは何故か
このような「共有」関係それ自体の「解消」と共有者間の「清算」を目的とする「共有物分割請求」が認められるのは何故でしょうか。それは、「共有」が1つの物の「所有権」を複数人で分け合っている状態であり、不完全なものだからです。前述のとおり、「共有」は、1つの物=「共有物」について、複数人の「共有者」が「共有持分」という形でそれぞれ一定割合の所有権を持ち合っている状態です。各共有者がそれぞれ一定の割合の所有権しか持っていないため、例えば、他の共有者の同意を得なければ共有物を変更することができない(民法民法251条1項)、管理行為については各共有持分の価格に従い、過半数の賛成を得なければ行うことができない(民法252条1項)など、各共有者の「所有権」は本来の完全な「所有権」に比べて大きく制約されています。つまり、各共有者の共有持分=一定割合の所有権は不完全な権利ということになります。このように、複数人の共有者が1つの物について不完全な権利を持ち合っているという状態は、各共有者間の利害の対立を招き、紛争(例えば、上記の「特定の共有者による共有物の独占的な利用」など)になりやすいというリスクがあります。そこで、各共有者に、リスクのある「共有関係」それ自体の解消と共有者間の清算を求める権利=共有物分割請求を行う権利が認められるのです。
なお、共有物の分割が問題となるのは、ほとんどの場合、不動産=土地・建物が共有となっている場合です。不動産は、一般的に価値が高いことが多く、その取得を希望する共有者がいる場合も多いため、共有関係を解消するにあたり、共有者間の清算をどのようにするかについて、紛争となることが多いからです。
例えば、土地を共有している場合に、共有者の1人がその土地上に自宅を建てて住んでいると、当該共有者はその土地の取得を希望するでしょうし、建物を共有している場合に、共有者の1人がその建物に居住している場合には、当該共有者はその建物の取得を希望するでしょう。このような場合、前述した「特定の共有者による共有物の独占的な利用」からトラブルとなり、その結果、「共有物分割請求」がなされたものの、共有物の「分割」を巡って更なるトラブルとなることも非常に多くあります。
そこで、以下では、共有物が不動産=土地・建物であることを前提に説明します。
3 共有物分割請求の具体的な方法
(1)協議
まず、各共有者は、いつでも他の共有者に対し、共有物の分割を請求することができます(民法256条1項)。なお、前述のとおり、共有物分割請求は、「共有」関係そのものの「解消」及び共有者間の「清算」を目的としているので、他の共有者「全員」に対して行わなければなりません。共有物分割請求がされると、まずは各共有者間の「協議」により共有物の分割と共有者間の清算を試みることになります。
(2)共有物分割請求訴訟
次に、共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、共有物の分割を求める共有者は裁判所に対し、「共有物分割請求訴訟」を提起することができます(民法258条)。共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、または協議をすることができないとき、に初めて「共有物分割請求訴訟」を提起することができるので、協議が可能であるにもかかわらず協議をしていない、というような場合には共有物分割請求訴訟を提起することはできません(提起したとしても、訴訟要件を満たしていないものとして却下されます)。
但し、「協議」といっても、事前に家庭裁判所における調停手続(=裁判所を介した話し合いの手続)まで経ている必要はないとされていますので、共有者間で任意に協議を試みたが、一部の共有者が分割に反対して協議がまとまらなかったという場合や、一部の共有者が協議を行うこと自体を拒絶したために協議が行えなかったという場合などは、問題なく「共有物分割請求訴訟」を提起することができます。
(3)まとめ
このように、共有物分割請求については、まずは「協議」で、これが調わなければ(あるいは協議自体ができなければ)、「共有物分割請求訴訟」を提起する、という形で行うことになります。
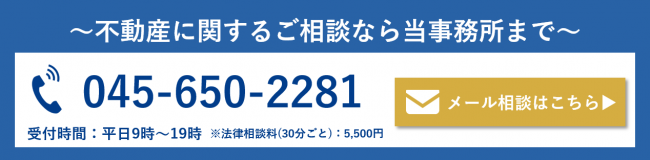
共有物の具体的な分割方法
1 共有物分割における基本的な考え方
共有物分割請求を行ったとして、実際、どのように共有物を分割するのでしょうか。
共有物分割請求は、「共有」関係そのものを「解消」するとともに、各共有者間の「清算」を行うためのものです。そのため、各共有者間の「公平」が最も重要な要素となります。つまり、特定の共有者だけが損をするような分割方法を採ることは基本的にできません。もちろん、「協議」により共有者全員の合意が取り付けられる限り、分割方法は自由に決められますが、自分が損をするような分割方法を敢えて受け入れる共有者は通常いないでしょうから、やはり共有者間の「公平」を欠くような分割方法は認められないものといえます。
このように、共有者間の「公平」を確保する、というのが共有物分割における基本的な考え方となります。
共有物の分割において、各共有者間の「公平」を確保するには、共有物そのものを物理的に分割して平等に分け合うというのが一番簡単な分割方法です。しかし、先程も少し触れたとおり、共有物はそのほとんどが物理的な分割になじまないので、共有物自体を直接物理的に分割して、各共有者間で平等に分け合う形で分割を行うことは基本的にできません。例えば、3人の共有者が建物を共有している場合、これを分割する(=共有関係を解消する)際に、建物自体を物理的に3つに切り分けて、各共有者がそれぞれ切り分けた建物の1つを取得する、というのは余りにも非現実的な話です。
そこで、基本的には、共有物の分割は、次の「代償分割」「換価分割」という2つ分割方法のうち、いずれかの方法で行うことになります。
2 代償分割
まず、共有物を特定の共有者が取得し、他の共有者との関係は当該共有物を取得する特定の共有者から他の共有者に対してそれぞれの共有持分に応じた適切な金額のお金を支払うことで清算する、という分割方法です。共有物の取得を希望する共有者がいる場合に使われます。本来、共有物の取得を希望する共有者が共有物を取得するのが一番望ましい分割方法です。しかし、単にその取得を希望する特定の共有者が共有物を取得するのでは、他の各共有者は自身が有している共有持分=一定割合の所有権を一方的に失うことになり、共有物分割において最も重要な共有者間の「公平」に反することになります。そこで、共有物を取得する特定の共有者が、自身が共有物を取得することによって他の共有者に生じてしまう損失をお金で償う、というのがこの分割方法です。ここで、他の共有者に生じてしまった損失を償うために特定の共有者が他の各共有者に対して支払うべきお金を「代償金」といいます。そして、共有物を取得した特定の共有者から他の共有者全員に対して「代償金」を支払う形で共有物を分割するので、この分割方法を「代償分割」といいます。
この「代償分割」において、共有物を取得する特定の共有者が他の各共有者対して支払うべき「代償金」の具体的な金額は、原則として、共有物を金銭で評価した金額(評価額)に各共有者それぞれの共有持分の割合を乗じて算出します。例えば、NOPの3名が土地をそれぞれ3分の1ずつの共有持分にて共有している場合に、NがOとPに対して共有物の分割を請求したとしましょう。このとき、Nが共有土地を取得したいと希望し、Nが共有土地を取得する形で「代償分割」を行う場合、NはOとPに対してそれぞれ「代償金」を支払うことになります。
前述のとおり、「代償金」は共有物の評価額に各共有者の共有持分の割合を乗じて算出します。仮に上の共有土地の評価額が3000万円だった場合、NはOに対して1000万円(土地の評価額3000万円×Oの共有持分割合3分の1)、Pに対して1000万円(同上)を、それぞれ「代償金」として支払い、共有土地を(単独)取得することになります。
一方で、仮にこの共有土地の評価額が4500万円だった場合、NはOに対して1500万円(共有土地の評価額4500万円×Oの共有持分割合3分の1)、Pに対して1500万円(同上)を、それぞれ「代償金」として支払わなければならないことになります。
このように、「代償分割」においては、共有物の「評価額」によって、共有物を取得する共有者が他の各共有者に対して支払うことになる「代償金」の具体的な金額が変動することになります。そして、共有物を取得する共有者は他の各共有者に支払うべき「代償金」の金額をなるべく減らしたいと考えるのが通常である一方、「代償金」の支払を受けるべき他の各共有者は自身が支払を受ける「代償金」の金額をなるべく増やしたいと考えるのが通常なので、その利害が真っ向から対立し、共有物の「評価」を巡って共有者の間で紛争となることが非常に多いというのが現実です。そのため「代償分割」では、共有物の「評価額」をどのように決めるのか、すなわち共有物をどのように「評価」するのか、が最も重要な問題となります。
3 換価分割
次に、共有物を共有者全員で共同して売却し、お金(売却代金)に換えた上で、このお金を各共有者の共有持分に応じて分ける形で分割する、という方法です。共有物の取得を希望する共有者がいない場合に使われます。共有者のいずれも共有物の取得を希望していない場合には、共有物を売却し、お金に換えた上で分割するのが最も簡便かつ合理的な分割方法です。
共有物を売却してお金に換えた上で分割するので、この分割方法を「換価分割」といいます。
この「換価分割」においては、共有物の売却代金を共有者間で分け合うことになるので、「共有物がいくらで売れるのか」が最も重要な問題となります。例えば、上の共有土地の例で、NOPが共同して共有土地を売却し、9000万円で売れたとしましょう。そうすると、NOPはこの売却代金9000万円(但し、仲介手数料等、売却代金の中から支払われるべきいわゆる諸経費についてはここでは考えないこととします)を各自の共有持分3分の1ずつで分けることになります。その結果、NOPはいずれも3000万円ずつ取得することになります。一方で、仮にこの共有土地を1億2000万円で売却できた場合には、NOPはこの1億2000万円(同上)を各自の共有持分3分の1ずつで分けることになり、それぞれ4000万円ずつ取得することができます。
このように、「換価分割」においては、共有物がいくらで売却できたのか、によって各共有者が取得できる金額が変動することになります。そのため、「換価分割」では、「共有物をいかに高く売却するか」という点について、各共有者の利害は基本的に一致し、共有者間の紛争は起きにくい、という特徴があります。
しかし、一方で、「換価分割」は共有物を共有者全員で共同して売却することが前提となるので、共有者のうちの1人でも売却に反対すると、そもそもこの分割方法を採ることができません。その意味では、「換価分割」は、実現できれば紛争は起きにくい方法ではあるものの、実現までのハードルは高い方法といえます。
4 まとめ
以上のとおり、共有物分割の具体的な方法としては、「代償分割」と「換価分割」があります。そして、共有物の取得を希望する共有者がいる場合には、「代償分割」(但し、当該共有物の取得を希望する共有者に「代償金」を支払えるだけの資力がそもそもない場合には、「代償分割」は行えません)、共有物の取得を希望する共有者がいない場合には、「換価分割」を、それぞれまずは検討することになります。
共有物を巡るよくあるトラブル
ここでは、これまで述べてきたことを前提に、共有物を巡るよくあるトラブルについて見ていきます。
なお、前述のとおり、実際に共有物を巡るトラブルが発生するのは、ほとんど共有物が不動産=土地・建物である場合なので、ここでも共有物が不動産=土地・建物であるという前提で説明していきます。
1 特定の共有者による共有物の独占的な利用
特定の共有者が共有物を独占的に利用し、他の共有者に利用させない行為は、他の各共有者が有する一定割合の所有権=共有持分に応じた共有物の利用権(民法249条1項)を侵害するものです。
このような特定の共有者の行為に対しては、他の共有者は、自身が共有物を利用できないことにより生じた損害について、賠償請求を行うことができます。
一方で、他の共有者も各自の共有持分に応じて共有物を利用する権利を有していますので、「自分にも共有物を利用させなさい」という意味で、理論上は、当該共有者に対して、共有物の明渡(共有物が不動産以外の物である場合には引渡)を求めることもできるように思えます。しかし、前述のとおり、判例上、この請求は、単に自身の共有持分に応じた共有物の利用権(民法249条1項)が侵害されているというだけでは当然には認められない、として否定されています。
そうすると、特定の共有者による共有物の独占的な利用によって共有物の利用権(民法249条1項)を侵害されている他の共有者は、当該共有物を独占的に利用している特定の共有者に対して、損害賠償請求はできるものの、共有物それ自体の明渡(ないし引渡)は求められないことになります。つまり、当該共有物を独占的に利用している特定の共有者が任意に共有物を他の共有者に対して渡さない限り、他の共有者は、依然として、共有物を利用できないまま、ということになります。
これでは、他の共有者は共有物を「共有」している意味はありません。そこで、上記の損害賠償請求とは別に、「共有」関係それ自体の「解消」と共有者間の「清算」を求めて、「共有物分割請求」を行っていくことになります。
2 「代償分割」における「共有物の評価」を巡るトラブル
共有物分割にあたり、共有物の取得を希望する共有者がいる場合には、前述のとおり、基本的に、まずは「代償分割」を検討することになります。「代償分割」においては「共有物をどのように評価するか」が最も重要な問題となります。「共有物の評価額」によって、共有物を取得する共有者から他の各共有者に支払われるべき「代償金」の金額が変動するからです。そして、この「共有物の評価」を巡っては、共有物の取得を希望する共有者と他の共有者との間で利害が真っ向から対立するので、この点を巡ってトラブルとなる場合が非常に多くあるのです。
そこで、共有物をどのように「評価」して「評価額」を算出すればよいのか、その方法について見ていきたいと思います。なお、実際にトラブルが発生するのは共有物が不動産=土地・建物である場合がほとんどであることは前述のとおりですので、ここでは土地・建物をどのように「評価」していくのかについて説明していきます。
まず、「土地」の評価方法ですが、主に次の4つがあります。
① 路線価に基づく評価
路線価は、国税庁が作成する路線価図に記載されている道路=公道に面した土地の1㎡あたりの価格です。これは、相続税等の課税の前提として土地の評価額を決める必要があることから、国税庁が算出した価格です。路線価は実勢価格の8割程度と実際の相場よりも低めに設定されていますので、「代償分割」の場面において共有土地の評価額を算出する場合には、この路線価を0.8で除して、実際の相場価格を算出した上、土地の面積を乗じて評価額を算出することになります。式で表すと、
「土地の路線価÷0.8×土地の面積=評価額」
ということになります。
路線価はインターネットを通じて無料で閲覧でき、比較的簡単に土地のおおよその評価額を計算できるので、土地の評価額を算出する際の目安として利用しやすいというメリットがあります。但し、対象となる土地が道路=公道に面していることを前提としているので、道路=公道に面していない土地については路線価の算出が困難であるというデメリットもあります。
なお、路線価は土地の1㎡あたりの価格を算出するためのものなので、建物には路線価は存在しません。
② 固定資産評価額に基づく評価について
土地については、その所有者に毎年固定資産税が課税されています。この固定資産税は、各土地について総務省が算出する固定資産評価額を基準にその課税額が決定されています。固定資産評価額は実勢価格の7割程度と実際の相場よりも低めに設定されていますので、「代償分割」の場面において共有土地の評価額を算出する場合には、この路線価を0.7で除して、評価額を算出することになります。式で表すと、
「土地の固定資産評価額÷0.7=評価額」
ということになります。固定資産評価額が記載された「固定資産評価証明書」は土地の所有者(共有者)であれば、役所で比較的簡単に入手できるので(但し、1通300円程度の手数料が掛かります)、路線価と同じく土地のおおよその評価額を知ることができ、土地の評価額を算出する際の目安として利用しやいというメリットがあります。
③ 不動産会社等による評価=査定に基づく評価
共有物としての土地の「評価」を巡るトラブルが実際に発生している場面では、上記の「路線価」に基づいて計算した評価額や「固定資産評価額」に基づいて計算した評価額が1つの目安となります。これらをそのまま「代償分割」における「評価額」として採用することも全くないわけではありませんが、いずれも課税の観点から算出されている金額であるため、当該土地の現状等を踏まえた的確な金額とは限りません。
そのため、現実に土地の「評価」を巡って紛争となっている場合には、「路線価」に基づいて計算した「評価額」や「固定資産評価額」に基づいて計算した「評価額」がそのまま土地の「評価額」として採用されることは少なく、ほとんどの場合、これらを参考としつつも、不動産会社等による評価=査定が用いられます。不動産会社による評価=査定は、専門家である不動産会社が、現地調査等を踏まえた上で、独自の知識や近隣土地の実際の販売事例等を基に土地の評価額=査定額を算出します。実際に土地の売却に携わっている専門家である不動産会社等が客観的な調査・検討を行って金額を算出するので、より相場に近い評価額が算出されやすい、というメリットがあります。
但し、一方で、不動産会社等は多数存在することから、不動産会社等ごとに査定額=評価額が異なることも多く、1つの不動産会社等による査定だけでは、「代償分割」における土地の「評価額」を算出する根拠としては弱い、というデメリットもあります。そのため、実務上は、複数の不動産会社等に査定を依頼し、各社が算出した査定価格の平均をとった金額を土地の「評価額」として主張することが一般的です。
また、不動産会社等は、基本的に査定を依頼した依頼者のために査定を行うので、誰が査定を依頼したのかによって算出される査定価格=評価額が異なる可能性が高いというデメリットもあります。例えば、共有土地を取得したい共有者は基本的に他の共有者に対して支払うべき「代償金」の金額をなるべく少なくしたい=共有土地の評価額を低く抑えたいと考えるので、このような共有者から査定の依頼を受けた不動産会社等は、その意向に基づき、実際よりも低めの査定価格を算出することがあります。また、逆に、「代償金」の支払を受けるべき共有者は基本的に自身が支払を受ける「代償金」の金額をなるべく増やしたいと考えるので、このような共有者から査定の依頼を受けた不動産会社等は、その意向に基づき、実際よりも高めの査定価格を算出することがあります。そのため、共有者間の利害が真っ向から対立し、お互いに自身に有利な査定結果を主張し合う査定合戦となり、結局、土地の「評価」を巡る紛争が解決されない、という場面が多々見受けられます。
④ 裁判所による鑑定に基づく評価
これは、土地の評価を巡る紛争が「協議」では解決せず、「共有物分割請求訴訟」に至ってしまった場合の話ですが、この訴訟の中でも土地の評価を巡る紛争が解決しない場合には、裁判所による鑑定がなされることになります。
裁判所による鑑定は、裁判所が、各共有者と利害関係がないことを確認した中立公正な立場の鑑定人(不動産鑑定士等)に共有土地の鑑定を依頼し、その評価額を算出させる手続です。裁判所からの依頼に基づく中立公正な立場の鑑定人による評価なので、各共有者による不動産会社等への依頼に基づく査定に比べて客観性が担保されており、紛争の解決に資するというメリットがあります。実際、この裁判所による鑑定が実施され、裁判所の選任した鑑定人により共有土地の評価額が算出された場合には、これがそのまま「代償分割」における「代償金額」を算出する前提となる共有土地の「評価額」として採用されることも多くあります。
つまり、この「裁判所による鑑定」は、土地の評価を巡る紛争を解決するためのいわば「最終手段」として機能しています。なお、裁判所の鑑定に要する費用(=主に裁判所が選任する鑑定士に支払う鑑定費用)については、基本的に、共有物分割請求訴訟における原告及び被告、つまり共有者全員が各自の共有持分に応じて負担することになるので、「路線価」に基づく計算、「固定資産評価額」に基づく計算、不動産会社等による査定(無料のことも多い)を用いる場合に比べて、費用を要するという点は注意しておく必要があります。
次に、建物の評価方法ですが、主に次の3つがあります。
① 固定資産評価額に基づく評価
土地と同様に、建物についてもその所有者に毎年固定資産税が課税されており、「固定資産評価額」が存在しています。そのため、これを基準に建物の評価額を算出することが可能です。但し、建物の固定資産評価額については、土地とは異なり、相場価格よりも低めに設定されているものではないため、「代償分割」に基づく共有建物の評価額を算出するにあたり、土地の場合のように0.7で除すという処理は行いません。
従って、建物の固定資産評価額自体が建物の評価額ということになります。
② 不動産会社等による評価=査定に基づく評価
建物についても、土地と同じく、不動産会社等による査定額を評価額とする方法が考えられます。しかし、土地の場合と同様に、建物についても、やはり最終的には査定合戦となってしまい、その評価額が確定しない、というリスクがあります。
③ 裁判所による鑑定に基づく評価
建物についても、上記①の固定資産評価額に基づく評価や上記②の不動産会社等の査定に基づく評価では決着が付かない場合には、土地の場合と同様、裁判所による鑑定が実施されることになります。
以上のとおり、土地及び建物の評価には複数の方法があることから、事案に応じて適切な方法を採っていくことになりますが、それでも共有者の間でその「評価」を巡る紛争が解決できない場合には、最終的に、「共有物分割請求訴訟」を提起し、その中で裁判所による鑑定の実施を求め、これにより算出された評価額を前提に、共有物の取得を希望する共有者から他の共有者それぞれに対して支払うべき「代償金額」を算出し、これに基づく「代償分割」を目指していくことになります。
3 分割方法を巡るトラブル
分割方法を巡るトラブルとは、「代償分割」という方法を採るか、「換価分割」という方法を採るか、というそもそもの分割方法の選択の段階でのトラブルを指します。例えば、共有者の大半が共有物の取得を希望せず、「換価分割」を希望しているにもかかわらず、一部の共有者が共有物の取得に固執し、売却に反対しているために、「換価分割」が実現できない場合です。本来、共有物の取得を希望していない共有者は、「代償分割」であっても「代償金」の支払を受けられるので、「代償金」の金額が適切に算出され、その支払を受けられるのであれば、「換価分割」に拘る理由はなく、一見すると、「分割方法」を巡るトラブルになることはないようにも見えます。
しかし、そもそも当該共有物の取得を希望している共有者に「代償金」を支払うだけの資力があるのか不明な場合など、「代償金」の支払に疑義がある場合には、仮に適切な「代償金」の金額を算出できたとしても、確実に「代償金」の支払を受けられるという保証がない以上、他の共有者としても、売却代金の中から確実に自身の共有持分に応じた金額の支払を受けられる「換価分割」を求めざるを得ないことになります。このような場合、共有物の取得を希望する共有者との間で、「分割方法」を巡るトラブルになります。
この場合、他の共有者は、共有物の取得を希望し売却に反対している共有者に対して、まずは「協議」により、「換価分割」に応じるよう説得を試みることになりますが、説得が成功しなかった場合には、「共有物分割請求訴訟」を提起した上で、最終的な分割方法について裁判所の判断を仰ぐことになります。
なお、「共有物分割請求訴訟」においては、共有物の取得を希望する共有者=「代償分割」を求める共有者が、自身に「代償金」を支払えるだけの資力があることを立証しなければならないとされています。そのため、当該共有者がこの点を立証できない場合には、裁判所が判決で「代償分割」を認めることはなく、競売による「換価分割」が命じられることになります。ちなみに、裁判所の「判決」では、共有物の「任意売却」を命じることはできないため、必ず「競売」による売却が命じられることになります。
また、本来、「換価分割」は、共有者のうちの1人でも反対していると行えませんが、「共有物分割請求訴訟」において、「競売」による「換価分割」を命じる旨の判決が言い渡され、この判決が確定した場合には、各共有者はこの判決に基づいてそれぞれ単独で共有物の「競売」を申し立てることができます。そして、同判決に基づく競売の申立てにより、競売が開始され、共有物が売却された場合には、その売却代金=競売代金が各共有者の共有持分に応じて裁判所により各共有者に支払われる(=配当される)ので、「換価分割」が実現されます。
4 まとめ
ここまで、共有物を巡るよくあるトラブルを見てきましたが、現実に最も多く、かつ最も重要なのが「代償分割」における共有物の「評価」を巡るトラブルです。
前述のとおり、共有物の「評価」によって、共有物の取得を希望する共有者から見れば他の共有者に支払わなければならない「代償金」の金額が、他の共有者から見れば自身が(共有物の取得を希望する共有者から)支払を受けられる代償金の金額が、変動することになるので、共有物の「評価」に関する対応(主張)を間違ってしまうと、思わぬ損失を被ってしまう可能性があります。
また、共有物の「評価」を行い、「代償金額」を確定したとしても、今度は当該共有物の取得を希望する共有者の資力の問題を検討しなければならず、その資力のいかんによっては、そもそもの分割方法を「換価分割」に変えなければならない可能性もあります。
このように、共有物の「評価」は、「代償分割」における「代償金額」の確定というだけでなく、当該共有物の取得を希望する共有者の資力との関係で、そもそも「代償分割」が可能なのか、という「分割方法」の選択にまで影響を及ぼすことになりますので、とりわけ慎重に検討する必要があります。
実際に共有物を巡るトラブルが発生してしまったら、当事務所に一度ご相談を
共有物を巡るトラブルが実際に発生してしまったら、まずは当事務所にご相談下さい。共有物を巡るトラブルを根本的に解決するには、「共有物分割請求」を行い、共有物を分割し、「共有」関係それ自体を解消する他ありません。各共有者はいつでも「共有物分割請求」を行えるので(民法256条1項)、「共有」関係が継続している限り、突然、他の共有者から「共有物分割請求」をされる可能性が常に付きまとうからです。そのため、現時点で、共有物の「分割」に関する紛争にまでは至っていない場合でも、共有物の「分割」を念頭に置いて対応していく必要があります。
しかし、前述のとおり、共有物の分割は、特に共有物の取得を希望する共有者がいる場合、「代償分割」における共有物の「評価」という形で共有者間の利害の対立をもたらすので、一筋縄ではいきません。
現在、共有物を利用している共有者がいるのか、共有物は今どのような状態なのか、共有物の評価額はいくらなのか、共有物の取得を希望している共有者の資力は十分なのか、共有物を(できるだけ高く)売却できる見込みがあるのか、など多岐に亘る事情を客観的に検討した上で、事案ごとにどのような分割方法が最も共有者間の「公平」に適うのかを的確に把握し、「代償分割」を目指していくのか、「換価分割」を目指していく(=共有物の取得を希望している共有者の説得を試みる)のか、という方針を決定する必要があります。
これには、共有物を巡る紛争に関する法的な知識はもちろん、特に共有物が不動産である場合には、不動産に関する知識・不動産市場の動向の把握など、多岐に亘る知識や経験が不可欠です。
しかし、このような多岐に亘る知識や経験を前提に、事案ごとに最も共有者間の「公平」に適う解決方法を模索しながら実際のトラブルに対応していくことは容易ではありません。
この点、当事務所は、これまで20年以上に亘り、不動産に関する問題を重点的に扱ってきました。その中で、2000件以上の不動産に関するトラブルのご相談を受け、うち500件以上を受任し、解決に導いてきました。共有物、特に共有不動産に関するトラブルも多数解決してきた実績があります。
このような長年の経験と実績から、当事務所では共有不動産を巡るトラブルを共有者間の「公平」に最も適う形で解決するための「生の知識」を身に着けてきました。また、当事務所では、信頼できる不動産鑑定士や不動産業者と密に連携し、不動産に関する最先端の情報を得るとともに、速やかに事案に応じた「相談」や「協力」を要請できる体制も整えております。
これら当事務所の強みから、共有物を巡るトラブル、特に共有不動産を巡るトラブルについて、必ずご相談者様のお役に立てると考えております。お1人で無理に対応しようとせず、まずはお気軽にご相談下さい。
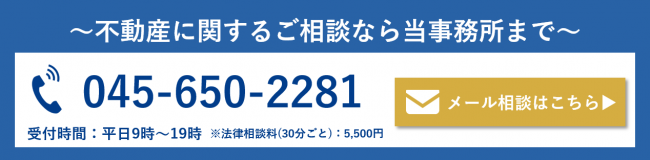
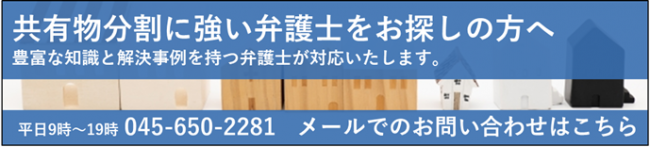
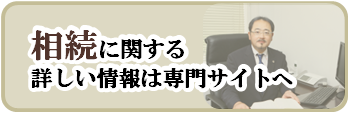
関連ページ
◆遺産共有とは
◆共有物分割請求の全面的価格賠償の要件
◆共有物分割請求とは
◆共有物分割請求の「濫用」
◆担保権が設定されている不動産の共有分割請求
◆夫婦間の共有不動産の共有物分割請求
◆共有物件の効果的な処分方法
◆建物の共有敷地のみの現金化
◆不動産が関与する相続について
当事務所の共有不動産に関する解決事例はこちら
複数の共有の賃貸不動産の持分を時価で買い取ってもらい、未分配だった賃料も回収した事例
不動産競売によって、業者の査定よりも高額で落札されて、その結果、より有利な条件で共有持分売却ができた事例
不動産競売によって、業者の査定よりも高額で落札されて、その結果、より有利な条件で共有持分売却ができた事例
持分買取業者の共有物分割請求訴訟に対して居住者による持分買取の和解を成立させた事例
持分を担保とした融資を受けた後に、共有不動産を共同売却した事例
高齢の父親が居住する共有の分譲マンションで父親に持分を買い取ってもらった事例
高齢の依頼者がリバースモーゲージで不動産担保ローンを組んで持分を買い取った事例
共有不動産を担保にした借入金で持分を時価で買い取ってもらった事例
遺産分割協議では、持分を現金で取得することを拒絶されたが、共有物分割請求をすることで持分を現金で取得できた事例
共有者の1名が売却に反対していた更地(共有)を共同売却した事例
共有の賃貸アパート1棟の競売(落札)による共同売却に成功した事例
投稿者プロフィール
- 弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県で約30年にわたり弁護士として活動しており、特に不動産分野に注力してきた。これまでの不動産関連のご相談は2,200件を超え、550件ものご依頼を受任。豊富な経験と知識で、常に依頼者にとって最良の結果を追求している。特に、不動産の共有関係や借地関係の解決には強い関心を持ち、複雑な問題も粘り強く解決に導く。
最新の投稿
- 2025.04.19建物明渡請求訴訟における占有移転禁止仮処分
- 2025.04.18所有者不明土地の解消 ~「特別代理人の選任」による解決方法~
- 2025.04.18所在不明等共有者の持分取得または第三者に譲渡するための手続【令和3年民法改正】について
- 2025.04.18不動産の使用貸借の終了に伴う立退きについて
- 共有物分割におけるトラブルを弁護士に相談するなら弁護士法人タウン&シティ法律事務所まで
- 共有者が居住している共有不動産の売却
- 共有持分を売却して現金化することは可能?トラブルなく売却するためのポイントとは?
- 共有不動産の名義貸とローンの解消
- 共有物分割請求による共有不動産・共同名義不動産の高額売却
- 他の共有者の持分を買い取った不動産業者との交渉
- 共有不動産の処分
- 共有持分を売却処分したい方へ
- Q.自身が所有している不動産が競売にかけられているが、どうにかしたいです。
- 共有者が出来る事、出来ない事
- 所在不明等共有者の持分取得または第三者に譲渡するための手続【令和3年民法改正】について
- 共有状態の解消方法