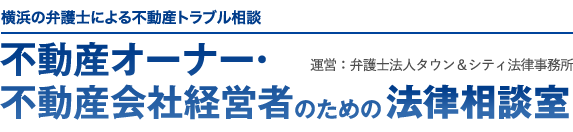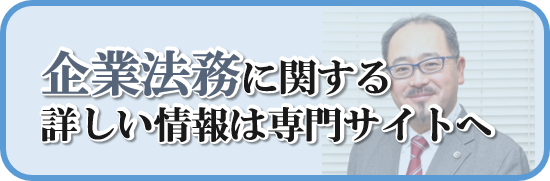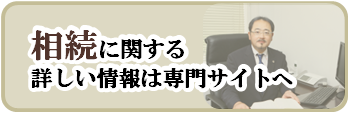借地の更新拒絶が認められる正当事由とは?立退料の設定金額について弁護士が解説
古い借地権は更新して半永久的に続くと言われます。しかし、期間満了の時に地主が正当事由に基づく異議を述べると借地契約は終了します。つまり、更新拒絶により終了します。どんな場合に正当事由が認められるのか、立退料はどうなるのか。弁護士が解説します。ご相談にも是非お越し下さい。
▼借地の立ち退きに関する記事はこちら▼
借家立ち退き・借地の整理(消費増税アップのチャンスを活用する)

1.借地の更新拒絶とは
借地の更新拒絶とは、地主が借地契約を期間満了で終了させたい場合に、
①借地権者からの更新の請求に対して異議を述べる
②契約期間満了後も借地の使用を続けている借地権者に対して異議を述べる
ことによって、借地契約を期間の満了で終了させることをいいます。そして、地主の異議に正当事由が認められると、借地契約は更新しないで終了します。正当事由は、地主の事情と借地権者の事情の比較によって決まります。
ここでは、どのような場合に、地主の更新拒絶が認められるのか、逆に認められないのか、立退料はどうなるのかなど、お話します。なお、ここでお話する「借地権」は、建物所有目的で、平成4年以前に設定された古い借地権を前提にします。また、借地権者に、地代の不払い、無断転貸、その他の契約違反がない場合を前提にします(借地権者に契約違反があれば期間満了を待つことなく契約を解除できます)。
2.更新拒絶(異議)の方法と時期
(1) 借地の期間満了と異議申立
ア.期間があっても更新します
借地権には、期間があります。建物の賃貸借契約には「期間の定めのない契約」があります。しかし、借地権は、当事者が決めなくても、更新の場合には堅固建物の所有目的の借地権で30年、非堅固建物の所有目的で20年というように、必ず期間があります。これは、契約の期間ですから、建前としては、契約期間が満了すると、契約は終了することになります。
しかし、借地権は、更新ができることになっています。
イ.更新請求と異議
建物の賃貸借の場合には、家主(建物の所有者)側が契約を終了させたい場合に、「更新拒絶の通知」をしなければならないことになっています。これに対して、借地の場合、法律上は、更新を希望する借地権者が、地主に対し「更新の請求」をすることになっています (*1) 。
この請求は、いつ、しなければならないのか法律には書いてありません。条文(旧借地法4条)を見ると、契約期間満了後でないとできないようにも読めますが、満了前にもできるというのが裁判所の考えです。ただし、期間満了よりもあまり前だと地主側も対応できないので、早くても数ヶ月くらい前だと思います(*2)。なお、期間満了後でもいいという裁判例があります。これに対して、地主側が「更新したくない」と思えば、「異議を述べる」ことができます。特別な手続はなく、また、「異議」という用語を使わなくても、「更新に反対」、「期間満了で契約終了」という地主の意思が借地権者に伝われば足ります。ただし、その異議に「正当事由」がないと、法定更新することになります。異議を述べて、それに正当事由があると更新しないで契約が終了するので、「異議を述べる」ことを「更新拒絶」と言います。 (*3) (*4)
(*1) 期間満了前に何らかの争いが起こり、借地権者が弁護士を依頼するような場合でないと、正式な形で「更新の請求」をすることはほとんどないと思います。
なお、「更新の請求」と具体的に書いたものだけでなく、期間満了後に、法定更新をする、という意思が地主側に伝われば「更新請求」になるとされています。ただし、更新の請求と認められると、地主が遅滞なく異議を述べないと法定更新するので、「地主が反対しても、法定更新する」という相当に強い意思が表れている必要があります。また、あくまでも「法定更新をする」という意思表示なので、更新料の支払い交渉をしたい(これは合意更新を求めることになります)と申し入れても、更新請求にはなりません。
(*2) 満期から5年も前の更新請求を有効と認めた判決もありますが(東京地裁昭和50年10月16日判決)、これは少々事実関係がややこしい事案で、しかも、地主の異議に正当事由を認めました。つまり、この更新請求を有効と認めても、地主が不利にならない事案でした。このような事情がなければ、早すぎる更新請求は地主が対応できないから一般的には有効とは認められません。
(*3) 地主側から、借地権者に対して、期間満了前に「更新拒絶」の通知をすることは、問題ありません。ただし、その後で借地権者から「更新の請求」が来た場合には、改めて、異議を述べた方が無難です。また、借地権者が期間満了後も土地の使用を続けている場合には、異議を述べなければなりません。
(*4) 地主側は、借地権者から更新請求が来なければ、満期まで黙って何もしなくて問題ありません。特に、借地上の建物が空き家になっている場合などは、満期前に「満期後には土地を明け渡せ」などと言うと、借地権者が無理やり子どもを居住させて建物の使用が必要だと主張するおそれがあります。ただし、借地権者が「合意更新について協議をしたい」などと言ってきた場合には、「更新の意思はない」という通知をした方がいいです。このような場合、その後の対応もあるので、弁護士に相談した上で通知した方がいいです。
これに対して、借地権者が借地を使用中なら、地主側から更新拒絶の要求をしても、特に問題はありません。ただし、満期前に更新拒絶を通知すると、正式な「更新の請求」をされることが予想されます。すぐに対応できるように弁護士に相談しておくべきです。
ウ.放置しても法定更新します
借地権者が、「更新請求」をしなかった場合、法定更新しないかと言うと、そうではありません。借地権者が、「更新請求」をしなかった場合でも、期間満了後もその土地を使っている場合(借地の上に借地権者の建物があれば土地を使っていることになります)には法定更新します。地主側が法定更新を拒否しようとしたら、「異議を述べる」必要があります。そして、その異議に正当事由があれば、借地契約は更新しないで、期間満了で終了したことになります。なお、期間満了前に借地権者が「更新の請求」をして、地主が異議を述べた場合でも、期間満了後も借地権者が借地の使用を続けている場合には、地主はもう一度、異議を述べる必要があります。しかし、この場合は一度、異議を述べているので、期間満了後の異議は、満了前の異議を撤回しないで続けていることが分かるようなもので足ります。例えば、満了後は地代の受領をしないとかが考えられます(お金は受け取るが、「地代ではなく使用損害金として受領する」と通知するなどでも足ります)。無論、「期間が満了したので建物を収去して土地を明け渡せ」と明確に通知するのが一番、問題がありません。
(2) 異議は遅滞なく
ア.異議は遅滞なく述べなければなりません
借地権者からの更新の請求があった場合と、借地権者が期間満了後も土地を使用している場合に、地主が、異議を述べないと法定更新することになりますが、「異議」は「遅滞なく」述べる必要があります。「遅滞なく」というのは、あまり遅いのはダメ、という意味です。
更新請求が弁護士から内容証明郵便で来た場合には、速やかに対応する必要があります。それでも、期間満了前の更新請求に対しては、地主にも、更新するかどうか検討する時間が必要なので、異議が2か月程度、後になっても遅滞があったとは言えません。更新請求というタイトルがなく、更新請求かどうかよく分からない場合には、もっと遅くなっても遅滞があったことにはなりません。これに対して、期間満了後に更新請求が来た場合や、期間満了後も借地権者が土地の使用を続けている場合には、すでに期間満了しているのですから、地主は更新を認めるかどうか決めているはずです。期間満了後の更新請求をされたり、期間が満了したら、速やかに異議を述べる必要があります。なお、事前に更新について協議をしていない場合には、借地権者も地主側も期間満了を忘れている場合があります。そのため、期間満了後の異議が2~3か月遅れても(その間に地代を受領していても)有効とされます。
ただし、契約の終了時期を忘れていれば、いつまでもいい、ということにはなりません(通常は契約書があり、少なくとも地主はそれを見れば終了時期が分かるからです)。
イ.契約書がなくて満了日が分からない場合
世の中には契約書がない上、契約当初の関係者も亡くなり、いつから契約が始まり、いつが契約期間の満了か分からない場合もあります。そのような場合に、期間満了後1年半後に異議を述べたとしても、遅滞なく異議を述べたことになるという判決があります(最高裁昭和39年10月16日判決)。ただし、この事案は、地主は期間満了直後に異議を述べたつもりだったのに、契約の終了時期がいつなのかが裁判で争われ、裁判所が認定した時期から数えると、異議を述べた時期が期間満了の1年半後だったというケースです。(*1) (*2)
(*1) 契約書がなくて、いつが契約の終了時期が分からない場合、通常は、借地上の建物が建てられた時期に期間を定めないで借地契約を結んだのだろう、と推測します。そして、最初は30年(期間を定めない場合の非堅固建物の最初の借地期間は30年になります)、その後、20年ごとに契約更新したと推測して、いつ契約期間が終了するのか、判断することになります。 このようにして、契約終了時期が容易に判断できる場合には、1年半も後に異議を述べるのは、遅すぎることになります。
(*2) 上の(*1)では、借地契約を結んだ時に建てられた建物が今も建っていることを前提にしました。しかし、借地契約の期間中に建物の建替え(再築)をした場合には、古い建物(取り壊した建物)の(滅失)登記すらも取得できない場合があります(取り壊し後長期間経っている場合です)。その場合、いつから借地契約が始まったのか、全く分かりません。しかし、建物の再築に対して、地主が異議を述べなかった場合、旧借地法7条で、古い建物の取り壊しから20年(非堅固建物の場合)の法定更新をすることになっています。古い話になると異議を述べたのかどうか分かりませんが、異議を述べたという証拠がなければ、異議を述べなかったのだろうと推測できます。そして、取り壊しの時から法定更新したと言えます。なお、取り壊しの時期も分からないのが普通ですが、再築建物ができる半年ほど前と考えていいと思います。その後、20年ごとに法定更新があったと考えられます。
3.異議の正当事由
(1) 法律の規定
廃止された旧借地法は、「正当事由」について、「 土地の所有者が自らその土地を使用する必要がある場合、その他の正当事由」と書いてあります。文字だけ読むと、地主側でその土地を使う必要があればいいんだと思われがちですが、そういうことではありません。平成4年に施行された新法(借地借家法)6条には、「 地主と借地権者それぞれが土地を必要とする事情のほか、借地に関する従来の経過や土地の利用状況、地主が土地の明渡しと引き換えに借地権者に対して財産上の給付をすると申し出た場合の金額を考慮して、正当の事由があると認められる場合」と書いてあります。
古い借地権の更新については、旧借地法が適用され、新法6条が直接適用されるわけではありません。しかし、新法6条は、新法が作られる前の旧法の正当事由の内容について、裁判所がした解釈をまとめたものとされています。つまり、旧法の「正当事由」の内容は、新法の6条の正当事由と同じ、ということになります。
(2) 正当事由の内容
旧法では、単に「土地の所有者(地主)が土地の使用を必要とする事情としか書いてないのですが、新法6条に書いてあるように、基本は、「地主と借地権者の双方が、それぞれ土地を必要とする事情」を比較することになります。比較と言っても、旧法の規定が前提ですから、まず、地主側で、「土地の使用を必要とする事情」がなければなりません。その上で、借地権者側の「土地の使用を続けなければならない事情」が、地主側の事情よりも強ければ、正当事由は認められないことになります。しかし、その場合でも、立退料の金額によっては、地主側に正当事由が認められることもある、ということになります。(*1)
昔から例に出される話ですが、地主が所有している唯一の土地がその借地で、地主自身は第三者が所有する借家に住んでいるような場合、地主には、自分所有の土地に家を建てて、その土地を自分で使用する必要があることになります。また、地主が事業のために店舗・事務所の建物を建てようとする場合にも、その土地を使う必要があることになります。
しかし、借地権者が、その借地上に、自宅建物を建てて住んでいる場合には、借地権者もその土地の使用を続ける必要があります。このように、双方、土地の使用の必要がある場合、どちらの方が土地の必要性が強いと言えるのか、また、立退料がどうなるのか、という問題が起こります。
(*1) 新法では、地主・借地権者が土地を必要とする事情「のほか」、従来の経緯や土地の利用状況、そして、地主側から借地権者側に提供する立退料の額で正当事由を決めると書いてあります。このため、基本はあくまでも、「地主・借地権者が土地を必要とする事情」で、その他の事情は、これを補うものと考えられています。例えば、いくら高額な立退料を積んだとしても(それで借地権者が納得すれば話し合いで解決しますが)、地主側に土地を必要とする事情が認められない場合には、正当事由は認められません。地主側にそれなりに土地を必要とする事情があり、それに立退料を加えると、契約終了にしてもいいだろうと判断できる場合でなければ、契約の終了(正当事由)は認められない、ということです。
旧法の正当事由の解釈でも、同じように解釈することになります。
(3) 地主が不利に扱われるわけではありません
ア.土地使用の具体性がなければ認められません
借地権者が保護されているので、正当事由は認められにくいと言われることがあります。しかし、これは、地主に土地使用の必要性が認められないことが多いからです。
地主が所有している土地が、その借地だけというケースはほとんどなく、少なくとも自宅の土地建物を持っている場合がほとんどです。そこで、「子どものための家を建てたい」などの主張をすることがあります。しかし、具体的な計画がないことがほとんどです。本当は、借地を返してもらって更地として第三者に売却したいとか、とりあえず、返してもらって、後で利用方法を考えると思われるケースがほとんどです。つまり、地主側に土地を使う必要性が認められない場合が多いのです。これに対して、借地権者側は、現実にそこに家を建てて居住したり、賃貸住宅として収入源にしていて、借地の使用を続ける必要性が高い場合がほとんどです。(*1)
このようなケースが多いので、借地権者は保護されているとか、旧法借地は半永久的に続くなどと言われることになります。しかし、これはあくまでも、そのようなケースが多いというだけの話です。裁判所が常に、地主に不利に判断する、ということではありません。実際に、地主側に土地を使用する必要性があれば、借地権者の必要性との比較になるとは言え、正当事由を認める場合があります。
(*1) 典型的な一例として、東京地裁昭和63年 5月30日判決は、「地主の必要性は、将来、次女夫婦に利用させたいというに尽きるが、次女夫婦には具体的な新築の計画及び資金の手当がなされているわけではない。これに対し、借地権者とその家族が本件建物を必要とする程度には大きなものがある。このような、賃貸人側の必要性と賃借人側の必要性とを対比するならば、賃貸人側の必要性が賃借人側のそれに優越しているとは認められない。」としました。
イ.正当事由が認められた事案
借地権者が借地上の建物を賃貸物件として使用していた事案ですが、「地主は、狭い借地にある店舗兼居宅に居住して鮮魚商を営んでいるが、毎日の生活にも差し支える生活を長期間余儀なくされている上、鮮魚の売上も年々落ちている。地主がこれからの生活のために本件土地に店舗兼共同住宅を建てて子供達と同居したいという事情がある」のに対し、借地権者は「別に居住用の不動産を複数所有していて、本件土地を居住用に使用する予定はなく、経済的にも恵まれた地位にある」、また、借地上の建物も相当古くなっているという事案について、立退料なしで正当事由を認めました(東京地裁平成3年6月20日判決)。ただし、建物買取請求権を認め、更地価格の約13% のお金を借地権者に払うことを求めました。
ウ.土地利用の有効性で正当事由を認めた例もあります
地主の使用の必要性は、地主が居住用建物を建てたり、事業の拠点となる建物を建てる場合に限られるわけではありません。土地の有効利用のために商業ビルを建てる場合でも正当事由が認められる場合があります。(*1)
ただし、そのためには借地権者が不必要に広い土地を使用して土地の有効利用がされていないとか、借地自体は狭い土地でも、地主がその隣地などを取得したり(他の借地権者に貸していて、返還の見通しがない土地ではダメです)、隣地の所有者と共同するなどして、隣地と合わせてビルを建てて土地の有効利用をしたい、という具体的な事情があれば、認められる可能性はあります。
しかし、これも借地権者の使用の必要性との比較や立退料の金額によります(東京地裁平成19年11月 7日判決はこのような場合に正当事由を認めました。また、東京地裁平成25年 3月14日も、地主側が他の土地と合わせて開発計画があることを理由に正当事由を認めました。
(*1) 東京地裁平成25年 3月14日判決は「地主側が土地の使用を必要とする事情には、借地の経済的な利用の必要も含まれると解するのが相当である」と言っています。その他、多くの裁判例が同じ考え方です。
(4) 正当事由の判断時と立退料の提示時期
地主側、借地権者側、それぞれの土地使用の必要性(正当事由の判断時)は、地主が異議を述べたときになければなりません(期間満了後、遅滞なく異議を述べる必要があるので、期間満了時としても大きな差はありません)(*1)。期間満了は堅固建物なら30年に1度、非堅固建物なら20年に1度だけです。借地権者は継続的に土地を使用していますが、地主は、20ないし30年に一度の「その時」に土地使用の必要性がなければなりません(近い将来、使用することが具体的な場合も、「その時」に含まれます)。これに対して、立退料は、異議を述べる時に借地権者に提供する必要はありません。裁判の最終段階で正式に提示(立退料を払うと言うこと。お金を見せる必要はありません)すれば足ります(最高裁平成 6年10月25日判決)。つまり、裁判官の顔色や言動に基づいて、金額を考えて提示すれば足ります。
(*1) 期間満了後の異議については、異議を述べた時を基準に正当事由を判断することになっています(最高裁平成 6年10月25日判決)。期間満了前に更新請求があって、それに対して期間満了前に異議を述べた場合、その異議に正当事由があったかどうかは、期間満了時の状況で判断されます(最高裁昭和49年9月20日判決、東京地裁平成25年12月25日判決)。期間満了前に更新請求があり、期間満了後に異議を述べた場合には異議を述べた時が基準になります。

4.借地権者の必要性
(1) 借地権者本人に必要でなければなりません
借地権が強く保護されているように言われていますが、地主が更新に異議を述べ、それなりに理由がある場合に更新するためには、借地権者本人が実際に借地を生活や営業の基盤として使用する必要がなければいけません。
借地権者の土地の使用の必要性とは
①借地権者自身が借地を使用している
②借地権者と実質的に同視できる者が、借地を使用している
場合でなければなりません(最高裁昭和58年 1月20日判決)。(*1)
②の「借地権者と実質的に同視できる者」とは、借地権者の子ども、借地権者が会社でその代表者などです(これは典型的なケースですが、あまり広い範囲ではありません)。また、土地の使用を必要とする事情とは
①借地上の建物が自宅で、そこに現実に居住している。または、借地権者と実質的に同視できる者がそこを借りて居住している。
②借地上の建物で事業をしている。または、借地権者と実質的に同視できる者がそこを借りて事業をしている。
③借地上に賃貸用物件を建てて、そこの賃料収入が借地権者の収入源になっている(どの程度の割合が必要かは、事案によります。例えば、生活費の1割でも、それがなくなれば本人にとっては大変な話ですが、地主の必要性や立退料との関係で評価されます)
ことが必要になります。(*2) (*3)
多くのケースでは、借地権者自身が自宅を建てて居住していたり、事業用に使用していたり、賃貸物件の賃料収入が生活費になっていると思います。ところが、中には、そうでないケースもあります。
(*1) これ以外に、最高裁判決は、借地権者以外の人が建物を借りて使用しているときに、その人の必要性を考慮できる場合があると言ってはいます。ただし、その要件は、「借地契約が当初から建物賃借人の存在を容認した」場合をあげています。しかし、平成4年よりも前に設定された古い借地権の場合、これが認められるような例はほとんどないと思います。
(*2) これらの事情がないと、「借地権者が土地の使用を必要としている事情」にはならない、という意味です。これらの事情があっても、それ以上に、地主の土地使用の必要性が高い場合には、地主の異議に正当事由が認められることになります。
(*3) ここに書いたのは、借地権者が個人の場合を前提にしています。借地権者が法人(会社等)の場合にも基本的には同じですが、会社の本社ビル、事業用施設、従業員の寮などの他、事業用の賃貸物件として建物を所有している場合も「借地権者が土地の使用をしている」場合に該当します。多数の事業用賃貸物件を所有している場合にその1つが借地上建物の場合も、「借地権者が使用している」に一応該当します。そして、賃料収入額や会社規模に応じて、地主側の使用の必要性と対比させることになります。なお、法人の場合にも「実質的に同旨できる者」でなければ、賃借人の事情は考慮されないので、例えば同族関係にある会社が賃借している場合でも、実質的に同旨できる場合に当たらないと考えられます(完全子会社でないと認められない可能性があります)。
(2) 借地権者に使用の必要性が認められないケース
ア.建物を使用していない場合
夫婦と子どもで居住していたが、子どもは結婚して独立。その後、夫が亡くなり、相続で妻が借地権者になり、しばらくは1人で居住していたが、転居したり施設に入り、借地上の建物は空き家になっている。また、相続で借地権を取得したものの、借地権者(相続人)は借地上の建物に居住していない、というのも、ありがちなケースです。つまり、借地上の建物が空き家になっている場合です。このような場合でも、いつかは使うかも知れない(子どもたちが家を建てる時に提供したいなど)と思って地代を払っている場合もあります。この状態でも、契約期間の途中なら問題ありません。しかし、満期になり、地主が更新拒絶した場合には、借地権者側に土地の使用を必要とする事情がないことになります。将来子どもに提供するかも知れない、というのでは具体性がありません。地主側に使用の必要性がある場合には、正当事由が認められる(土地の明け渡しが認められる)可能性があります。
イ.建物を借りている人の事情は考慮されません
昔は自宅として使っていたけれども、現在は他の場所に住んでいて、とりあえず、親戚や知人に安い賃料で建物を貸す場合もあります。しかし、住んでいるのが借地権者の子どもなどでない場合には借地権者と実質的に同視できる者が利用しているとは言えません。その親戚・知人にとって居住の拠点で、しかも、安い賃料なので他に転居できない、という事情があったとしても、そのような親戚・知人の事情は考慮されないことになっています(上記の最高裁判決)(*1)。
(*1) 借りている者の事情が考慮されない、というのは、借地権者と地主の関係では考慮されないという意味です。更新が認められず、借地権者が建物買取請求権を行使すると、地主に建物の所有権が移り、地主が建物の賃貸借契約を引き継ぎます。その結果、建物の借主は保護されます(「建物買取請求権」については、「建物買取請求権」をご覧ください)。しかし、建物の賃料額が極端に低い場合などは、賃貸借ではなくて、使用貸借とみなされることもあります。使用貸借の場合には、地主に引き継がれないので、借り主は退去するしかありません。
特に、建物の賃料額が地代相当額だった場合には、使用貸借とみなされる可能性があります。建物の使用貸借の場合、借り主が必要費を負担しなければなりませんが、地代は必要費とされています(東京地裁平成22年 2月 4日判決)。 このため、建物の賃料として支払っていても、使用貸借の必要費の支払いに過ぎないと評価される可能性があります。
ウ.子どもが住んでいても本人のようには重視されません
では、子どもが使っていれば大丈夫かと言うと、必ずしもそうとは言えません。借地権者が借地上の建物を子に貸している場合でも、使用の必要性が低いと評価されて、地主の明け渡しが認められた裁判例があります。借地とその上の建物(横浜市内)に居住していた親が亡くなり、2名が相続して借地権者になりましたが、2名は北海道と神戸に住んでいて、相続から4年間、空き家にしていました。そして、期間満了の直前になって、相続人の子が1人で住み始めたのですが、居住の理由は都内の予備校と大学に通うためだったという事案です。この事案について、裁判所は、土地の有効利用を図りたいとする地主の明け渡しを認めました。立退料の支払いが条件になっていますが、借地権価格の2割程度でした(東京地裁平成19年11月 7日判決。この判決については→5の(3)の(*1))。借地権者の子が居住していますが、この場合、子が借地権者本人と同視できると言っても、子の使用の必要性が考慮されるだけです。正当事由の判断時点では学生ですから、借地権者自身が生活の基盤として使用しているのと同じようには評価できず、使用の必要性が低いと評価されたと思います。
(3) 借地権を売る必要がある場合
借地を第三者に売ってお金にしたいので、更新後も契約を続ける必要がある、という場合があります(売る時や売った後で借地権が消滅するのでは誰も買いません)。(*1)
しかし、借地を売ってお金にしたい、というのは、ある意味では借地権者が「借地を使う必要がない」と言っていることになります。期間途中なら何の問題もありませんが、期間満了の時にはこの点は問題になります。これについての裁判例を紹介します。期間満了前に、借地権者が「更新請求」をして、地主が異議を述べたのですが、その直後に、借地権者が亡くなりました。そして、相続人(借地権者の地位を相続します)が、借地権とその上の建物を第三者に売りたいので、承諾してほしいと地主に申し入れたのですが、地主は拒否しました。そこで、相続人が借地権譲渡の借地非訟(裁判所に、地主の承諾に代わる許可を求める裁判)を求めました(これについては、「借地権の譲渡・転貸」の「地主が承諾しない場合(裁判所の許可)」をご覧ください。これに対し、地主は、「借地権を売るということは、借地権者自身が借地を使う必要がない、と言っていることになる。更新は認められない」と主張して、借地権者に対して、土地の明け渡しを求める裁判を起こしました。借地権者が借地を売ろうとしたのは、売ってお金にしないと相続税(そのほとんどはその借地の相続税です)が支払えないという事情がありました。上記の借地非訟は認められたのですが、借地非訟の裁判では、借地権があるかどうかの最終的な判断にはなりません。本裁判(土地の明渡を求める裁判)で、借地権が否定されて、土地の明け渡しが認められると、借地権を売ることはできなくなります。この事案について、最高裁は、「地主には正当事由がない」としました(最高裁平成 6年 6月 7日判決)。実は、この事案の地主は、借地の上の建物を借りて使用していたのですが、期間満了の前に、前の地主から土地(底地)を更地価格の2割程度の値段で買い受けたという事情がありました。新地主は、借地権を消滅させて借地上の建物を取り壊し、隣地の所有者と共同で高層ビルを建築することを計画していました。
つまり、借地権者は相続税の支払いのため借地権を売る必要がある、地主の方は安く土地を手に入れて、借地権を消滅させて高層ビルを建てようとしていた、という事案でした。このような事案全体を見た場合に「地主には正当事由がない」というのが、最高裁の判決の理由です。しかし、新地主も、更地価格の2割で土地を手に入れたというのですから、底地価格としては相当額だと思います。とは言え、借地権が消滅すると、更地価格の8割相当の権利が転がりこむことになります。ちょっと儲けすぎるように感じます。これに対して、借地権者は借地の相続で課税される相続税が支払えなくなって気の毒です。この対比が決め手のようです。地主が相続税相当の立退料を支払うと言っていたら、地主の明け渡しが認められたかも知れない、という解説もあります (立退料支払いの申し入れはありましたが、相続税額よりも少ない提示しかなかったようです) 。
借地権者の使用の必要性の中には、実際に土地を使う場合の他、「 借地権は売れるのでその価値を確保する必要性」もあり、それも借地権者側の必要性として考慮できる場合がある、と解説されています(それでも、基本的には、借地権者自身が土地を使う必要性があることが、借地権者側の事情になります)。最高裁の事例も、地主側に特殊な事情がありましたが、そこまで行かなくても、地主側に土地を使用する必要性が弱く、借地権者に「借地の相続で多額の相続税がかかり、その支払いのために借地権をお金に換える必要がある」場合には、地主の正当事由が否定されることになると思います。
ただし、最高裁の事案でも、立退料額によっては地主の更新拒絶が認められたのではないか、という解説があるので、立退料次第ではどちらに転ぶか分からないと言えます(借地権者も売ってお金を作りたいというのですから、立退料次第と言えます)。
(*1) ここで「借地を売る必要がある」というのは、満期の時点で売ってお金にする必要がある、という意味です。満期後もそのまま借地をもっていて、いつか誰かに借地権価格相当で借地権を売りたい、というのでは話になりません。なお、東京地裁令和元年 6月10日判決は、借地権者が築80年の老朽化した建物を相続で取得して所有していましたが、そこに住むことはなく、将来、売却しようと思っていると主張した事案です。裁判所は「借地権者には本件土地を使用する必要性がおよそ認められない」としましたが、地主側の必要性も弱い事案だったためか、借地権価格の20%の立退料で明渡を認めました。ただし、借地権価格の鑑定で、55%の市場性減額がされました(建物が老朽化していたことが考慮されたようです)。つまり、実質的には借地権価格の10%程度の立退料になったようです。
(4) 建物の再築・改築の必要がある場合
ア.建物の建替えの必要がある場合と異議の正当事由
借地上の建物が古くなったりして、建替えをする必要がある状態の時に、期間が満了することがあります。借地の契約に増改築禁止特約が着いているのが通常なので、建替えには、地主の承諾か、それに代わる裁判所の許可が必要になります(この点については「借地上建物の建替えと禁止特約」をご覧ください)。しかし、期間満了が迫っている場合には、裁判所は、建替えの許可を出さなかったり、許可を出したとしても、地主の更新拒絶に正当事由が認められるかどうかの正式な裁判(借地非訟でない裁判)の結論が優先します。そこで、期間満了の時に、建物の建替えの必要がある場合について、異議の正当事由にどういう影響があるのかお話します。
イ.建物がないと更新できません
建替えの必要があるかどうか以前の問題として、更新の時に建物があることが、借地権の更新の条件です。建物がない場合には、借地権者は「更新の請求」ができません。また、期間満了の時に建物がないと、借地権者が土地を使用していても(建物がなくて土地を使用しているというのはかなり特殊な場合ですが)、地主が異議を述べるのに正当事由がいりません。つまり、無条件で、借地権は消滅します。
この場合、「建物がない」理由に、制限はありません。自然に朽廃して建物でなくなった場合だけでなく、火事で全焼した場合、自分で取り壊した場合(再築しようとして取り壊した場合も含みます)など、いずれにしても、その時に建物がなければダメなのです。
ウ.建物があっても更新拒絶が認められる
雨風をしのげる壁があり、屋根もあれば、「建物」と認められます。 とりあえず、建物があればいいので、老朽化していずれは建て替えた方がいいような建物でも、地主の更新拒絶に「正当事由」が必要になります。しかし、「とりあえず、建物があれば 地主の正当事由が否定される」ということにはなりません。正当事由は、地主側と借地権者側の土地の使用の必要性の比較で判断されます。建物が使用できる状態かどうかは、土地の使用の必要性の判断と強く関連します。古くても人が住んでいる建物と、火事で内部が焼け、とりあえず「建物」としては建っているが、通常の使用ができないので使用していない、というのでは、借地権者の土地の使用の必要性に大きな違いがあります。 どちらの建物も、借地契約に増改築禁止特約があっても、裁判所の許可があれば建て替え(再築・改築)ができます。
しかし、火事で内部が焼けて使用していない建物の場合、期間満了の時点で使用していないことになります。無論、期間満了の直前に火事になった場合には、それ以前の使用が続いていると評価できます(火事という偶発的事情で一時的に利用できないだけと評価できます)。ところが、火事になって数年間も放置されて満期になった場合には、借地の使用の必要性がないと評価される可能性があります。長い期間建て替えをしないのは、具体的な使用計画がない、ということです。つまり、親が亡くなり空き家になった家と同じように評価されるということです。
エ.老朽化した建物の保護は低いと評価されます
老朽化して近い将来建て替えの必要のある建物は、現実に人が住んでいても、借地権者に不利に評価される可能性があります。借地権が保護されるのは、借地上の建物の保護の趣旨があります。借地権者がそれなりの資金をかけて建物を建てたのだから、それを保護しようということです。建て替えの必要性がない建物と比べると、近い将来、建て替える必要がある建物は保護の必要性が低いことになります。
つまり、通常よりも、地主の方に軍配があがる可能性が高くなります(あくまでも比較の問題です。地主に土地の使用の必要性がほとんどない場合には、地主の異議に正当事由が認められません)。
例えば、地主に土地の高度利用の必要性があり、借地権者の古くなった建物を残すよりも土地の利用の点で優れている場合には、立退料の額にもよりますが、更新拒絶に正当事由が認められることもあり得ます(更新拒絶を認めた、東京地裁平成3年6月20日判決は、借地上の建物が築60年経過していることを理由の一つにしています。また、東京地裁平成19年11月7日判決は、建物が築70年経過していることを理由の一つにしています)。

5.借地の立退料の金額
(1) 立退料と借地権価格
建物の賃貸借(借家)の場合、立退料は、基本的には、賃借人の移転に伴って発生する経済的損失が基礎になります(これについては、「建物賃借の法律相談・その2」の「立退料の相場と計算方法」をご覧下さい)。これに対して、借地権の場合には、地主の承諾がなくても裁判所の許可があれば借地権を第三者に売ることができます。その時の価格の基準が借地権価格です(借地権価格の評価方法については、「借地の相続」の中の「借地権価格の評価方法」をご覧ください)。そして、借地権が消滅すると借地権価格という財産権が消滅します。このため、借地権の場合は、移転に要する費用だけでなく、借地権価格を加えたものが、立退料の金額になりそうに思えます。移転に要する費用に、建物を再築する費用を含めるとすると、立退料の金額は土地の更地価格よりも高くなるかも知れません。
しかし、判決例を見ると、借地の立退料の金額は、借地権価格よりも低い金額(半分にも充たないこともあります)になることが多いです。
(2) 立退料が借地権価格よりも低い理由
ア.土地を使う必要が低ければ立退料は低くなり、必要が高ければ立退が否定されます
立退料額が低くなる一番の理由は、借地権の更新拒絶に正当事由が認められた判決が、多くの場合、借地権者の側に、土地を使用する必要性が低かったという事情があります。逆に、借地権者に土地を使う必要性が高い場合は、更新拒絶が認められないことが多いです。建物の更新拒絶の場合には、賃借人に使用の必要性が高い場合でも、立退料額で調整して立ち退きを認める例が多いです 。
しかし、建物の賃借人と違って、借地権者は、代わりになる移転先を見つけるのが困難です。また、地主側が高額な借地権価格相当の立退料の支払いに応じないことも多いと思われます。つまり、借地権者に使用の必要性が高い場合には、地主の請求が認められないという結果になります。とは言え、判決の中には、借地権価格相当の立退料と引き換えに借地の返還を認めた判決もあります。借地権者にはその借地以外に不動産がなく、借地上に自宅建物を所有して居住していました。そして、地主側にもある程度の正当事由があった上、借地権価格相当の立退料の支払いをする意思を表明していました(それでも借地権者が土地の返還の和解を拒否したので判決になりました)(*1) 。
借地権価格相当の立退料を認めた判決は、この判決同様、借地権者が借地上に自宅建物を建てて生活の本拠にしていて、他に所有不動産がない、というケースです。ただし、地主側にもある程度の正当事由がないと、立退料を払っても請求は認められません。(*2)
(*1) 東京地裁平成25年3月14日判決は、地主側の再開発計画に正当事由を認め、借地権者が居住している借地上の建物の収去と土地明渡を認めた事例です。借地権者は他に所有不動産がないので、借地権者側の使用の必要性が高かった事案です。裁判所は、借地権価格を5500万円とし、立退料額を5000万円としました。判決はその理由について、「本件建物の価格については,建物買取請求権の行使によって,その補償が図られるべきであり,上記立退料の金額には含めていない。」と言っています。この事案、最終的に建物買取請求の金額がどうなったのかは分かりません。しかし、判決後に買取請求権の行使をしたはずです。その結果、前の判決のいっていた500万円が建物買取代金額になり、立退料と合わせると、総額5500万円になったのではないかと思います(500万円よりも高くなる可能性もないとは言えませんが、裁判をやっても前の判決が尊重される傾向があります)。しかし、借地権者は居住用建物を失うので、代わりの居住先を確保しなければなりません。借地上建物と同じ広さの居住先を確保するのに十分な金額かと言うと、何とも言えないと思います。
(*2) 少々、珍しいケースを紹介します。東京地裁令和元年10月30日判決は、借地権者が「建物で一人暮らしをしており,建物内で炊事をすることや風呂を利用することはほとんど無く,休日も外出することが多い旨供述している。また、建物は築年数が古く,損傷が多いのに、修繕等をしていない。また、借地権者は公務員として安定した収入があり,平成20年に世田谷区豪徳寺の土地建物を購入して全く居住しなかったにもかかわらず,平成28年まで住宅ローンを支払い続けたという。このため、他の建物を賃借するなどして,転居することが経済的に困難であるとはいえない。建物と勤務先は離れており,建物に居住することが通勤の便宜から必要であるとはいえない」などの事実をあげています。とは言え、判決では借地権価格相当の立退料を認めました。これは借地上の建物を生活の基盤として他に不動産のない借地権者の立退料と同じです。
判決によると、上記の豪徳寺の土地建物に住民登録をしていたとのことですから、ここに住んでいなかったとは思えません。それでも、平成28年に売却して借地上建物に住民登録を移したとのことです。借地の満期が平成30年3月ですが、その時点で、借地上建物以外に居住していたという証拠はありません。ですから、「おかしいと思うけど、ここに住んでいないとは断定できない」、と言うのが判決の趣旨のようです。この事案では借地権者が豪徳寺の土地建物を売却した理由が不明ですが(ローンの支払いができなくなって古い借地上建物での生活を始めた、というわけではなさそうです)、借地上建物に住んでいないとは断定できないとしても、その使用の必要性が高いとも言えないので、立退料は借地権価格の半分程度が妥当だったように思います。
イ.借地権価格の支払い義務はありません
理由の2つ目は、古くからの借地権は、地主に借地権価格に相当する権利金などを払って成立したものではない、ということがあります。権利金なしで土地を借りて、いつの間にか、借地権価格相当の権利を持っていることになっているのがほとんどです。「借地権価格に相当する権利金の授受がないので、借地権価格を立退料の基礎にはできない」と明言している判決もあります(東京地裁平成31年 1月15日判決)(*3) 。
つまり、借地権価格は、敷金などと違って、土地を返す時に当然に借地権者に戻ってくるものではない、ということです。立退料は、地主、借地権者双方の土地使用の必要性の差を埋め合わせて調整するもので、借地権価格そのものではありません(上記判決)。とは言え、何も目処がないと決めようがないので、借地権価格を、ある程度参考にしているというのが、この判決を含めた裁判例の傾向と言えます。
(*3)借地権の譲渡許可を求める借地非訟で、地主が介入権(自分に借地権を売るように求める権利)を行使する時には、その代金額は、借地権価格が基礎になります。そのことと、一見、矛盾するようにも思えます。しかし、借地権価格は借地権を第三者に売るときの代金のメドです。そして、介入権は、第三者の代わりに地主に借地権を買い取る権利を認めたものです。そのため、介入権の代金額は、借地権価格を基礎に算定されます。しかし、介入権を行使するかどうかは地主が自由に決めることなので、地主に有利な金額にする必要はありません。これに対し、20年ないし30年の一発勝負になる期間満了時の立退料は、それとは違う発想で決めるということです(譲渡許可の借地非訟の介入権については、「借地の譲渡・転貸」の「地主の介入権」をご覧ください)。
ウ.建物買取請求権が行使されなければ買取価格を控除します
理由の3つめは、借地権が更新しないで契約終了が認められると、借地権者には、建物買取請求権が認められるので、この点を考慮した、ということもあります。
建物買取請求権は、借地権価格の2~3割程度が相場と言われています(それだけの金額が地主から借地権者に支払われることになります)が、建物買取請求権は、地主側からの土地明渡の裁判が借地権者敗訴で終わった後でも行使できるとされています。つまり、契約終了を認めるかどうかの裁判(土地明渡の裁判)の時点で、建物買取請求権が行使されていない場合には、裁判所は、建物買取請求権を考慮しないで立退料を決めることになります。この場合、裁判後に建物買取請求権を行使することが予想されるので、これを加えたものが最終的に借地権者に支払われる金額になります。そこで、将来、建物買取請求代金が行使されることを予想して(その分を引いて)立退料を決めると考えられます(「建物買取請求権」については「建物買取請求権」をご覧下さい)。(*4)
(*4) 上記(*1)の東京地裁平25年3月14日判決は、「本件建物の価格については,建物買取請求権の行使によって,その補償が図られるべきであり,上記立退料の金額には含めていない。」と明確に言っています。また、東京地裁令和 2年 9月 8日判決も、「建物買取請求権の行使によって補填されるべき本件建物の価格を控除した金額」を立退料額として、この立退料の支払いと引換に借地上建物からの退去(建物の取り壊しではなくて)と土地明け渡しを認めています。これも判決後に建物買取請求権が行使され、立退料とは別に建物代金が支払われることを前提として立退料を決めたと言っています。
(3) 和解と立退料
一応、考えられる理由を書きましたが、それでも金額に幅があります。どういう基準で金額が決まるのかよく分かりません。立退料額を借地権価格よりも減額する場合は、かなり大雑把な理由でばっさり切っている印象です(細かな理由を書いてあるものもありますが、他の判決と統一した基準に基づくものではありません)。(*1)
そもそも、借地の更新が認められないで、契約終了を認める判決(何らかの形で公表されているものですが)というものの数が少ないです。裁判になっても、和解で終わるものが相当数あると思います。借地権者が土地を明け渡すことを認める和解の場合、地主が借地権を買い取る(借地権価格相当の立退料を払うのと同じことになります)という内容の和解で終わる場合も相当数あるのではないかと思います(公表されていないので正確には分かりません)。言えることは、判決では、当然には、借地権価格相当の立退料を認めることはなく、それよりも随分低い場合が多いということです。また、借地権者にその土地の使用の必要性が高い場合でも(借地上に自宅があり、他に所有する土地がない場合が典型になります)、立退料の上限を、借地権価格にしているように思えます(移転費用などはその中に含まれるという想定です。移転費用の算定がしにくいという事情や、地主側がそれ以上の立退料に応じないという事情もあると思います)。地主が立退料を出し渋っている場合は仕方ありませんが、借地権者としては、地主側が有利だと思われる場合には、できるだけ借地権価格相当で借地権を地主に買い取らせる和解(そうでなければ底地の買取)を考えるのがいいように思います。しかし、地主の正当事由が認められるケースも少ないので、あくまでも事案によりけりです。
(*1) 東京地裁平成19年11月7日判決は、建物の鑑定をしています。鑑定によると、建物は築70年で、経年相当の老朽化が見られるが、未だ住居としての機能を果たしているとのことでした。しかし、判決は、「老朽化も進んでいることから,建て替える方が社会的経済的に見て合理的と考えられる」とした上で、その他の事情も考慮して(長く居住していた借地権者が亡くなり、相続した新借地権者は4年間放置した後、満期の直前に受験生、大学生の子を居住させたという事案です)、借地権価格の約20%の立退料で明渡を認めました。この件では建物の鑑定をしていますが、築年数相当の老朽化という以上の意味はなく、これも1つの要素として他の事情と総合して立退料を決めたことになります。なお、総合する場合の計算式のようなものはありません。

投稿者プロフィール
- 弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県で約30年にわたり弁護士として活動しており、特に不動産分野に注力してきた。これまでの不動産関連のご相談は2,200件を超え、550件ものご依頼を受任。豊富な経験と知識で、常に依頼者にとって最良の結果を追求している。特に、不動産の共有関係や借地関係の解決には強い関心を持ち、複雑な問題も粘り強く解決に導く。
最新の投稿
- 2025.08.06不動産トラブルのセカンドオピニオンを検討中の方へ
- 2025.04.18不動産の使用貸借の終了に伴う立退きについて
- 2025.04.15定期借家契約の活用術
- 2025.04.15Q.自身が所有している不動産が競売にかけられているが、どうにかしたいです。
- 借地の更新の際に支払う金銭トラブル
- 借地上の建物の建替えでよくあるトラブルとは?増改築禁止特約を弁護士が解説
- 借地権の譲渡におけるトラブルとは?地主の承諾が得られない時の対応方法を解説
- 借地への抵当権設定においてよくあるトラブルとは?
- 借地の共有持分の譲渡におけるトラブルとは?
- 借地権の遺産分割の適切な方法とは?
- 借地の更新拒絶が認められる正当事由とは?立退料の設定金額について弁護士が解説
- 借地からの立ち退きに関わる問題を横浜の弁護士が解説
- 借地人が立退きを求められた時、弁護士に相談すべき理由とは?
- Q&A | 「借地権の買取などとんでもない。借地契約を終了させるならすぐに更地にして返してもらいたい!」強硬な地主のために窮地に陥った借地人…借地人側としては何か対抗する手段はないのでしょうか?」
- Q&A | 借地人による「借地権の譲渡」を承諾することの対価として「承諾料」520万円を受け取った地主…譲渡契約が白紙になったことで「支払った承諾料を返して欲しい」と返還を求められましたが、地主は返金する必要があるのでしょうか?