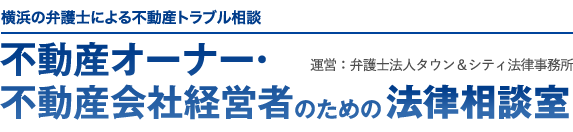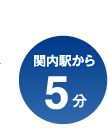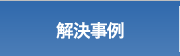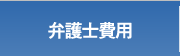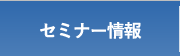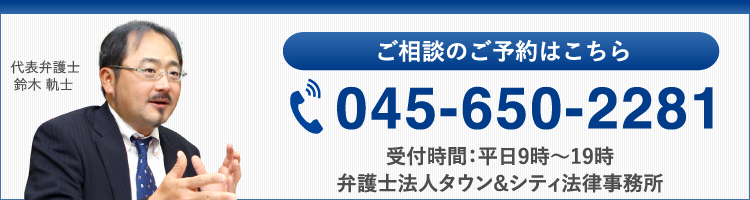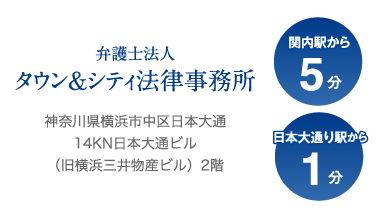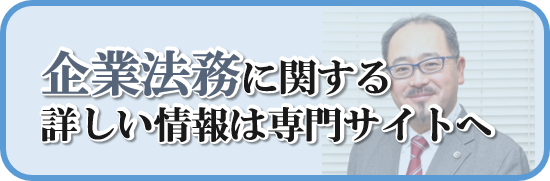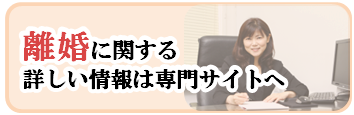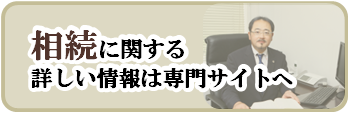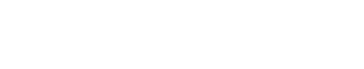定期借家契約の活用術
Contents
はじめに
建物の賃借人は、借地借家法によって手厚く保護されています。
このため、賃貸人は、一度借地借家法の適用のある「普通」借家契約を締結してしまうと、仮に自身の都合で契約を終了させたいと思っても、簡単に賃借人に対して契約の終了及び建物明渡しを求めることができません。
たとえ契約書に、契約期間を定めたとしても、契約期間満了時期の6か月前には更新拒絶通知を出さなければなりません。かつ、通知が効力を認められるためには、法律上の「正当事由」が必ずなければなりません。上記の各要件を充たさなければ、自動的に更新されます。「正当事由」があると裁判所に認めてもらうことのは、容易ではなく、正当事由が十分でないのに契約の終了を認めてもらうために、一定の「立退料」を支払わなければならない場合もあります。
最近の首都圏内での立退き請求事案では、昨今の不動産価格の高騰により、立退料額が比較的高額化しています。契約の終了を求める賃貸人にとっては頭が痛いところです。
賃貸人側としても、「この時期には確実に賃貸借契約を終了させて、賃借人に出て行ってもらいたい」
「自分が使わない一定期間だけに限って、建物を賃貸に出したい」という事情がある場合もあります。
このような事情があるときに、賃貸人の希望を実現する手段として利用されるのが、「定期借家契約」です。
定期借家契約について
定期借家契約とは、借地借家法38条に定められた建物賃貸借の一類型です。
更新拒絶通知の有無も、正当事由があるかも、いずれも問題とせず、契約書に定められた契約期間が満了すれば、確定的に契約が終了するという、建物賃貸借契約です。
定期借家契約の場合でも、通常の建物賃貸借契約(普通借家契約)よりも、契約期間内の中途解約はむしろ厳しく制限されるので、「自分が必要となった場合にすぐに契約を終了させたい」というオーナーの希望は実現できません。 しかし、オーナー自らが建物を必要とする(将来の)時期が、あらかじめ確実に決まっているようなケースでは、普通借家契約よりも使い勝手のよい契約類型といえます。
定期借家契約は、賃貸人にとって利用し易い契約か?
定期借家契約は、上記のとおり賃貸人側にとって利用し易い反面、実は
① 契約成立時点の注意
② 普通借家契約から定期借家契約への切り替えの可否
③ 契約終了時点(ⅰ)→再契約をする場合
④ 契約終了時点(ⅱ)→再契約もしない場合
それぞれの段階で、賃貸人(オーナー)側は十分に注意して、対応しなければならないポイントがあります。上記を実は、不動産業者も、弁護士すらも、完全に正確に理解していない場合があります。
そして、もし各ポイントで適切な対応をしていないと、せっかく定期借家契約をした意味がなくなってしまったり、普通借家契約を締結した場合よりも不利になったりする可能性すらあります。
それぞれの時点で賃貸人が注意すべき事柄をきちんと理解し、正しい理解に基づいて契約を締結したり、締結後の対応を採っていく必要があります。
それぞれの時点でのポイント
契約成立時点の注意
(ア)4つの形式要件
(普通借家契約ではなく)「定期借家契約」が成立した、と認められるためには、契約書に「定期借家契約」「更新しない」と記載するだけでは不十分です。法律上は、
(a)契約期間の定め
(b)更新しないという条項
(c)書面で契約を締結すること
(d)更新がないことの書面による事前説明
の4点が必要です。
(イ)契約書の「更新しないという条項」に注意
ウがあるので「口頭」での定期借家契約は成立しませんが、普通は、(a)(b)の条項を記載した契約書を作成するでしょうから(a)~(c)の要件が問題となることはありません。
(ウ)「書面交付説明」の要件に注意
問題になりがちなのは、(d)の要件です。締結する契約書とは別に、賃貸人は賃借人に、「この建物賃貸借契約は更新がなく、期間の満了によって終了する契約です」という内容を記載した書面を、あらかじめ渡して、説明をしなければならないのです。
あとで「そんな書面もらってないし、説明も受けてない」と言われないために、賃貸人としては、契約書とは別に(契約書案文では効力が認められない、とされた例があります)、説明書面を用意し、「この書面を受領して、説明を受けたことを確認します」との文言を入れて、賃借人から署名・押印をもらっておくことも併せて重要となります。
上記のとおり、定期借家契約は、特殊な契約です。この契約を締結したい場合は、自身でやらず、専門家である弁護士等に任せた方が安心です。
普通借家契約から定期借家契約への切り替えの可否
定期借家契約という類型を知ったら、「今貸している建物も、定期借家契約に切り替えたい」と思う賃貸人(オーナー)もいるかもしれません。実は、これは非常に難しい要望です。
(ア)平成12年3月1日より前から契約している「居住用建物」の切り替えは認められない
借地借家法中、定期借家契約の条項が施行されたのは平成12年3月1日です。この制度が施行される際、制度施行日より前から存在する「居住用建物」の普通借家契約については、同一の当事者間で、同一の建物について定期借家契約を締結することは、当分の間、できないとされたのです。既に制度施行から25年以上経ちましたが、現在もなお、上記制限が存在している状況です。
このため、施行日以前から存在する居住用の普通借家契約については、定期借家契約に切り替える内容の合意をしたとしても、無効とされます。
なお、平成12年3月1日以降に成立した普通借家契約については、きちんと合意さえすれば、定期借家契約への切り替えは可能です。
また、事務所、店舗等の事業用賃貸借契約の場合にも、成立した時期が昔のものであっても、切り替えは可能です。
(イ)更新がない点で不利であることを説明して認識させた上で契約する必要
法律上は切り替えが可能な場合であっても、普通借家契約から定期借家契約への切り替えは、通常は不利な内容への切り替えとなります。裁判例においてですが、上記の切り替えが有効であるかどうかについては、
「既に存在している契約を更新せずに、終了させること」
「新しい契約は契約期間満了時に更新がないという点でより不利な内容であること」
を、きちんと賃借人が理解していることが必要だとも指摘されています。したがって、単に、所定の手続をとって作成された契約書を保管しておくだけでなく、契約の切り替えにあたり、事前にやり取りした交渉過程のお手紙・やり取りの内容なども、重要な意味(証拠価値)が出てくる可能性があるため、これらの経緯について書面もきちんと保管しておいた方がよいものと思われます。
契約終了時点(ⅰ)→再契約をする場合
(ア)再契約と更新は全く違います
定期借家契約を締結した場合、契約期間内の解約は、普通借家契約よりもむしろ厳しく制限されます。このため、定期借家契約の契約期間は、2年など比較的短期に設定しておき、再契約条項を入れておくことで、契約期間満了時に同じ内容で再契約をし、事実上更新と同様に扱おうとする場合もあります。
しかし実は、更新と再契約とは全く違います。普通借家契約よりも面倒な手続なのです。
(イ)再契約の場合もまた、契約書作成、書面交付説明が必要
再契約は、法律上は従前の賃貸借契約とは全く別のものです。再契約後の賃貸借も、定期建物賃貸借契約とするならば、再契約をする段階で、また、当初の契約時と同様に、契約書を新たに作成した上で、書面交付による説明が必要となります。
説明が必要ということは、単に契約書の郵送等では足らず、必ず対面や最低限電話やWeb等リモート通信等を利用してで説明することも基本的には必要となります。
(ウ)敷金、保証金、保証人は再契約した契約には引き継がれない
更新の場合には、保証人も敷金¥保証金も引き継がれます。しかし、再契約の場合、新たな契約書に再度保証人にも署名・押印してもらう必要があります。
但し、一度お金を返還しまた預け入れる、という金銭移動の手続をわざわざ執るのは面倒なことから、再契約の際の契約書に、占有開始した当初の時点で締結された契約に基づいて預託された敷金・保証金は、返還せずに再契約による敷金・保証金として引き継ぐという内容の条項を入れて、実務上は便宜を図っています。
(エ)原状回復条項の「原状」の確認
再契約の契約書にも、契約終了時の明渡し・原状回復条項は設けます。
しかし、賃貸人としては、当然、明渡時の原状回復は、最初に物件を貸渡したときの状態にしてもらうものと考えているでしょう。
しかし、再契約の際の(再)契約書に記載しないのであれば、「原状」とは、再契約時点の状態ということになります。
よって、原状回復の「原状」は、再契約時点の「原状」ではなく、賃借人が建物の占有を開始した最初の時点の状態であることを確認する特約条項(原状時点の遡及条項)を入れておく必要があります。
契約終了時点(ⅱ)→再契約もしない場合
(ア)賃貸人は何もしなくていいわけではありません
定期借家契約であるからといって、賃貸人が何もせずに、契約期間満了と同時に契約が当然に終了する、というわけではありません。法律上、契約終了時期が近くなった時点で、賃貸人が執らなければならない手続があります。
また、契約期間が満了したのに、賃借人が建物の占有を続けている場合、これを放置してしまうと、「黙示の普通借家契約が締結された」と賃借人側から主張されて認められてしまうこともあります。これでは、折角「定期借家契約」にした意味がなくなってしまいます。
(イ)終了通知
定期借家契約の契約期間が1年以上の場合、期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃貸人は賃借人に対して、「期間満了により契約が終了する」という内容の通知(終了通知)を送付しなければなりません。
終了通知は、特に書面で行う必要はないのですが、契約書に「書面で通知する」と書いてある場合には、必ず書面で通知しなければならず、口頭での通知は、要件を満たさないものとされます。 後日での証明を容易にするためにも内容証明郵便にて通知することをお勧めします。
ただし、定められた期間内に終了通知をするのを失念してしまっても、契約期間満了と当時に、賃貸借契約は確定的に終了します(=通知人は契約終了自体の要件ではないということです)。契約終了に基づく具体的な請求(明渡、遅滞による約定損害金の請求)が、終了通知から6か月経過した後でないと請求できない、ということです。
契約期間満了時期と同時に、明渡しや明渡し遅滞による遅延損害金の請求をするのであれば、定められた期間内に終了通知を行う必要があります。この期間内の終了通知ができなかった場合であっても、(通知時期が契約期間内か契約期間後であるかに関わらず、)通知を行ってから6か月経過すれば、賃借人に対し、契約終了による明渡請求や、約定遅延損害金の請求もできるようになります。
(ウ)契約期間満了後も賃借人が使用継続しているのに、これを放置して黙認している場合
定期借家契約の契約期間が終了した後も、賃借人がそのまま使用を継続し、従前と同じように賃料が支払われているとしても、基本的に、それだけで「更新された」「再契約した」「普通借家契約に切り替わった」と扱われるわけではありません。
この点、民法619条1項には、「期間満了後に賃借人が使用継続する場合に、賃貸人がこれを知りながら異議を述べない場合」の黙示の更新の定めがあります。しかし、定期借家契約については、「更新はない」とした制度趣旨に鑑み、この民法規定の適用はないとした裁判例があります。
しかし、契約終了後の使用継続をいつまでも放置したり、建物賃貸借契約の継続について賃借人に期待させるようなことをすると、状況は変わってきます。
先ほどの「終了通知」の考え方からすると、契約期間満了後、終了通知を行えばその6か月後には明け渡しが求められる、ということになります。しかしそれをいつまでも許してしまうと、「定期借家契約」を一度締結しさえすれば、契約期間満了後は、賃貸人が、いつでも自由に、6か月で契約終了を主張できるという、専ら賃貸人側にとってのみ都合がよい契約類型を作り出すことを認めてしまうことになりかねません。このような法の潜脱のような事態は基本的には許されません。
つまり、裁判例の中には、「定期借家契約が終了したあとも、賃借人が使用を継続し、賃貸人も異議なく賃料を受領し続けている場合には、新たな普通借家契約が締結されたというべきだ」と判断したものもあります。
そして、新たに締結されたと判断されるのは、定期借家契約ではなくあくまで普通借家契約です。黙示的な契約ですから当然、契約期間の定めもないですし、更新料の請求などもできません。このように認定されてしまった契約を終了させることは、通常は、相当ハードルが高くなります。なぜなら、借地借家法に基づき正当事由となるからです。仮に、このような判断をされてしまうようだと、折角、最初に定期借家契約を締結した意味は全くなくなり、(期限の定めのない(借家契約となってしまい「更新料」ももらえなくなってしまうことから)むしろ賃貸人により不利になってしまいます。
(エ)普通借家契約が締結されたといわれないために
裁判例が、「黙示の普通借家契約が締結された」と判断するような事例は、放置・黙認以外にも何らかの事情があるケースがほとんどですが、少なくとも1年以上も何もしないということは避けるべきです。
したがって、賃貸人としては、
①適宜の時期に書面で終了通知を行う
②契約期間満了後、すみやかに明渡しを求め、かつその請求は、内容証明郵便などでその証拠が残る形で行う
③賃借人が応じない場合には、何度も定期的に立ち退きを求める
④少なくとも1年以上放置はしない
⑤いつまでも明け渡しが実現しない場合は、調停・訴訟など法的手続をとる
⑥新たな定期借家契約締結の打診など、将来の使用継続を期待するような行動は決してしない
など、賃借人側が「いつまでもここにいられる」と期待しないように、様々な対応を積極的にとっていく必要があります。
⑤の段階ではもちろんですが、弁護士等に相談することはもちろんなのですが、そこに至るまでに賃貸人自身が行っていたこと等が不利に判断される材料となることもあります。必ずしも揉めそうな場合は、早い時期に不動産関係に明るい弁護士等専門家へ相談するなどして、対策を採っていく必要があるものと思われます。
※この記事は公開時点の法律をもとに執筆しています。
投稿者プロフィール
- 弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県で約30年にわたり弁護士として活動しており、特に不動産分野に注力してきた。これまでの不動産関連のご相談は2,200件を超え、550件ものご依頼を受任。豊富な経験と知識で、常に依頼者にとって最良の結果を追求している。特に、不動産の共有関係や借地関係の解決には強い関心を持ち、複雑な問題も粘り強く解決に導く。
最新の投稿
- 2025.08.06不動産トラブルのセカンドオピニオンを検討中の方へ
- 2025.04.18不動産の使用貸借の終了に伴う立退きについて
- 2025.04.15定期借家契約の活用術
- 2025.04.15Q.自身が所有している不動産が競売にかけられているが、どうにかしたいです。
- 借地トラブルならタウン&シティ法律事務所へご相談を
- 借地の更新の際に支払う金銭トラブル
- 借地上の建物の建替えでよくあるトラブルとは?増改築禁止特約を弁護士が解説
- 借地権の譲渡におけるトラブルとは?地主の承諾が得られない時の対応方法を解説
- 借地への抵当権設定においてよくあるトラブルとは?
- 借地の共有持分の譲渡におけるトラブルとは?
- 借地権の遺産分割の適切な方法とは?
- 借地の更新拒絶が認められる正当事由とは?立退料の設定金額について弁護士が解説
- 借地からの立ち退きに関わる問題を横浜の弁護士が解説
- 借地人が立退きを求められた時、弁護士に相談すべき理由とは?
- Q&A | 「借地権の買取などとんでもない。借地契約を終了させるならすぐに更地にして返してもらいたい!」強硬な地主のために窮地に陥った借地人…借地人側としては何か対抗する手段はないのでしょうか?」
- Q&A | 借地人による「借地権の譲渡」を承諾することの対価として「承諾料」520万円を受け取った地主…譲渡契約が白紙になったことで「支払った承諾料を返して欲しい」と返還を求められましたが、地主は返金する必要があるのでしょうか?
- 定期借家契約の活用術