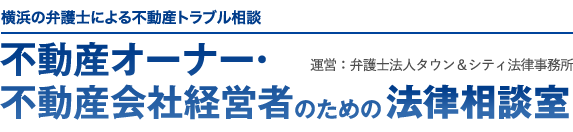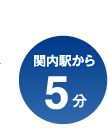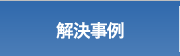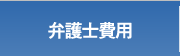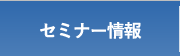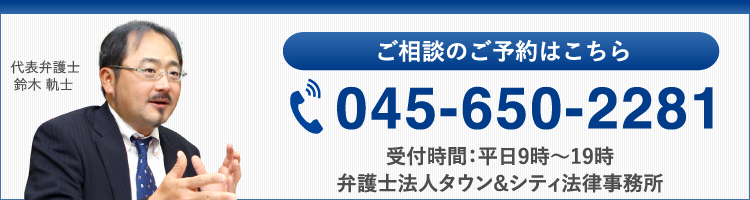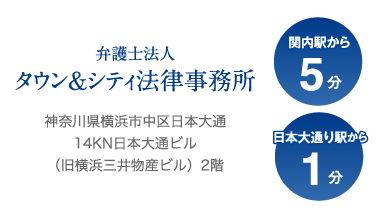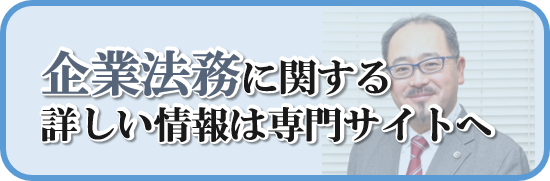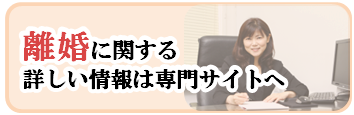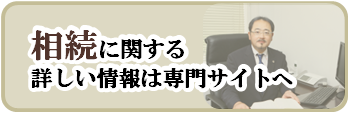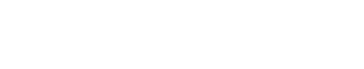建物明渡請求訴訟における占有移転禁止仮処分
1.はじめに
建物(横浜市内の3LDKのマンション)の所有者Aが、その建物をBに賃貸していました。ところが、Bが賃料を長期間滞納しました。そこで、未払賃料の支払を請求し、建物からの退去も求めました。しかし、Bは全く応じません。そのため、AはBとの建物賃貸借契約を解除し、Bを被告として、建物明渡等請求訴訟を提起することにしました。
この場合、Aが勝訴決を得て、それが確定したにもかかわらずBが任意に応じないのであれば、Bに対して建物明渡しの強制執行をすることになります。
ところが、仮にAが勝訴の確定判決を得ても、この訴訟中等にBがAに無断でCに建物を転貸する等して、建物の占有をCに移していた場合には、判決の名宛人となっていないCに対しては強制執行できません。
その場合にはAは、再度Cを被告とする建物明渡請求訴訟を提起せざるを得なくなります。仮に悪質なCだと、更に第三者Dに建物の占有を移すかもしれません。悪質な賃借人は、このようにして賃貸人の権利行使を妨害します(いわゆる「占有屋」等)。
2.占有移転禁止の仮処分とは
上記のような事案に対応するために、建物明渡請求訴訟の提起前(または提起後でも訴訟係属中)に、「占有移転禁止の仮処分」を行うことが考えられます。
占有移転禁止の仮処分とは、裁判所の民事保全制度の一種で、本件のような建物明渡訴訟の被告となる占有者を訴訟前(中)に固定し、勝訴判決確定後の強制執行に備えるための手続です。
上記事案の場合、占有移転禁止の仮処分により建物の占有者はBに固定されるため、仮処分決定後にCやD等の第三者が建物の占有を取得したとしても、Aは、Bに対する建物明渡訴訟の勝訴判決に基づいて、BだけでなくCやDに対しても、建物明渡しの強制執行ができることになります。
建物に賃借人B以外の第三者Cが出入している場合や、賃借人Bが本当に居住しているか確認できない場合等には、第三者への占有移転により強制執行できなくなる可能性が高いです。このことから、このような場合には「占有移転禁止の仮処分」を行う必要性が高いと考えられます。
3.占有移転禁止の仮処分の手続き
占有移転禁止の仮処分の手続は、保全命令手続と保全執行手続の2段階に分かれます。
保全命令手続は、民事保全をするかどうかを審理、判断する段階であり、保全執行手続は保全命令手続で下された命令を執行する段階です。
(1) 保全命令手続
保全命令手続は、裁判所に占有移転禁止仮処分申立書を提出して行います。
申立が認められるためには、賃貸借契約終了等に基づく建物明渡請求権(被保全権利)が存在し、かつ、訴訟中に占有者が変わり強制執行ができなくなるおそれや著しく困難になるおそれがあること(保全の必要性)について、疎明することが必要です。
疎明とは、裁判官に確信とまではいかないが、一応確からしいという推測を得させる程度の証明することです。
このため上記の例で言うと、Aは、Bとの間の賃貸借契約書、Bの賃料の入金履歴、Bへの解除通知書、建物の図面、Bの住民票、Aによる報告書等の証拠資料(基本的には原本を呈示した上で写)を提出します。
通常の場合、申立書提出から数日で仮処分命令が出ますが、この命令を出してもらうために、Aは担保(保証金)を法務局に供託する必要があります。これは仮処分によってBが受ける可能性のある損害を補償するためのもので、裁判所の裁量により、賃料1~3か月分程度の金銭等の供託を求められることが多いです。なお、建物明渡訴訟でAの勝訴判決が確定した場合等には、裁判所による担保の取消し決定により、Aは供託した金銭等を取戻すことができます。
(2) 保全執行手続
裁判所から占有移転禁止仮処分命令が出ると、裁判所の執行官に占有移転禁止仮処分の執行申立書を提出します。申立書が受理され、3万円程度の保管金(予納金)を納めた後、担当の執行官と仮処分執行日時の打ち合わせをします。
執行当日は、執行官が、建物の中に入って占有者や占有状況を調査し、占有移転禁止の仮処分命令が出ていることを記載した書面を、建物内の見えやすいところに貼り付けます。執行後は、執行官から仮処分調書の謄本が本人または代理人宛に郵送されます。
4.おわりに
建物明渡請求訴訟の提起にあたり、占有移転禁止の仮処分が必要かどうかを、まずは十分に検討する必要があります。また、仮処分申立書の作成や資料の収集等の手続は、単純かつ安易とは限らないので、仮処分の手続においてつまずくと、その後の訴訟も円滑に進まないこと等が多いので、建物所有者(本件のA)の損失がより拡大するおそれがあります。
当事務所は2000年の創立以来、数多くの不動産トラブルを扱い、建物明渡請求訴訟の実績(ノウハウと解決実例の蓄積)がある当事務所にぜひご相談ください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
投稿者プロフィール
- 弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県で約30年にわたり弁護士として活動しており、特に不動産分野に注力してきた。これまでの不動産関連のご相談は2,200件を超え、550件ものご依頼を受任。豊富な経験と知識で、常に依頼者にとって最良の結果を追求している。特に、不動産の共有関係や借地関係の解決には強い関心を持ち、複雑な問題も粘り強く解決に導く。
最新の投稿
- 2025.08.06不動産トラブルのセカンドオピニオンを検討中の方へ
- 2025.04.19建物明渡請求訴訟における占有移転禁止仮処分
- 2025.04.18所有者不明土地の解消 ~「特別代理人の選任」による解決方法~
- 2025.04.18所在不明等共有者の持分取得または第三者に譲渡するための手続【令和3年民法改正】について