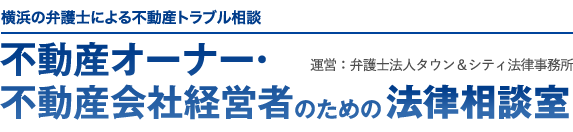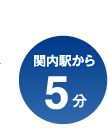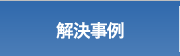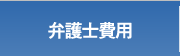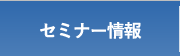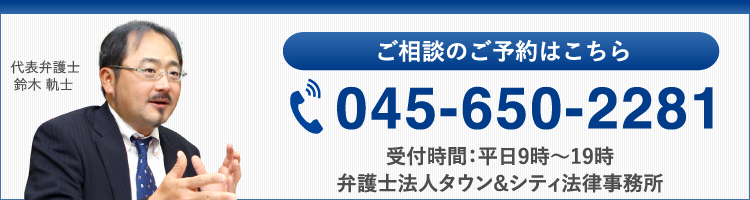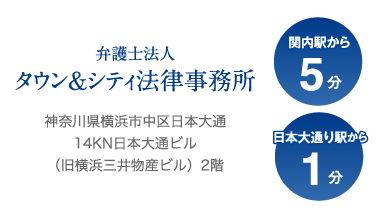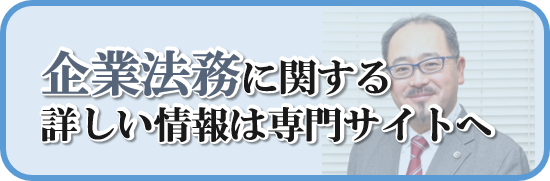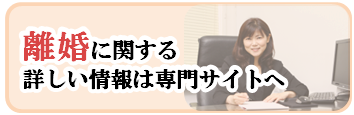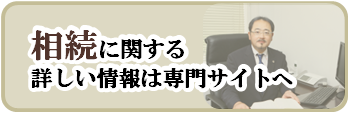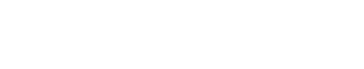不動産の使用貸借の終了に伴う立退きについて
Contents
1. はじめに
不動産の使用貸借には特別な人的関係が基礎にあることが多いです。なぜなら、一般的に不動産は高額なので、無償で貸すことは通常想定されないからです。
ところが、期間が経過することにより、このような人的関係に変動が生じたり、場合によっては消失し、これに伴い紛争に発展するケースも多々あります。
このような不動産使用貸借においては、典型的な紛争の1つとして、使用貸借契約を解消して不動産を明け渡せと請求する、またはされたりするものが挙げられます。そのような場合にはどのような対応すべきでしょうか。
以下では、使用貸借契約についての基礎知識、不動産の使用貸借の終了及び当該不動産からの立退を請求する、またはされた場合の対応について説明します。
2. 「使用貸借契約」について
(1) 賃貸借契約の違い
使用貸借契約とは、簡単に言えば、人に「タダ」で物を貸す契約です。また、親族や友人間に多いように、使用貸借契約は契約書がなく口頭でのみ締結していることが多いです。同じく「貸す・借りる」契約である賃貸借契約との大きな違いは、使用料(賃料)の有無にあります。賃貸借契約では賃料(対価)を支払う必要がありますが、使用貸借では、このような対価を支払う必要はありません。
(2) 「使用貸借」契約の終了時期
使用貸借契約の終了時期がいつかを判断するためのポイントは契約締結時に、その①期間を定めたのか、②使用及び収益の目的を定めたのか、③終了を求めるのが借主か貸主かの3点です。
(ⅰ)期間の満了
使用貸借にあたって期間を定めた場合は、当然ですが、期間の満了によって終了します。
(ⅱ)使用及び収益の目的
使用貸借契約の目的を定めた場合には、その目的に従って使用及び収益を終えた場合、または目的に従って使用及び収益するのに足りる期間が経過した場合に終了します。目的を定めていなかった場合には、貸主は借主に対して、いつでも解約し、返還を求めることができることになっています。
(ⅲ)終了を求めるのが借主か貸主か
使用貸借契約は、ほぼ、「借主のための」契約なので、借主はいつでも解約をすることができます。また、借主が死亡した場合には契約は無条件で終了します(借家権や借地権のように「相続」が問題となることもありません)。
一方で、貸主が解約する場合には、上記の期間も目的も定めなかった場合を除けば、上記のような終了原因(期間の満了や目的の達成・達成に必要な期間の経過等)が必要です。
3. 立退きを要求する場合について
(1) 使用貸借契約の終了を争われることがあるため、注意が必要
まず、借主が立退きしたくないと言って、「終了原因」があるのかどうかを争ってくることがあり得ます。使用貸借契約が終了していなければ立退き義務はないので、いかに「終了原因」を認めてもらうかが肝要となります。
使用貸借契約が締結された経緯や、経済的・精神的な扶養が期待されるといった当事者の関係性、それまでの使用期間の長短、建物の価値の大小、双方にとっての土地・建物使用の必要性の比較といった諸要素を考慮して、使用貸借契約が終了しているか否かが判断されることになります。
(2) 立退料の支払による解決もあり得る
仮に上記の終了原因がない場合には、立ち退きを求めることは出来ないのでしょうか?この場合、一定の金額を立退料として支払うことと引換に立ち退きしてもらうといった解決策もありえます。
お金で解決することによって以後の人間関係に気を遣う必要もなくなります。すなわち、紛争から早く解放されることによる精神衛生上のメリットがあります。
この場合には、建物に関する資料(建物の利用価値の算出根拠等)等に基づいて使用借権の価格を算定した上で立退料に関する交渉をすることになります。
すなわち、使用借権の価格をいくらと算定するかがポイントとなります。ちなみに、公共用地の取得に伴う損失補償においては土地使用借権の価格は借地権価格(住宅地だと、更地価格の6割程度)の3分の1(=更地価格の18%)程度が標準とされていますが、一般市民間で不動産使用貸借を解約する際の使用借権の価格の計算方法には種々の考え方があり、いずれを用いるかどうかで、貸主側は経済的負担が、大きくことなることになります。
4. まとめ
以上のとおり、通常、特別な人間関係が基礎にあることが多い不動産使用貸借は、複雑な問題点も多くあるため、適切な対処のためには専門家の助力が望ましいといえます。
当事務所では弁護士だけでなく、税理士・司法書士の不動産登記や税務についても協力できる専門家をそろえています。そのため多角的な視点から、当事者にとって最も利益になる解決案を提案することができます。
不動産に関するご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
投稿者プロフィール
- 弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県で約30年にわたり弁護士として活動しており、特に不動産分野に注力してきた。これまでの不動産関連のご相談は2,200件を超え、550件ものご依頼を受任。豊富な経験と知識で、常に依頼者にとって最良の結果を追求している。特に、不動産の共有関係や借地関係の解決には強い関心を持ち、複雑な問題も粘り強く解決に導く。
最新の投稿
- 2025.08.06不動産トラブルのセカンドオピニオンを検討中の方へ
- 2025.04.18不動産の使用貸借の終了に伴う立退きについて
- 2025.04.15定期借家契約の活用術
- 2025.04.15Q.自身が所有している不動産が競売にかけられているが、どうにかしたいです。