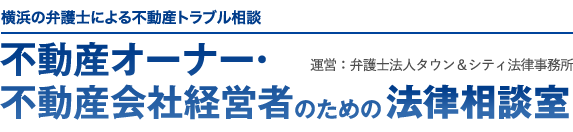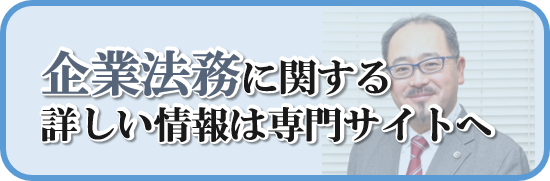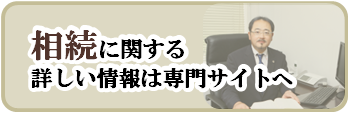売買契約書・媒介契約書について
Contents
はじめに
売買契約書の重要性とは
宅建法37条書面であること=宅建業者は、37条1項各号に掲げられた事項を記載した書面を交付すべきことを義務付けられている。→書面の交付義務違反は業務停止処分の対象になり(法65条2項2号)、50万円以下の罰金が科せられることに(法83条1項2号)。
※1 37条書面に記載すべき具体的事項売買契約の成立を証明する文書であること
A「買付証明書・売渡承諾書」との違い(※8)(※9)〔裁判例1〕〔裁判例2〕〔裁判例3〕
B「不動産取り纏め依頼書」との違い(※10)〔裁判例4〕
C「仮契約書」との違い(※11)〔裁判例5〕
D「協定書」との違い(※12)(※13)〔裁判例6〕
E「売買契約書案」との違い(※14)〔裁判例7〕
F「覚書」との違い(※15)〔裁判例8〕
G「売買予約」との違い (※16)〔裁判例9〕
媒介契約書の重要性とは
以下2点が要素になります。
・宅建法34条の2書面であること
・媒介契約成立を証明する文書であること
「標準媒介契約書」との関係
「媒介契約の有効期間又は有効期間の満了後2年以内に、甲(委託者)が乙(宅建業者)の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的物件の売買又は交換の契約を締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます」(専任約款10条、専属約款10条、一般約款12条)
「標準媒介契約約款」に基づく仲介業者の報酬請求権の要件事実(東京地判平成13.6.29判タ1104号201頁)
・宅建業者と委託者との間において標準媒介契約書による媒介契約が成立していること
・媒介契約の有効期間または有効期間満了後2年以内に、委託者が宅建業者の紹介によって知った相手方と売買契約を締結したこと
・委託者が売買契約の締結に当たり宅建業者を排除したこと
・宅建業者が売買契約の成立に寄与したこと及びその寄与割合
各契約書の作成ポイント
売買契約書の作成ポイント
不動産売買契約書の仕組み(※2)
売買の成立要件
以下が成立要件の要素にあたります。
1.当事者
2.目的物の特定
3.売買代金の額の確定
4.手付契約
契約内容と履行について
1.目的物 → 所有権移転、境界の明示、付帯設備
2.売買代金 → 代金支払、清算の要否(公簿売買・実測売買)
3.履行期日
4.担保責任など → 目的物の制限・負担の除去、瑕疵担保責任、危険負担
5.その他 → 固定資産税などの分担、賃料などの収益・管理費などの負担の清算、登記費用、貼付印紙代の負担
契約関係からの離脱の種類
1.約定解除 → 手付解除、ローン契約とローン解除
2.目的不達成による解除 → 瑕疵担保責任、危険負担
3.債務不履行解除 → 契約解除と損害賠償額の予定・違約金
不動産売買契約書を検討するに当たり確認すべき事項(※3の1及び2)
【参考】
消費者契約のうち、売主が消費者、買主が事業者である場合には、瑕疵担保責任について免責特約を定めても有効であるが、売主が事業者で買主が消費者である場合には、売主である事業者の瑕疵担保責任について免責特約を付することはその内容によっては無効となることから注意が必要である(消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号=同年5月25日に成立し翌29年6月3日に施行))(※4)。
※4消費者契約法(消費者の解除権を放棄させる条項の無効)
第8条の2 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一.事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項
二.消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的
物に隠れた瑕疵があること(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があること)により生じた消費者の解除権を放棄させる条項
中間省略登記
旧不動産登記法の下では、所有者かAからBが不動産を買受け、これをCに転売する場合、AからB、BからCへ順次所有権移転登記をするところ、Bが登録免許税・不動産取得税の課税を回避するため、売買契約書に、「売主は、買主またはその指定する者に対し本物件の所有権移転登記申請手続をしなければならない」と定め、Aから直接Cに所有権移転登記する中間省略登記がなされることがあった。不動産登記法が改正され、所有権移転登記申請手続には登記原因を証する具体的な情報を提供する「登記原因証明情報」が必要となり(不動産登記法61条)、AC間で売買契約が締結されていないため従来の中間省略登記が事実上困難となった。そこで、AB間の売買契約における「買主(B)の地位の譲渡」によって、AからCに直接所有権移転登記をする方法、AB間において「第三者(C)のためにする契約という取引形態をとって、AからCに直接所有権移転登記をする方法がとられることがある。
マンションの専有部分の床面積
分譲マンションの専有部分の床面積は、売買契約書では壁芯面積(建築基準法施行令2条1項3号による算定方法)により表示されるが、竣工後の登記面積は内法面積(壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積、不動産登記規則115条による算定方法)により表示され、相違がある。
署名を巡る問題
(文例)
下記売主・買主は、本物件の売買契約を締結し、本契約を証するため契
約書正本2通を作成し、売主及び買主が署名押印のうえ各自その1通を保有する。
平成○○年○月○日
(売主)住所
氏名 印
(買主)住所
氏名 印
媒介業者 免許証番号 ○○県知事(○)第○○○○号
事務所所在地
商号(名称)
代表者氏名
宅地建物取引士 登録番号 ○○県知事第○○○○号
氏名 印
媒介業者 免許証番号 ○○県知事(○)第○○○○号
事務所所在地
商号(名称)
代表者氏名
宅地建物取引士 登録番号 ○○県知事第○○○○号
氏名 印
契約当事者である売主と買主は、売買契約書記載の内容について合意したことを確認する証として署名欄に署名する。当事者が個人の場合には自らの氏名を記し(自署)捺印をすることが本人の意思を確認する意味で重要である。印章(はんこ)は、必ずしも実印(市町村長にあらかじめ届け出て印影を証明する印鑑証明書の交付を受けることができる印章)に限らず、認印(いわゆる三文判)でも契約書の効力には変わりがない。ただ、本人の印章が押されたかどうかが争われた場合、実印であれば印鑑証明書によって印影を照合して本人の印が押されていること(民訴法228条4項)を立証し、売買契約書が本人の意思に基づいて作成されたことの立証が容易になる。売主又は買主が法人のときは履歴事項証明書で法人の名称、所在地、代表者などを確認する。新築分譲マンションの売買では、売買契約書を1通作成し正本は買主が所持し写しを売主(事業主)が所持することが多い。
【本人以外の署名】
当事者本人に代わって代理人が署名する場合、「○○○○代理人□□□□印のように本人の名前を表示し代理人が署名捺印し、本人が自署し実印を押した委任状を添付する。わが国では本人以外の者が本人の氏名を書いて捺印すること(いわゆる署名代理)が珍しくない。売主が高齢者で認知症のため判断能力を欠く状況にあり、後見開始の審判(民法7条)を受けないまま家族が本人の署名をしても、本人に意思能力がなければ契約締結行為は無効となる。売買仲介に関与する宅建業者は、代理人の代理権限の有無・内容を調査すべき義務を負うことから、本人以外の者が契約書に署名する場合、本人の意思能力の有無、本人の許諾の下に行われた署名か、代理権限の授与があるか、本人と署名者との間柄、本人に代わって署名した理由、当事者の属性などを確認する必要がある。
【契印】
契約書を一枚の書面にすることは難しく数頁にわたる。後日、契約書の一部が差し替えられることを防ぐため、袋綴じをして表紙・裏表紙の綴じ代に当事者が押印するか、各頁の繋ぎ目に押印する。
【持回り契約】
契約締結の年月日は当事者間において売買契約が成立した日を特定するために記載する。契約当事者が対面して署名した日を記載すべきであるが、時には、契約当事者の一方または双方が複数であるとか、遠隔地に居住していて実際に一堂に介して契約書を締結できないため、仲介業者が契約書を順次持ち回ったりして署名を求めることがある。各人の署名した日が異なる場合は契約当事者のうち最後に署名した日が契約締結行為の完結した日として契約締結日となる。契約当事者が縁起を担いで大安吉日としたり、実際の取引日とは異なる日付に遡らせる場合もある。特段の事情がない限り、当事者の意思は契約締結日として記載された日が契約の効力発生日とする趣旨であろうが、契約締結日が起算点となり権利関係に影響を及ぼす場合に疑義が生じないようにすべきである。
【仲介業者の記名押印】
仲介業者は、売買契約書の「仲介業者(または媒介業者)」欄に記名押印する。当事者双方の当該売買契約に関する合意が成立したこと、仲介業者が当該売買契約を仲介したことを証する趣旨である。宅地建物取引士は、売買契約書に記名押印することが義務付けられている(法37条3項)。契約当事者の双方または一方が宅建業者の場合や複数の仲介業者が売買取引に関与した場合、当該免許登録番号などを記載して記名押印し、それぞれの宅地建物取引士の記名押印をする。
【立会人】
不動産売買契約書に「立会人」欄を設け、売主・買主以外の第三者(弁護士など)が立会人として記名押印することがある。契約の立会とは、売主・買主が売買に関して合意した事実を見届けることをいう。仲介業者が記名押印する場合、売買契約が成立したことを確認するとともに仲介業者が売買仲介したことを示す趣旨でもある。仲介業者が契約当事者から仲介委託を受けたかどうかは、現実に仲介業務をしたかなど実質的な取引事情を考慮すべきであって、立会人欄に記名捺印したことだけで契約当事者の一方または双方から仲介委託を受けたことを基礎付けることはできない。
媒介契約書の作成ポイント
宅建業法34条の2=仲介契約関係の曖昧さ、不透明さに起因する紛争を防止するため、宅建業者が委託者と宅地建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、所定事項を記載した書面を作成して記名・押印し、委託者にこれを交付することを義務づけた。
媒介契約書への記載事項
媒介の目的物である宅地建物(いわゆる「受託物件」を特定するために必要な表示)
・宅地=その所在、地番等で表示をする
・建物=その所在、種類、構造等で表示をする
☆通常、全部事項証明書(旧不動産登記簿謄本)の表題部登記を記載
☆媒介の目的物が宅地の一部の場合は、「…番の一部地積約○○㎡」と記載し、図面等で特定する。
☆未登記建物の場合は固定資産税評価証明書等で特定する。
「売買すべき価額」(媒介価額)=売買媒介における「売買すべき価額」=「売出し価格」とも呼ばれ、いわゆる「売り値」=宅建業者が依頼者から売買の媒介を受託するに当たって、宅建業者が依頼者と協議し広告などで表示したり買主に提示したりする価格≠売買契約が成立したときの売買価額(=「成約価額」)
・「専任媒介契約かどうか」
・媒介契約の有効期間、解除に関する事項
・指定流通機構への登録に関する事項
・報酬に関する事項などを記載しなければならない(専任約款3条、専属約款3条、一般約款3条参照)
物件購入の仲介契約では「依頼者が取得を希望する物件が具体的に決まっていない場合には、物件の種類、価額、広さ、間取り、所在地、その他の希望条件を記載することとして差し支えない」とする(宅建業法34条の2に関するガイドライン)。=「取引物件の所在○○方面、宅地○○㎡前後、購入希望価額○○○○万円」等、委託者のおおよその希望条件を記載すれば足りる。←同法34条の2及び標準媒介契約書は、買受仲介の委託については、取引物件について買受希望条件がおおむね確定すれば、たとえ目的物が特定されなくても仲介契約の成立を認めるとの考えを採用した(建設省計画局不動産課監修「不動産取引の標準媒介契約約款」28頁【末吉興一発言】)。
仲介業者が買受物件の探索をなしえない程買受け希望条件が具体的でなく漠然としている場合は、仲介契約は成立しているとはいえないが、上記ガイドライン記載程度の物件の概要が示されると、仲介業者が取引物件の探索に着手できる状態となり、買受仲介の委託・受託に関する意思表示の合致があれば→「遅滞なく」媒介契約の内容を書面化すること=媒介契約書の交付が義務付けられることに。

媒介契約書を作成しないまま直接契約が行われた場合の取り扱い(=直接取引と報酬請求権の問題)
ポイント
直接取引の紛争事例では、標準媒介契約書を締結していないことが多いため、次のような論点が出てくる。
・仲介契約が成立したか、報酬を支払う約束(報酬支払の合意)があったか?
・仲介契約が成立したが、その後、途中で解除されたか?
・委託者が仲介業者を排除したか、委託者の排除行為が信義則違反に該たるか?
・仲介業者は売買契約の成立に寄与したか?その寄与割合の有無と程度
標準媒介契約書を締結していない場合
・法律構成=民法130条または同条の規程の趣旨、信義則違反等
この場合の直接取引の態様
以下3つの態様があります。
A:委託者が報酬の支払を免れる意図で仲介業者を排除する事案
B:委託者が仲介業者の仲介行為に不信を抱き仲介業者を介さずに取引の相手方と直接交渉した事案
C:委託者と相手方との取引条件に開きがあり契約交渉が打ち切られた後に当事者のいずれかが直接交渉を申し入れ成約に至った事案
上記各態様を分析する際の要点
以下3つの要点になります。
ア:仲介業者が排除された時期とその理由
イ:当事者が直接交渉を始めたきっかけと成約に至る経緯
ウ:仲介業者の仲介行為の売買契約の成立への寄与度
これらは民法130条または同条の規程の趣旨を根拠とする考え方です。
要件事実とは
要件事実の要素は以下の6つです。
a:仲介業者と委託者との間において仲介契約が成立していること
b:仲介業者による仲介行為が存在すること
c:委託者が仲介業者の紹介によって知った相手方と売買契約を締結したこと
d:委託者が売買契約の締結に当たり仲介業者を排除したこと
e:仲介業者が委託者に対し、cの売買契約の締結をもって条件成就とみなす意思表示をしたこと
f:仲介業者が売買契約の成立に寄与したこと及びその寄与割合
相当因果関係を根拠とする考え方
仲介業者の仲介活動と仲介契約解除後の売買契約成立との間に相当因果関係があるときは報酬特約または商法512条に基づいて報酬請求権を有することになる(東京高判昭和34.6.23下民集10巻6号1324頁、東京地判昭和45.11.25判時629号87頁、東京高判昭和47.10.27判タ289号331頁、高知地判昭和57.2.22判タ474号188頁、東京高判昭和61.12.24判時1225号63頁、福岡高判平成10.7.21判時1695号94頁等)。
要件事実
要件事実の要素は以下の5つです。
a:仲介業者と委託者との間において仲介契約が成立していること
b:仲介業者による仲介行為が存在すること
c:委託者が仲介業者の紹介によって知った相手方と売買契約を締結したこと
d:仲介業者の仲介行為とcの売買契約成立との間に相当因果関係が認められること
e:仲介業者が売買契約の成立に寄与したこと及びその寄与割合
仲介契約の成否:直接取引の事案では、仲介業者が委託者から排除され、委託者と相手方間の売買契約成立時に立ち会っておらず、標準媒介契約書を締結していないことも多いため、仲介契約の成否が争点に。→従来の裁判例では、直接取引事案による報酬請求事件における仲介契約の成立については、比較的緩やかに認定している。←仲介業者が、委託者のために成約に向けて仲介業務を進めている途中で、委託者が仲介業者を排除したことが信義則に違反し、仲介業者の報酬請求を認容すべき具体的妥当性の考慮が働いていることから。
売主(所有者)との売却仲介契約の成立を基礎付ける事実
ア:売主が仲介業者に対し取引物件の土地測量図などの資料を提供したこと
イ:売主が仲介業者と売却希望価格などの売却条件を打ち合せ提示したこと
ウ:仲介業者が自社のホームページや販売広告に売却物件として掲載することに売主が同意したこと
エ:仲介業者が買い受け希望者との契約交渉に関与することについて、売主が特に異議を述べず、交渉内容の報告を受けたり意見を述べたりして容認していたこと
オ:売主が仲介業者に不動産取り纏め委任状、売却依頼状、売渡承諾書を提出したこと(逆に売却仲介契約の成立を基礎付けるに至らない事実)
カ:売主が別の仲介業者に委託していること
キ:売主が仲介業者の介入を拒否していること
ク:仲介業者に対し報酬を支払わない旨表明していたこと
買主との買い受け仲介契約の成立を基礎付ける事実
あ:買主が仲介業者に希望する取引物件の探索を依頼したこと
い:仲介業者から買主が現地案内、物件資料の提供を受けたこと
う:買主が仲介業者から紹介を受けた取引物件について買受希望条件を提示したこと
え:買主が仲介業者に対し価格等の買受交渉を依頼したこと
お:買主が買付証明書を仲介業者に提出したこと
か:買主が仲介業者の売買取引への関与や仲介業務の提供に特に異議を唱えずに受け入れたこと
き:買主が仲介業者に対し報酬の支払を提示し、買主が特に異議を述べていないこと等(逆に買主との買受仲介契約の成立を基礎付けるに至らない事実)
く:仲介業者が取引物件を紹介したが、買受希望者が仲介業者に買受交渉を依頼しないと断ったこと
け:仲介業者が売主側の受託業者であるため買受希望者のために仲介業務をしたものではないこと
こ:買受仲介に関与することを断られたこと
仲介業者の紹介によって知った相手方=委託者が、仲介業者から告げられるまで、当該取引物件が売却予定であったとか、所有者が売却意思を有しているとか、買受希望者が買受の意思を有していた者であることを知らなかったこと
具体例
仲介業者Xが買受希望者Yに数か所の売却物件を現地案内し、Xが本件土地建物を紹介したところ、Yが「この土地は他に頼んであるから、見る必要はない」と言って断った後、Yが本件不動産を購入した場合、「当時既に本件土地建物については別個のルートを通じてYと所有者との間に売買の交渉が進行中だったので、YはXにこのことを告げてその斡旋を断ったのであるから」Yの仲介の対象から除外されており、Yが本件土地建物を購入したとしてもXの「紹介によって知った相手方」には該たらない(東京地判昭和34.11.16下民集10巻11号2431頁)。
仲介業者の排除の有無
直接取引では、委託者が仲介業者を「排除」したといえるかどうかが、最大の争点となる。「排除」=仲介業者と委託者間で仲介契約成立後、仲介業者が委託者に物件情報を提供したり取引交渉に入る等、成約に向けて仲介活動をしている過程で、委託者が仲介業者を介さないで相手方と直接契約交渉し、仲介業者の仲介行為による成約の機会を妨げたり喪失させ、これが信義則に反すること
委託者が仲介業者を故意に排除する意思を有すること(次のア、イの各事実から裏付けが可能(最判昭和45.10.22民集24巻11号1599頁))
ア:仲介業者が仲介業務に関与した最終的な時期とその後当事者間で締結した売買契約の時期とが近接していること
イ:当事者間で成立した売買価額が仲介業者の斡旋調整していた額に近接している事実
委託者の故意性の要否
直接取引と認定されるためには、委託者において仲介業者を排除する意思もしくは認識を必要としない。
【参考】
①上記の相当因果関係を根拠とする考え方⇒仲介業者を排除するに至った事情は相当因果関係の有無の判断要素の一つにすぎず、仲介業者の仲介行為が売買契約の成立に寄与している事実を重視する。
②標準媒介契約約款にいう「排除」は仲介業者を排除する故意の存在を要件としてはいない。
〔裁判例10〕=(標準媒介契約約款中の直接取引と認定される要件が)媒介契約の有効期間の満了後2年以内と長期に定めていることからすれば、委託者Yが媒介業者Xを「意図的に排除する目的の有無にかかわらず、媒介者の行った労力に対し、その効果が残存していると認められる相当な期間について、媒介者の寄与に応じて仲介手数料の支払義務を認める趣旨があるものと解するのが合理的であること、YはXに対し本件物件の売買交渉をXに関与させることなく継続することを告げてその了解を得た事実は認められないこと」をもって約款に基づく相当額報酬請求権の発生を認めた。
委託者による排除が信義則違反となることを基礎付ける事実
仲介契約の存続期間中に委託者が仲介業者を介さずに相手方と直接交渉して売買契約を成立させる行為=委託者が仲介業者を「排除」したことを基礎付ける事実の一つになり得るが、これだけでは仲介業者の「排除」を決定づけることにはならない。次の各事実を総合的に考慮する必要あり。
a委託者が仲介業者を排除した時点において
ア:仲介業者が委託者に対し提供した物件情報の内容、資料など
イ:仲介業者が成約に向けてどの程度の尽力をしていたか、特に取引条件の調整、合意の事実
ウ:取引経過の状況、売買契約の成熟度
b委託者が仲介業者を排除した以降、相手方と交渉した時期と交渉内容
c委託者が相手方と直接交渉した時期と売買契約が成立した時期とが近接しているかどうか
d仲介業者を通じて交渉していた取引条件と直接取引により当事者間で成立した売買契約の取引条件とがどの程度近接しているか
e委託者が仲介業者を介さずに相手方と直接交渉する合理的または正当な理由が存在したか、仲介業者において仲介契約上の義務違反があるか
標準媒介契約書を締結している場合
標準媒介契約書=「媒介契約の有効期間または有効期間の満了後2年以内に甲(委託者)が乙(宅建業者)の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的物件の売買または交換の契約を締結したときは、乙は甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます」と定めている(専任約款10条、専属約款10条、一般約款12条)。
要件事実(東京地判平成13.6.29判タ1104号201頁)
・宅建業者と委託者間において標準媒介契約書による媒介契約が成立していること
・媒介契約の有効期間または有効期間満了後2年以内に、委託者が宅建業者の紹介によって知った相手方と売買契約を締結したこと
・委託者が売買契約の締結にあたり宅建業者を排除したこと
・宅建業者が売買契約の成立に寄与したこと及びその寄与割合
・標準媒介契約約款は、委託者が媒介契約を解除しないで直接取引した場合だけでなく、媒介契約を解除した後「媒介契約の有効期間の満了後2年以内」であれば報酬請求ができる。
媒介契約が成立後、途中で解除された場合
・仲介契約は準委任契約=委託者はいつでも仲介契約を将来に向かって解除可能(民法651条1項)。
解除のパターンは
A:委託者または仲介業者が明示的に仲介契約を解除した場合
B:委託者である売主が取引物件の売却を断念し、その旨を仲介業者に伝えて合意解約されたとみるべき場合
C:委託者である買主が取引物件の購入を見合わせる旨を仲介業者に申し入れ合意解約されたとみるべき場合
D:相手方との契約交渉が進まず、委託者も成約に向けた交渉意欲を失い、媒介契約期間として定めた3ヶ月を超えてお互いに連絡しなくなり、仲介契約が期間満了をもって終了したとか黙示的に合意解約されたと解される場合等々。
ポイント
委託者が仲介契約を解除した後、仲介業者から紹介された取引の相手方と直接売買契約を締結したからといって、この事実のみで信義則にもとる直接取引というわけではない。仲介業者の責めに帰すべき事由を原因として委託者が仲介契約を解除し、その後、相手方と直接交渉して売買契約を成立させる場合もある。→仲介契約が存続しているか、委託者がなぜ仲介契約を解除したかについては個々の取引経過を検討する必要があることに。
・標準媒介契約約款=直接取引の場合の報酬請求について「媒介契約の有効期間または有効期間の満了後2年以内に、甲(委託者)が乙(宅建業者)の紹介によって知った相手方と乙を排除して」目的物件の売買契約を締結したときと定める(専任約款10条、専属約款10条、一般約款12条)→委託者が媒介契約を解除した後、2年以内に仲介業者の紹介によって知った相手方と売買契約を締結し、これが「乙を排除」したことに該当するときは直接取引として報酬請求が可能に。
委託者が仲介業者から提供を受けた物件情報(取引の相手方、取引物件)や仲介業者の取引交渉の成果等を利用して相手方と直接交渉して売買契約を締結することが信義則に違反する場合→「排除」に該たる。
委託者が仲介業者を排除した事案であっても、上記の「委託者による排除が信義則違反となることを基礎付ける事実」記載の事実に加えて下記の事実を併せて検討する必要はある。
・仲介契約が解除された経緯、前後の事情
・委託者が仲介契約を解除したときの説明が事実に反したもの(虚偽)であったか
・仲介契約が解除された時期と売買契約が成立した時期が近接していること
・仲介契約が解除された時期の取引条件と委託者と相手方との間で成立した売買契約の取引条件とが近似していること
委託者からの抗弁
委託者が取引の相手方と直接取引をしたとしても、仲介業者の責めに帰すべき事由が存する等正当な理由があるとかで信義則に反しない場合→不当に仲介業者を排除したことにはならない。
主張・立証
仲介業者は、委託者が仲介業者を介さないで直接取引によって売買契約を成立させたことを主張・立証すればよい。←委託者が売買仲介を委託した仲介業者が仲介行為をしている最中に、委託者が取引の相手方と交渉し売買契約を成立させること=特段の事情がない限り信義則に反するものと推認されるから。
委託者は、仲介業者を介さないで直接取引をした行為が信義則に反しないこと、正当な理由があること(=具体的には仲介業者の誠実義務違反、説明義務等の注意義務違反、信頼関係の破壊などを基礎付ける事実等)等を主張・立証することに。
確認すべき事項
仲介契約が解除されていない場合
・仲介業者が委託者に対し、取引物件に関する情報をどの程度提供していたか
・委託者は仲介業者に対し、契約交渉についてどのような希望条件を示していたか
・仲介業者が相手方(またはその仲介業者)との間で、どのような契約交渉をし、委託者に対し仲介活動に関する報告、連絡、相談などをどのようにしていたか
・仲介業者が排除された前後の経過、委託者や相手方の態度
・相手方との契約交渉の進捗状況、特に売買代金などの取引条件をどの程度協議し検討したか、どのような取引条件についてどの程度開きがあったのか
・売渡承諾書、買付証明書の授受はあったか
・売買契約の成立間際だったか(重要事項説明書や売買契約書の案文の提供・検討の有無)
・仲介業者が委託者へ連絡した最後はいつ頃か、委託者が仲介業者に連絡してきたのはいつ頃か
・委託者が直接取引をした前後の状況
・仲介業者が直接取引を知ったきっかけ、委託者が相手方と直接取引したことを否定したか、どのような説明をしたか
仲介契約が解除された場合
・仲介業者との仲介契約が解除された当時の契約交渉の進捗状況
・仲介業者との仲介契約を解除したとき、委託者が仲介業者にどのような説明をしたか(虚偽の説明があったか)
・委託者が仲介契約を解除する正当な理由や合理的な理由があったか
・仲介契約が解除された後、委託者が相手方との取引交渉を始めた経過やきっかけは何か
・委託者と相手方が取引交渉を再開した時期は、仲介契約が解除された時期とどの程度近接しているか
・委託者が相手方と直接売買契約を成立した取引条件(価格など)は、仲介業者が交渉していた取引条件とどの程度開きがあったか
・仲介業者がなすべき調査・説明義務違反(仲介行為の瑕疵)の有無
報酬額の算定について
直接取引と報酬
直接取引がなされた場合:標準媒介契約約款=「契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬」を請求できる、と。←仲介業者が契約締結に至るまでに排除されたため、その後の協議交渉や重要事項説明書の交付や説明、売買契約書の交付、契約締結や決済等の売買契約の節目となる場面に立ち会っていないため。
参考
①委託者が故意に仲介業者を排除した場合:主位的に民法130条に基づく約定報酬を請求し、予備的に標準媒介契約約款に基づいた相当額の報酬請求を。
☆標準媒介契約書を締結していない場合→まずは仲介契約の成立自体が争点に。次に直接取引に該当するかどうかが争点に。更に「相当の」報酬額の算定が争点に。
☆☆仲介業者=商人(商法502条11号、4条1項)→報酬合意がなくても商法512条に基づき報酬請求権がある。
②報酬告示=仲介業者が委託者に対し請求できる報酬の最高限度額を定めたものに過ぎない。→当然に報酬告示の最高限度額を請求できるものではない(最判昭和43.8.20民集22巻8号1677頁等)。
【報酬額の算定】
A 委託者と仲介業者間で具体的な報酬額を支払う旨の報酬合意があり、かつ委託者の故意により仲介業者を排除した場合→民法130条に基づいて条件成就とみなし約定報酬額の請求を全部認容した裁判例もある(大阪高判平成4.11.10詳解不動産仲介契約1213頁、東京地判平成5.7.26金判964号42頁等)。
B 最判43.8.20が示した「取引額、媒介の難易、期間、労力その他諸般の事情を斟酌して定められる性質のもの」を前提に売買契約の成立に至る寄与度を考慮して報酬額を割合的に認定されている。→標準媒介契約約款=「契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬」を請求することができる、との定め=従来の判例を踏襲している。
寄与度を基礎付ける事実
A:売却仲介
仲介業者が売主に買主(取引の相手方)の存在を知らせる
買受仲介→仲介業者が買主に売却物件の存在を紹介し物件情報を提供する=いずれも売買契約を成立に至らしめる機縁、端緒として重要な価値を有するものとして評価される(東京地判昭和35.3.29判タ106号51頁、東京地判昭和37.10.22判時328号28頁、大阪地判昭和44.11.19判時599号60頁、東京地判昭和47.11.15判時698号75頁、東京地判昭和56.6.29判時1022号74頁、東京高判昭和61.12.24判時1225号63頁)。
B:仲介業者が相手方と契約交渉している途中の段階で、委託者が仲介業者を排除し相手方と直接交渉して売買契約を成立させた場合、仲介業者を排除したものの、委託者(または別の仲介業者)が従前仲介業者が成約に向けて尽力していた仲介行為(仲介活動)を白紙にして一からやり直すことはなく、むしろ、従前仲介業者が積み重ねてきた交渉内容を基に交渉を再開して歩み寄り成約している→仲介業者の先行した仲介活動が、売買契約の成立に寄与したことを評価すべき。⇒直接取引における報酬額の算定は、仲介業者が委託者によって排除された時点までに売買契約の成立に向けて尽力した仲介行為(仲介活動)が、その後契約成立に至るためにどのように寄与、貢献したか(寄与度、貢献度)によって判断される。→仲介業者が成約に向けて尽力したものの価格交渉が難航し、その後、委託者または別の仲介業者の尽力によって、当初の委託者の希望に沿った取引条件で売買契約が成立した場合→別の仲介業者の交渉能力や条件調整能力を評価せざるを得ない事情もあるため、委託者が仲介業者を排除した事情は考慮するとしても、排除された仲介業者の成約に対する寄与度が減じられる事情にすぎない。⇔仲介業者としては、売買契約成立に寄与したことを積極的に主張・立証することに。
・仲介業者が委託者によって排除されるまでに、どのような仲介行為(物件情報の提供、価格調整等)をしたか
・仲介業者が売買取引に関与した期間、労力、支出した費用、仲介の難易
・価格等の取引条件が難航したか、どのように価格交渉を重ねたか
・委託者が仲介業者を排除した時期は、どのような取引段階であったか
・委託者が仲介業者を排除した事情、信義則違反の有無・程度等
・報酬の支払期日と遅延損害金の起算点
・仲介業者が委託者に対し条件成就とみなす旨の意思表示をし、報酬請求した日から 遅滞に。報酬請求した書面または訴状送達日の翌日から支払済まで年6分の割合による遅延損害金(商法514条)を求めることが可能(東京地判昭和60.8.6判時1196号126頁、東京高判昭和61.12.24判時1225号63頁、東京地判平成7.4.20判時1552号67頁)。
直接取引に関与した別の仲介業者に対する損害賠償請求の可否
直接取引に関与した別の仲介業者に対する損害賠償請求
(別の仲介業者)Y3は、売主Aとの売買取引の契約交渉の再開、成約に向けた尽力の依頼を受けた場合、仲介業者として、他の仲介業者Xの報酬請求権を不当に侵害しないように配慮すべき注意義務を負う(認容例として横浜地判平成18.2.1判タ1230号197頁)。→Y3がXの仲介による売買取引へ関与することが不当なものかどうかは、従前の仲介業者の仲介行為の内容、従前の仲介業者を排除することについての正当な理由があるか、等についてどの程度委託者から確認していたかに関わってくる。
売主または売主側の仲介業者に対する損害賠償請求
売主Aが売却仲介を仲介業者Y1に委託し、Y1がAのために仲介業務に従事していても、買主Y2は誰に仲介を委託するかは自由に決めることができる。=Y2はY1ではなく、X及びY1以外の仲介業者Y3に購入仲介を委託することもできる。
→この場合に、XのAまたは売主側の仲介業者Y1に対する損害賠償請求が認められるための要件は、
・AやY1が、Y2に対し、Xを排除して直接AまたはY1との交渉を働きかけたり、
・Y2がAやY1に対し直接交渉を求めたようなXのY2に対する報酬請求権を不法に侵害する行為に該当することが必要(詳解不動産仲介契約1251頁以下)。

売買契約書・媒介契約書にまつわるよくあるトラブル事例など
当事務所で解説している紛争事例はこちら
※1宅建業法における37条書面に記載すべき事項
1~6は必要的記載事項、7~13は特に定めがあるときに記載する事項である。
1.当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所(1号)
2.宅地の所在、地番その他宅地を特定するために必要な表示又は建物の所在、種類、構造その他建物を特定するために必要な表示(2号)
3.既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項(2号の2.平成30年4月1日施行)
4.代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法(3号)
5.宅地又は建物の引渡しの時期(4号)
6.移転登記の申請の時期(5号)
7.代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに金銭の授受の時期及び目的(6号)
8.契約の解除に関する定めがあるときは、その内容(7号)
9.損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあるときは、その内容(8号)
10.代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置(9号)
11.天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容(10号)
12.宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容(11号)
13.宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容(12号)
※3の1確認すべき事項①
・取引実務で一般に使用されている契約書式か
・当事者の権利義務関係を加重・軽減する条項、依頼者にとって有利・不利な条項があるか、取引特有の事項に関する定め(特約)はあるか、重要な契約条項が欠落していないか
・契約条件が明確か、不明瞭な文言や条項相互間の矛盾はないか
・宅建業法・消費者契約法・住宅品質確保法の規定に違反する条項はないか
・重要事項説明書の内容と矛盾していないか、売渡承諾書・買付証明書の取引条件と売買契約との比較検討
※3の2確認すべき事項②
・当事者双方の属性、売主・買主・仲介業者のいずれの立場に立って案文を検討するのか
・どのような契約目的・動機で売買取引するのか、売買契約に至る経過、売買の目的物とその現況、範囲など
・契約締結に当たって懸念する事項は何か、契約履行に関し、特に不確定な事情があるか、最優先すべき取引条件は何か
・曖昧、不明確な条項の表現の見直し
・契約書案に掲げられていない条項がないか
※8.裁判例
売渡承諾書や買付証明書の交付をもって売買契約の成立を認めた裁判例はないようである。当事者が売買に関して確定的な意思表示の合致を留保していることを基礎づける事実としては、当事者の属性(宅建業者など)、取引物件(事業用物件など)、売渡承諾書や買付証明書の交付時期、交付に至る経過、記載内容、交付後の取引条件の協議・調整の経過事実などが挙げられる。何をもって確定的な意思表示の合致を留保していたと認定しているのかに着目しながら裁判例を参照する。
※9.確認すべき事項
・当事者の属性(事業者、宅建業者、企業の規模など)
・取引の端緒とその後の経過(仲介業者を通じて、いつ頃からどのような取引交渉が進められたか、教受された書類、契約交渉中のメールなど)
・取引物件(居住用建物か事業用物件か)、どのような事業用物件か、売却目的・購入目的は何か
・売主の売却意思または買受希望者の購入意思がいつ頃、どのような方法で仲介業者または取引の相手方に伝えられたか
・買付証明書等が提出された時期、提出した理由と経過、記載内容、名宛人は誰か、有効期限の有無、社内稟議や取締役会の承認が必要であるとの記載の有無
・買付証明書等を交付した段階で、取引条件はどの程度協議・調整されていたか、予定された契約締結・引渡しの年月日はいつか
・買付証明書等を交付した後、どのような取引条件が協議・調整されていたか、重要な取引条件は何か、契約交渉を続けるには障害があったのか
・買付証明書等の有効期限経過後に契約交渉が打ち切られたのか、有効期限経過後にどの程度契約交渉が続けられたのか、その理由と交渉内容
※10.不動産取纏め依頼書
買受希望者が仲介業者宛に提出した不動産取纏め依頼書に「売主の承諾が得られ次第、売買契約の締結を致します」と契約予定日などが記載されていた事案について、「不動産の購入を希望する意向を示したものにすぎない」として売買契約の成立を認めなかった(東京地判平26・12・18)
※11.仮契約書
不動産売買では、時折、仮契約書なるものを締結することがあり、売買契約の成否が争われることがある。改めて正式な売買契約書を締結することから、仮契約書は売買に関する最終的かつ確定的な意思表示の合致とはいえない。
※12
バブル経済期には地価高騰に対処する為、国土利用計画法(略称:国土法)は監視区域内の土地取引を行う際、譲渡人と譲受人に都道府県知事等への事前届出を義務づけ(旧23条)、知事等の不勧告通知前に売買契約を締結することを禁止し、名称を問わず届出前に法的拘束力のある契約(売買予約を含む。)の締結や手付金の授受を禁じた。不勧告通知を受け後に地価が届出価格よりもさらに高騰する状況にあったため、売主が届出価格による売買契約の締結を拒否し、買受希望者が売主(所有者)と締結した協定書が売買契約・売買予約であるとして損害賠償を求める紛争が生じた。ところが、バブル経済が崩壊して地価が著しく下落し始めると、買受希望者が不動産市場や事業採算を理由に契約締結を拒否し、売主が協定書をもって売買契約が成立したと主張し買受希望者に対して提訴する損害賠償請求訴訟が増え始めた。その後、地価下落により監視区域の指定はほとんど廃止されたが、分譲マンション・商業施設などの事業用建物の建物用地の売買では、契約締結に至るまでの交渉に相当期間を要し、多岐にわたる事項を協議する必要があるため、所有者と買受希望者との間で契約交渉が一定の段階に達したときに、買付証明書等の交換にとどまらず協定書(基本協定書、基本合意書など)と題した書面を締結することが多い。協定書においては、①基本的な取引条件を確認するほか、②契約締結までに実施すべき確定測量作業、土壌汚染調査、地質調査などの確認、③開発行為・建築確認手続などの許認可申請手続、予定建築物の設計などに関する協議、④売買契約締結予定の時期などを取り決める。
協議書の文言に照らせば、当事者間で取引物件を売買によって譲渡する旨を約定しているが、近い将来正式な売買契約を締結する時期を定めており、協定書締結前後の事情や経緯をみると、引き続き契約交渉を続けることを予定していることからも、協定書は当事者において最終的な意思表示の合致が留保されている。協定書の締結をもって売買契約が成立したとはいえないし、売買予約にあたるとはいえない(京都地判昭61・2・20金742号25頁、東京地判平5・1・26判時1478号142頁、東京地判平6・1・24判時1517号66頁、東京地判平8・12・26判時1617号99頁、東京地判平10・10・26判時1680号93頁)。ちなみに、宅建業者は、未完成物件(宅地造成・建物建築に関する工事の完了前の物件)について開発許可・建築確認等を受けた後でなければ、自ら当事者として売買等の契約を締結してはならない(法36条、契約締結等の時期の制限)。協定書を締結する当事者の一方または双方が宅建業者である場合、協定書締結をもって売買契約成立を主張することは、宅建業法36条の違反事実を主張することにもなる。
買付証明書等は作成者から名宛人へ一方的に交付する書面であるのに対し、協定書は契約交渉段階において当事者双方が合意に達した基本的な事項や締結予定の売買契約に関する事項をあらかじめ確認した合意文書である。両者は、様式が異なるだけでなく、内容を見ると、一般的に協定書には売買契約書で取り決める事項が相当詳細に盛り込まれている。協定書は、当事者間で「売買契約を締結するまでの準備段階においてなされた合意」と解され、当事者双方は、売買契約書を締結することを約していることから相手方に対し契約締結に向けて誠実に交渉すべき義務を負う(京都地判昭61・2・20、東京地判平8・12・26、東京地判平10・10・26、東京地判平12・5・19)。そのため、当事者の一方が正当な理由なく、協定書に定めた債務を履行しなかったり、契約交渉を打ち切って契約締結を拒否し、相手方が損害を被った場合、信義則上の義務違反による損害賠償責任を負う。
※13.確認すべき事項
・協定書が締結された時期、理由と経過、記載内容、社内稟議や取締役会の承認の有無、協定書締結時点で取引条件はどの程度協議・調整されたか、予定された契約締結・引渡しの年月日はいつか
・協定書締結後、どのような取引条件が協議・調整されたか、特に重要な取引条件は何か、協定書締結後、どのような理由で契約交渉が打ち切られたのか
・重要事項説明書・不動産売買契約書の案文は誰がいつ頃作成し、どのような方法で検討したか、修正箇所はあったか、どのような個所か、修正した理由は何か
・契約交渉期間、協議事項
・不動産売買契約締結に至らなかった時期、理由は何か、損害の有無、損害立証の可否
・売買契約が成立していないことを前提とした言動があったか
※14.売買契約書案の作成
契約交渉過程で取引条件が協議・調整されるのと並行して、仲介業者などが売買契約書案を当事者双方に示し細部の条項の検討に入る。売買契約書案を検討することは、契約締結に向けての具体的な準備であり、売買契約を締結するとの当事者の確定的な意思を根拠づけるものである。しかし、売買契約書の案文を交付した段階ではいまだ売買契約が成立したとはいえない。売買契約の成立を認めなかった裁判例として、東京地判昭63・2・29、大阪地判昭58・7・14、東京地判平20・11・10。
※15.覚書の締結
売買契約の要素は、目的物と代金額が確定していることであり(司法研修所編「問題研究 要件事実」11頁)、これを充足すれば売買契約の成立は認められる。不動産売買契約の成否が争点となった裁判例のほとんどは、売買が諾成・不要式の契約であることを認めつつ、不動産売買の特性や取引慣行などに鑑み、最終的に売買契約書を締結したことをもって確定的な意思表示の合致とする。このような裁判例の趨勢にあって、東京高判平成6・2・23は、不動産売買取引の特性や契約書の位置づけ、取引慣行などに言及せず、目的物と代金額の確定のみをもって売買契約の成立を認定しており、きわめて異例と言って過言ではない。事案を見ると、売主Xの購入予定者Yに対する契約準備段階における信義則違反を理由に損害賠償請求するのが一般的な法律構成であるが、XらはYに対する債務不履行解除による損害賠償のみを請求しており、遺産分割の調停中にXが売買目的物を相続することを条件として目的物と代金額算定のための単価を取り決めた合意に至る経緯に照らして確定的な意思表示の合致があると認定したものと思われる。
※16.売買予約の成否
ⅰ)売渡承諾書の交付(東京地判昭59・12・12)、買付証明書・売渡承諾書の交換(仲介報酬に関して東京地判平22・1・15)、
ⅱ)協定書締結(京都 地判昭61・2・20、東京地判平元・7・28、東京地判平6・1・24)をもって売買予約の成立を主張する事案があるが、いずれも主張が排斥されている。
予約とは、
ⅰ)本契約締結義務を負担させる債権契約である「本来の契約」と、
ⅱ)当事者の一方が一方的意思表示により特定した内容の本契約を成立させることができる予約完結権を有する契約である「予約完結型の予約」とある。“売買予約”を主張する際には、当該契約においてどのような“予約”の取り決めがなされているのかを確認する。買付証明書と売渡承諾書の交換があっても、当事者は、引き続き売買契約(本契約)に向けて取引条件を交渉することを予定し、売買契約書を締結するまでは確定的な意思表示の合致が留保されている。とりわけ事業用物件の売買において開発許可・建築確認を受ける手続きが未了で、代金支払方法・時期等が定まっていない場合などは、当事者の一方または双方に売買契約の予約完結権を付与する条項がないのが一般的である。裁判例を見ると、売買予約の成立を主張しながら、訴訟において予約完結権の行使を主張立証していないものがある(東京地判平22・1・15など)。

投稿者プロフィール
- 弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県で約30年にわたり弁護士として活動しており、特に不動産分野に注力してきた。これまでの不動産関連のご相談は2,200件を超え、550件ものご依頼を受任。豊富な経験と知識で、常に依頼者にとって最良の結果を追求している。特に、不動産の共有関係や借地関係の解決には強い関心を持ち、複雑な問題も粘り強く解決に導く。
最新の投稿
- 2025.08.06不動産トラブルのセカンドオピニオンを検討中の方へ
- 2025.04.18不動産の使用貸借の終了に伴う立退きについて
- 2025.04.15定期借家契約の活用術
- 2025.04.15Q.自身が所有している不動産が競売にかけられているが、どうにかしたいです。