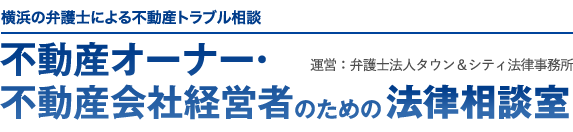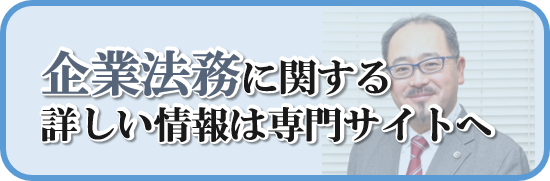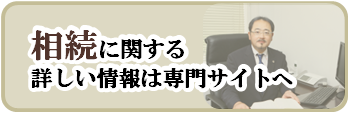不動産業に関する債権
Contents
第1 はじめに
1 不動産業にまつわる債権の重要性
- 不動産業者は、宅地建物取引業者であろうが、土地等を直接取得し建物を建築等開発するデベロッパー的業者であろうが、仲介等の取引や売買・請負等の各契約の対象となるのは、いうまでもなく不動産すなわち土地・建物であり、これらを規制する法律は、講学上は、いわゆる「物権」法の分野であり、「債権」法の分野はそれ程かかわりがないかのように思われがちです。
- しかし、講学上の問題はともかく、実務上は、対象物がどのようなものであっても、その売買や請負はまさに「契約」であり「債権」法の分野です。また、宅地建物取引業者の行う仲介(媒介)も同様に「契約」であり「債権」法の分野です。
そこで、不動産業者が実務を行う上でも、むしろきちんと押さえておくべきは「債権」の分野とも言えることから、「債権」のくくりで、関係する諸問題をまとめてみることにしました。
第2 不動産業者に実務上関係する債権関係の概要
1 不動産業者が賃料請求・明渡し・立退きで弁護士法違反にならないために
特に「債権」に限定した話ではないとも言えますが、特に宅地建物取引業者は、業法上、報酬を得て行える業務が、媒介と代理に限定されています。契約自体は売買も賃貸もあり得るのですが、いずれも、探し出した契約当事者双方の間に立って代金や賃料その他の契約条件等を交渉し契約締結に導く行為(媒介)と、契約当事者の代理人として上記諸条件を本人(=契約当事者)に代わって交渉して契約を締結する行為(代理)のみを、業者として、すなわち報酬を得て行えることとされています。
ところが、一口に「媒介」や「代理」と言っても、現実の実務では、契約書や重要事項説明書等の各書面を作成するだけでなく、契約当事者をはじめ利害関係人の様々な利害を調整して売買等契約の締結に導かなければなりません。むしろ、このような調整が全くなしで契約を締結できる場合の方が実務上は少ないかもしれません。
そこで、宅地建物取引業者は、媒介や代理の各業務の内容の一環として、上記利害関係の調整まで広く行い、極力契約の締結に至ることを目指しますが、かたや、弁護士法72条では、弁護士以外が報酬を得ることを目的として「業務」として法律事務等を行うことを、刑事罰まで設けて禁止しています。そのため、上記のとおり、宅地建物取引業者が契約の締結を目指して行う利害関係の調整業務をどこまで行うことができるのか、逆を言えば、どこまで踏み込むと弁護士法違反になるのか、が問題となります。
判断する際のポイントを以下で述べます。
- 報酬を得るのか?…報酬を得ないのであれば、上記弁護士法には触れません。但し、株式会社等の「商人」がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求できることが商法上定められています(同法512条)。そのため、例えば、売買契約成立後に同契約の解釈や履行に関して紛争が生じ、あるいは契約の不備な点の是正その他相手方の債務の履行を確保するための適切な措置を宅建業者が買主等からその解決のため相手方と折衝すること等を依頼され交渉し、妥結させたりした場合(=これらの業務は「契約締結後」であるため、直接宅建業者の業務の対象になる訳ではないこと、しかし同業務の「付随的業務」として、一定の範囲内では行うことが許されていることは余り争いがありません)に、この商人の商法上の報酬請求権と弁護士法72条との関係が問題となります。
この点判例は、弁護士法72条には違反せず、商法上の付随的商行為(同法503条)に該たるとして、同法512条の報酬請求を認めたものがあります(最判昭和50.4.4民集29巻4号317頁、判時779号105号、判タ324号195頁(裁判例1)、大阪高判昭和47.3.24、民集29巻4号338頁、判時673号79頁(裁判例2))。
なお、弁護士法72条に触れない理由としては、上記両裁判例ともに、次の「業務」性がないことをその根拠としています。
- 「業務」として行うのか?…「反復・継続」の必要性
弁護士法72条で禁止されているのは、あくまでも「業務」として行う場合です。この場合の「業務」とは客観的に「反復・継続」していること、または客観的には「反復・継続」してはいなくても、その意思がある、すなわち主観的には「反復・継続」していることを指します。上記裁判例1及び裁判例2の両事案とも、報酬請求をした宅建業者が行った付随的業務は、いずれもいわばイレギュラーな態様での偶発的な、いわば一回きりのものであったという色彩が強いものでした。
仮にこのようなイレギュラーなものではなく日常的に発生する業務の場合には、仮に宅建業者の「付随的業務」ではあっても、次の(3)で述べる「争訟性」が備わるのであれば、そのような業務を行って報酬請求することは弁護士法72条違反に問われる可能性は非常に高くなるものと考えられるため注意が必要です。
- 弁護士法で規制する「法律事務」に該たるのか?…「争訟性」の存在
契約当事者その他の利害関係人の間が利害が相反し、必ずしも訴訟や調停にまで至らない純粋な交渉の場面でも「紛争」になっているないしはなるおそれがある場合には広く「争訟性」が認められて、弁護士以外がこれらの解決や解決とまではいえない交渉ないし締結行為すらも「業務」とすれば弁護士法72条違反に問われる可能性が高いです。
この点、同条の「その他一般の法律事件」といえるためには「争いや疑義が具体化しまたは顕在化したものであることが必要である」という解釈を展開した主張に対し「かかる解釈では狭きに失すると思われる」と判断し、その理由として、例えば上記「その他一般の法律事件」に「督促手続」が入ることは異論がないだろうが、同手続は、必ずしも上記「争いや疑義が具体化しまたは顕在化したものである」ではなく、その多くは、単に、まずは「債務名義」を取得するために申し立てられていることを挙げています(東京高判平成21.10.21東高判時刑事60巻1~12号172頁、判タ1332号282頁、LLI/DB判例秘書(裁判例3。なお、この事案の東京地裁判決が裁判例4であり、同じく最高裁判決が裁判例5である))。いずれにせよ、本事案では、弁護士資格を有しない者が、ビルの各室の賃借人との間で交渉を行い賃貸借契約期間中の同契約を合意解除した上で各室を明け渡させる等の業務を受託し、これを業として行った行為について弁護士法72条違反の罪が成立するとされました。
ちなみに、上記各裁判例のうち、最高裁は「賃貸借期間中で、(賃借人らは)現にそれぞれの業務を行っており、立ち退く意向を有していなかった賃借人らに対し、専ら賃貸人側の都合で、同契約の合意解除と明渡しの実現を図るべく交渉するというものであって、立退き合意の成否、立退きの時期、立退き料の額を巡って交渉において解決しなければならない法的紛議が生じることがほぼ不可避である案件にかかるものであったことは明らかであり、弁護士法72条にいう『その他一般の法律事件』に関するものであったというべきである」という点を同条違反の根拠にしていますが、同条における上記要件(=「その他一般の法律事件」)の解釈にあたって参考になるものと思われます。
また、上記事案では当該賃貸ビルの所有権が被告人(会社)らに移転したように仮装したり、賃借人らに種々の不安や不快感を与えるような振る舞いもしながら同ビルの賃借人らと立退き交渉等を行っていたような比較的悪質な事案でした。上記裁判例のうち地裁判決は、上記仮装をしたことをもって、被告人らの弁護士法72条違反を基礎付ける事実の認識(=同罪の故意)の有無について「有」という認定の根拠にしています(←単なる「代理人」だと賃借人らは真の賃貸人との交渉のみを望みかねないから所有者兼賃貸人を装った、すなわち本件業務が代理や和解に準じる性質のものだと十分に認識していたものと認定したことから)。
なお、上記事案のように弁護士法72条違反となれば、その報酬請求は強行法規に反するものとして、少なくとも公序良俗(民法90条)違反として認められない(=仮に受領した場合には不当利得や損害賠償として返還義務を負う)ことは当然です。その他、弁護士法72条違反が問題となった裁判例として東京高判昭和43.12.13東高判時刑事19巻12号253頁、判タ232号174頁、判時574号81頁(裁判例7)、大阪高判平成28.10.4判タ1434号101頁判時2330号33頁(裁判例8)も参照。
- 仮に弁護士法には違反しないとして、宅地建物取引業法には違反しないのか?…報酬の上限との関係が問題に。
上記の弁護士法72条に違反しないとしても、宅地建物取引業法46条1項及びこれに基づく国土交通大臣告示(=売買等代金の3%+6万円)で定められている報酬の上限を超えていれば、それが認められない(=仮に受領した場合には不当利得や損害として返還や賠償義務を負う)ことは当然です。
ちなみに、弁護士法72条違反を理由に公序良俗違反として認められなかった報酬請求は、その金額も、到底上記宅建業法の上限内に収まるものなどではなかった(→「暴利行為」として上記公序良俗で無効との判断の根拠とされています)のですが、仮にこの上限内だったのであれば、「コンサルティング契約」との名目であっても実質は「媒介契約」という認定をしたので、この金額の限りでは認容された可能性は十分にあったものと思われる裁判例も見受けられます(東京地判平成25.9.3、LLI/DB 判例秘書(裁判例6))。
- 結局、報酬は受領できるのか?…弁護士法72条違反→報酬請求は無理(公序良俗違反等で棄却)→仮に宅建業法上の上限(代金の3%+6万円)内ならば認容される可能性はあります(上記裁判例6)。
- 受領できるとすればいくら受領できるのか?…基本は上記宅建業法上の上限(代金の3%+6万円)⇔上述した「付随的業務」の場合には、内容からして上記宅建業法の上限よりは少額であるべきとして、任意の金額(上記宅建業法上の上限から4分の1程度を減額した金額)のみを認容した事例もあります(裁判例2)。
☆では、弁護士法72条に違反しないためには、具体的にはどうすればよいのか?
① まず、宅建業者として、出来るだけ余計なことは受任しないし、業務としても 行わない→契約締結後は既述のとおり、「付随的商行為」→報酬も、業務内容に 応じた相応の分しか受領できないし…。
② 受任するなら無料(タダ)で!あるいは今回の1回のみで!!→弁護士法72条の「報酬を得る目的」とか「業務として」に該当しないで済む。
③ それでも受任するなら、宅建業法上の上限の範囲でのみ報酬を受領する→オーバーしたら即宅建業法違反であるし、宅建業者の業務範囲を超えているとの認定になるなら弁護士法72条違反の責任も問われる。
④ それでもどうしても受任したいということであれば、係争対象物(物件)を取得してしまう→取得により所有者となり、売主や賃貸人という「当事者」として、明渡し等を求める交渉等をしても何ら問題はない。→むしろ、利幅も報酬もより大きくなる!!
2 債権回収の類型(通常訴訟・調停・支払督促・少額訴訟など)
…得られる「債務名義」により長所と短所があります。…債権の内容は、賃料等請求権や売買代金請求権等の金銭債権と、土地・建物の明渡し請求権の2つに大きく分かれる。
- 通常訴訟 長所:内容及び金額とも上限なし。短所:時間・手間・費用が多くなりがち。
- 即決和解(起訴前和解) 長所:明渡し請求についても債務名義になる。短所:債務者との事前の合意がなければ、そもそも申し立てられない。
- 調停 長所:内容及び金額とも上限なし。親族間等においては活用の余地あり。短所:当事者間での合意が整わなければ結局、訴訟等へ移行せざるを得ない。
- 支払督促 長所:内容及び金額とも上限なし。かつ、債務者側から異議が出されなければ極めて早期に債務名義の取得が可能。短所:書面等の証拠(ほぼ書証に限定)が揃っていることが申立てのための要件。債務者側から異議が提出されれば通常訴訟に移行してしまうので、結局上記(1)と同じに。
- 少額訴訟 長所:1~3回程の期日で結審となるため、解決までが比較的短期間。かつ証拠が督促手続と違って書証のみに必ずしも限らない。短所:訴額に上限(60万円)あり。
- 公正証書の作成 長所:公証人役場で、執行認諾文言入りの公正証書を作成すれば、金銭債権については債務名義になる。短所:債務者の合意及び公証人等への協力が必要。
3 民法改正を踏まえた債権の時効期間の変更等について
- 債権の消滅時効の通則の改正
- 改正前民法における概要
A 原則:権利を行使できる時から10年
B 例外1:1年以下の期間で定期的に支払われる定期給付債権(家賃・地代・マンションの管理費等)=同5年(改正前民法169条)←支払いが多数回&請求書・領収書等の資料も長期間保存されないことから。
C 例外2:債権者の職業や債権の発生原因により1年~3年(例:飲食代=1年、弁護士報酬=2年、医師の診療報酬=3年)
D 例外3:商行為により生じた債権=同5年←商人は多数取引&資料も長期間保存されないことから。
⇒これら以外にも個別に消滅時効期間の定めがあったりもしたこと等から、時効期間の統一化・単純化を図るべきとの指摘が!
- 改正法による通則
ア 「権利を行使できる時から」10年(客観的起算点)
イ 権利を行使できることを「知った時から」5年(主観的起算点)
⇒いずれか早く到来した期間の終期で消滅時効は完成する。
Cf.上記イの主観的起算点からの「5年」という期間は、改正前の商事時効(商法522条)や会計法の時効期間(会計法30条)とも適合することから。→上記商法522条は削除され、債権の消滅時効は改正民法(166条)により統一された(改正民法の施行に伴う整備法)。
Cf.人の生命や身体が侵害されたことによって生じる損害賠償請求権=上記アの客観的起算点は権利を行使できる時から「20年」に伸長された(改正法167条)。←債権者(=被害者)に深刻な被害が生じ、日常生活を送ることすら困難な状況も考えられ債権者に時効完成を阻止するための措置を要求することができない場合も多い反面、債権の性質上、他の債権よりもむしろ権利行使の機会を確保する必要性も高いものと考えられたため。
- 協議による時効の完成猶予
A 従来の時効の中断事由a請求(=訴訟等の提起)(改正後は時効の「完成猶予」事由に)
b差押・仮差押・仮処分(改正後はいずれも同上←但し、仮差押と仮処分については、手続開始に債務名義は不要であることやその後に本案訴訟の提起が予定されていることから。→仮差押・仮処分の取下げで終了した場合=時効の進行を止めるためには6か月以内の提訴等が必要)
c債務の承認(改正後は時効の「更新」事由に)
d催告(但し、6か月内の提訴等が必要)(改正後は時効の「完成猶予」事由に)
B 改正法により新設された協議による時効の完成「猶予」
債権者と債務者が、債権の有無や支払条件等について「協議することを」「書面等で」合意すれば、合意から1年間、またはその合意で定められた1年未満の協議期間中は、時効期間は終了しないという新しい制度が創設された。
a 「合意」は「協議すること」についてであり、協議の結果として債権の有無や支払方法についての合意でなくてもよい。
b 「合意」は、必ずしも書面でなくてもよく、Eメール等の電磁的記録であってもよい。
c 協議の合意がなされると、次のアないしウの期間の最も早い時まで時効期間は満了しなくなる(改正法151条)。
ア 協議の合意がされた時から1年間
イ 協議の合意において協議期間が定められたときは、その期間。但し1年未満であることが必要。
ウ 協議期間中であっても、一方から他方に協議続行を拒絶する通知が書面等でなされたときは、その通知から6か月。
d 上記アないしウにより時効の完成が猶予されている間に再度協議の合意が書面等でなされれば、同じように時効期間は満了しない。
但し、協議の合意を繰り返しても、本来ならば時効期間が満了する時点(例えば家賃であれば支払期限から5年経過した時点)から、合計で5年間しか、時効の完成は猶予されない。
- 改正民法施行前に締結された賃貸借契約は、施行(令和2(2020)年4月1日予定)後、旧法と新法のどちらが適用されるのか?
結論:改正前の民法(旧法)が適用される。
理由:改正民法施行前に締結された契約等に旧法と新法のどちらが適用されるかは、改正民法の附則に定められている。
A 改正民法の附則:以下については、改正民法施行後も、改正前の民法が適用される。
a 施行前に発せられた解除等の意思表示の到達(附則6条2項)
b 施行前に生じた賃料等の消滅時効期間(附則10条4項)
c 施行前に生じた利息や遅延損害金の法定利率(附則15条1項、17条3項)cf.改正後は3%(改正民法404条2項)&3年毎に短期(=1年未満)貸付の平均金利の変動を参照して1%刻みで利率が変動することに(同条3項~5項)。
Cf.消費者契約法上は、消費者の金銭の支払が遅れた場合の遅延損害金は年14.6%を超える違約金を定めたときは、超える部分は無効(消費者契約法9条2号)
d 施行前に締結された契約の解除(附則32条)
e 施行前に締結された賃貸借契約や売買契約(附則34条1項)
B 施行前に締結された定型約款(=定型取引(ある特定の者(業者)が不特定多数の者を相手方として行う取引で、その内容の全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ)において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者(業者)により準備された条項の総体をいう(改正民法548条の2第1項)):施行後は改正民法の適用を受けるのが原則(附則33条)cf.大手不動産会社が多数の顧客相手に使用している「売買契約書」・「仲介契約書」は、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的」とは言えない→この「定型取引」には該当しないと解釈されるのが一般。
Cf.定型約款に関する改正民法におけるルールの概要
a 定型約款に該当する場合、ア 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、またはイ 定型約款を準備した者が予めその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときには、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる(改正民法548条の2第1項)。
但し、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして民法1条2項に規定する基本原則(いわゆる「信義則」)に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなされる(改正民法548条の2第2項)。
b 定型約款を使用する場合、相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない(改正民法548条の3第1項)。
c 定型約款を使用する場合、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意することなく契約の内容を変更することができる場合がある(改正民法548条の4第1項)。
- 賃貸借契約における消滅時効等の改正点
- 家賃の消滅時効期間
A 改正前:家賃を請求できる時から5年間(改正前民法169条)
B 改正後:上述のとおり、a権利を行使できることを債権者が知った時から5年間(主観的起算点=改正民法166条1項1号)b債権者が権利を行使できることの知・不知に関係なく権利を行使できる時から10年間(客観的起算点=同項2号)→cf.上記bは、例えば賃貸人が死亡して相続が発生し、相続人が相続財産に賃貸不動産があることを知らなかったといった特殊な事情がある場合くらいしか適用は考えられない。
- 用法違反による損害賠償請求権の消滅時効
A 改正前:不都合あり=用法違反で賃借人が賃貸物件に損害を与えた時から10年間または賃貸人が賃貸物件の返還を受けてから1年間のどちらか早い方で消滅時効期間が完成するとされていた。=例えば賃貸借契約が長期間継続し、例えば新居として入居し家具等を搬入する際に壁に大きな傷を付けたがその後12年間に亘り賃借後、12年後に契約が終了し賃貸人に物件を明渡したケース等→明渡の時点で既に損害賠償請求権の消滅時効が完成し、明渡の時点で内覧して初めて傷の存在が判った賃貸人が用法違反(債務不履行責任)による損害賠償請求をしようとしてもできない、という問題があった。
B 改正後:賃借人から明渡を受けてから1年間は賃貸人の損害賠償請求権は時効消滅しないとするルールを新設(改正法622条、600条)→どんなに長期の賃貸借契約でも、明渡の際に発見した用法違反による損害賠償請求権は、明渡から1年間は時効消滅しないことに。
C 不法行為に基づく損害賠償請求との関係について
損害賠償請求権は、被害者(賃貸人)が、加害者及び損害の発生を知った時から3年間、不法行為の時から20年間のどちらか早い方で消滅時効完成(民法724条)。→上記例から言えば、傷を付けたのが20年以内であるなら、賃貸人が明渡を受けて初めて傷の存在を知ったのであれば、知った時から3年間は損害賠償請求ができる。但し、不法行為責任の追及では、賃借人の故意・過失等を賃貸人側が主張・立証しなければならない⇔契約(債務不履行)責任の追及では、賃借人側が、賃借人に故意・過失がなかったことを主張・立証しなければならない。結論:賃貸人は、遅くとも明渡を受けてから1年間の間には(上記改正法)、損害賠償請求(この場合には、通常は主張・立証責任の軽い契約責任の追及だろう)をしておくべき!!
- 売買契約における消滅時効等の改正点
- 買主の権利行使期間
A 改正前:瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求等について、瑕疵を知ってから1年以内に請求権を行使するという権利行使の期間制限が定められていた(旧民法566条3項等)。→この請求権は、「売主に対し、具体的に瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求をすることを表明し、請求する損害額の算定の根拠を示す」必要があるものとされていた(最判平成4.10.20民集46巻7号1129頁)。
また、上記期間制限とは別に、旧法570条による損害賠償請求権について、物を引き渡した時を起算点とする10年の消滅時効(同法167条1項)に服するとしていた(最判平成13.11.27民集55巻6号1311頁)
B 改正後:「種類または品質」に関する契約不適合を認識したにもかかわらず、売主に対して1年間その旨の「通知」をしない間に、買主は失権することと定めれた(改正法566条)。→契約不適合についての損害賠償請求まですることは求められず、通知をすることのみで足りるものとされた。←仮に詳細な通知を要求すれば、迅速な通知の妨げとなり、かつ買主に過大な負担を課すことになるから。
Cf.「通知」=商法526条2項の「通知」と同様に、契約内容の不適合について、その大体の範囲を明らかにすれば足り、損害賠償の額の算定根拠まで示す必要はないとされている(大判大正11.4.1大民集1巻155頁、東京地判平成14.9.27判例秘書掲載L05732039、法制審議会民法〔債権関係〕部会 部会資料75A・22~25頁、39頁以下)。
a 合板の売買に関し、不良製品の正確な枚数を明示していなくても同項の「通知」として欠けるところはないと判断された事案(東京地判昭和56.8.19判時1035号123頁)
b ゴルフネットの売買に関し、買主が売主に対し品質に多少問題があるようである旨の話をしたことが、同項の「通知」としては不十分であると判断された事案(東京地判昭和54.9.25判時959号119頁)
Cf.「認識」=買主が売主に対し担保責任を追及し得る程度に確実な事実関係を認識したことを要するとする判例(最判平成13.2.22判時1745号85頁)の解釈が参考になると説明されている(法制審議会民法〔債権関係〕部会 部会資料75A・39頁)
C 売主が、売買目的物の引渡時に契約不適合があることを知り、または重過失で知らなかったときは、この通知期間制限が適用されない(改正法566条但書)。
D 「種類または品質」以外の「目的物の数量」「権利移転」の契約不適合は対象とならない。Cf.(改正民法の)上述の債権の消滅時効(5年または10年)は、「目的物の数量」「権利移転」の契約不適合の場合でも対象となる=改正民法566条の対象とはならない。
- 改正宅建業法40条(担保責任についての特約の制限)…「数量」が除かれているのは、既に実務的には広く普及しているいわゆる「公簿売買」を除くため←「契約の内容に不適合」と「数量」(不足)の問題も含めて担保責任の規定を改正してしまった故の特別法である業法からのフォローに他ならない。
- (建築等)請負契約における消滅時効等の改正点
- 注文者の権利行使期間:改正民法637条=売買の規定とほぼ同様。
- 請負人の報酬請求権の消滅時効:旧法170条2号の「3年」は廃止→上述の5年、10年が適用される。→時効期間を「短縮させる」合意をすることも一案(cf.時効期間を延長する特約は無効(民法146条))。但し、公序良俗に反する無効な特約とならないようには要注意!
- (設計監理等)委任契約における消滅時効等の改正点
- 委任者の権利行使期間:消滅時効の起算点を「建築建物の」完成引渡時とする合意等することを検討(cf.四会連合設計・監理契約書類の約款23条2項)←この合意がなければ「設計図書等の設計成果物の」引渡時から起算されてしまう不都合がある!
- 受任者の報酬請求権の消滅時効:上述の請負人の報酬請求権とほぼ同様。
投稿者プロフィール
-
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を残している。
最新の投稿
- 2024.07.25借地の更新拒絶が認められる正当事由とは?立退料の設定金額について弁護士が解説
- 2024.07.25借地権の遺産分割の適切な方法とは?
- 2024.07.25借地の共有持分の譲渡におけるトラブルとは?
- 2024.07.25借地への抵当権設定においてよくあるトラブルとは?