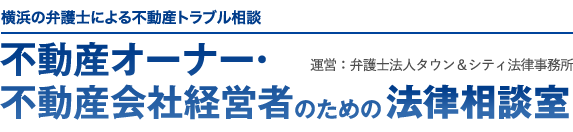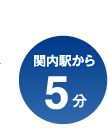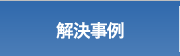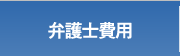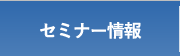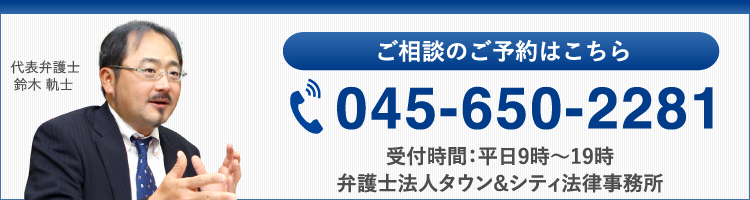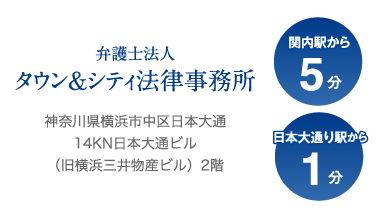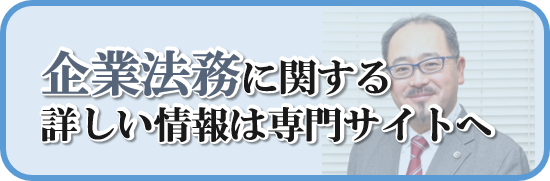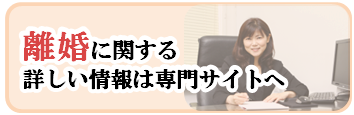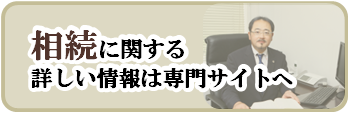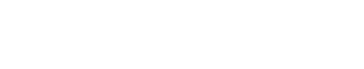共有物分割におけるトラブルを弁護士に相談するなら弁護士法人タウン&シティ法律事務所まで
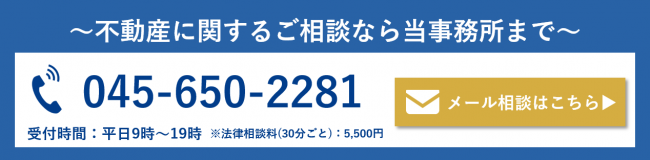
Contents
共有不動産における、よくあるトラブル
不動産を共有することがあっても、共有関係を維持し続けることが不都合な場合もあります。例えば、当事務所では、以下のようなケースが、共有者間で話し合いがまとまらずトラブルとなってしまっているというご相談を多く受けます。
• そもそも誰が共有するのか?
• 共有不動産の使用は誰がどのようにするのか?
• 共有している建物を修繕するのか、するとして、どのような規模の修繕(工事)をするのか?
• 共有物の維持管理にかかる費用(例:固定資産税等の税金やマンション棟の管理費)は誰が(いくら、ないし)どのような割合で負担するのか?
• 利用しなくなった共有不動産を保持し続けて、第三者に賃貸等するのか、それとも売却処分するか?
• 共有物を売却するとしても、そもそも誰に対しいくらで売却するのか?
• 共有物を売却して得た代金は、どのように分配するのか?要した経費はどのように分担するのか?
• 共有者の連絡先がそもそもわからない、あるいは連絡を無視されているが、どうしたらよいか?
共有の背景には先代からの相続問題等が絡んでいることも多く、感情的な対立がある場合も多いため、当事者間での話し合いでの解決が困難なケースも少なくありません。共有者同士の人間関係が疎遠であるために、コミュニケーションが取りづらいという場合もあります。
当事務所は、不動産に関係する法律問題を数多く扱っており、共有物分割問題の解決実績も多いです。共有不動産を売却する際の税務問題や登記手続きについても、提携司法書士や税理士と協力して対応可能です。
さらに、数多くの不動産問題を解決する過程で不動産業者からの協力も得やすいため、不動産を売却する場合でも、売却手続きの最初から最後までお手伝いさせて頂けます。
共有物分割請求とは
民法上、共有者は原則としていつでも共有物の分割を請求することができ、共有者間で協議が調わない時は共有物の分割を裁判所に請求することが出来ます。
主な分割方法としては、
①現物分割
②代償分割
③換価分割
の3種類があり、場合によりこの3つの類型を組み合わせることもあります。
①現物分割は、共有物を物理的に2つ以上に分けるものです。②代償分割は共有者の1人が共有物を取得し他の共有者が取得した共有者から代償金を取得するというものです。③換価分割は共有不動産を売却して代金を持分割合に応じて分配するというものです。
①の現物分割をとるのが原則とされています。しかし、
(a)そもそも、共有物の現物を分割することができないとき、又は、
(b)分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるとき
は採用できません。
例えば、建物の現物分割や、土地上に建物が目一杯建っているケースでの土地、共有不動産が2つ以上あるような場合は困難な場合が多いことになります(上記(a))。また、現物分割することにより、共有物全体の価値から2,3割程度の価値の下落が見込まれる場合には、「価値を著しく減少させるおそれ」があると評価される結果、分割が困難となるケースがあります(上記(b))。
結局、現物分割が殆ど行われない理由についてですが、特に都市部においては土地や建物の権利関係が入り組んでいるため、そのどちらも現物での分割は物理的にもなかなか難しいということが挙げられています。すると特に都市部においては、共有者のうち誰かが共有物を取得する②の代償分割か、共有不動産を売却して代金を分配する③の換価分割のいずれかであることが殆どということになります。
代償分割とは、持分以上の現物を取得した共有者が、他の共有者に対して代償金を支払うことによって、共有関係の解消を図る方法をいいます。このうち、共有不動産を共有者のうち1人だけの単独所有にした上で、単独所有者から他の共有者に対し「代償金」を支払うことによって共有関係の解消を図る方法を「全面的価格賠償」といいます。
全面的価格賠償の方法を採るためには、
(ⅰ)共有者のうち特定の共有者1人が取得する相当な理由があること
(ⅱ)適正な買取価格の提示がなされること
(ⅲ)取得者に支払能力があること
が(主張)立証された場合に初めて認められます(最高裁平成8年10月31日判決)。
なお、②の代償分割を行う場合には、不動産の評価が問題となります。評価については当事者間の「評価合意」を行う事が多いですし実務上は費用・時間・手間共にこれが最も節約できることから、まずはこの合意を目指します。しかし、評価合意が成立しない場合には裁判所が選任する不動産鑑定士の鑑定評価によることになります。用いられることが多い評価合意についてや、共有物分割請求訴訟における不動産鑑定については、また個別に説明させて頂きます。
③の換価分割とは、共有不動産を売却し、その代金を持分割合に応じて分割する方法のことです。換価方法としては、
(a)共有者全員の合意による売却(任意売却)と、
(b)裁判による競売による方法(形式的競売)
があります。裁判による競売の場合、他の共有者の同意なく売却(強制的な換価)をすることができます。しかし、競売を申立てる要件として「判決」を得なければなりません。よって、上記(a)の任意売却による方法と比べると費用・時間・手間を要することが多いです。
なお、裁判による競売の場合、売却金額(入札ないし応札金額)が時価と比べて2、3割程度低くなってしまうこともあります。昔の「最低売却価格」制度時代から比べると「売却基準価格」制度に代わった現在は、昔ほど極端に安価となるケースは少なくなりましたが、(結局は個別事情次第ですが)最大の問題は、「入札」という制度を使うために価額を任意には決められず予測ができない場合があるということです。
また共有物分割請求は金銭問題から生じることが多く、さらに共有物分割請求によって金銭問題が生じることもあります。このような共有物分割請求の金銭問題についても、また個別に説明させて頂きます。
以下では共有物分割請求手続の流れについて説明します。
(1)共有物分割協議
共有物分割請求をするには、最初に共有物分割「協議」をする必要があります。中にはさんざん話し合いをしてもらちがあかなかったから、すぐに訴訟、競売を希望するという方もおられます。
ですが、法律では「共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求できる」と規定されています。訴訟提起の要件として「共有者間に協議が調わない」というのがあるため、仮に共有物分割協議をせずに訴訟提起をすると、訴訟(提起の)要件がないから共有物分割請求訴訟は認められない(却下されるべき)などと相手方から言われるおそれがあります。
このように、訴訟(提起)の要件を備えるためにも、最初に共有物分割協議をする必要があります。
あと、実務上も「協議」で進められるなら、費用・時間・手間を最も節約できるであろうことは上記の「評価合意」についてと同様です。法律では共有物分割協議の方法についての規定はありません。実際に会って話し合いをする方法でも電話や手紙・電子メールでやり取りをする方法でも構いません。
しかし、仮に訴訟になったときに、相手方から「共有者間に協議が調わない」という要件を備えてないから共有物分割請求訴訟はできないはずだ、などと言いがかりをつけられないためにも、最初に配達証明付きの内容証明郵便で共有物分割協議の申入をした事実を書面より証拠として残すべきです。これは共有者全員に送付する必要があります。
そのような方法をとれば、共有物分割協議の申入をしたことについて配達証明による日付入りの書面で証明することができますので一定期間経過しても共有物分割協議が成立しておらず、「共有者間に協議が調わない」という訴訟要件を備えたと証明することができ、相手方から無用の反論を受けずにすみます。
かたくなに適正価格での持分売買や共有不動産共同売却を拒絶していた人でも、弁護士が代理人として共有物分割協議の申し入れをしただけで、持分売買や共有不動産共同売却に応じてもらえることも少なくありません。
共有物分割協議の申入をして、相手から何の応答もなかった場合(通常は期限付での回答を求めます)、話し合いをしたが話し合いがまとまらなかった場合は「共有者間に協議が調わない」ことになるので共有物分割請求訴訟を起こすことができます。
(2)共有物分割請求訴訟
共有物分割協議が調わなければ、共有物分割請求訴訟を提起することができます。要件は次のA~Cです。
A(当事者)共有者全員を当事者にする必要があります(固有必要的共同訴訟)。
B(裁判管轄)裁判所は被告となる相手方のいずれかの住所地又は不動産所在地を管轄する地方裁判所に提起することになります。不動産を対象とする訴訟ですので簡易裁判所に訴訟提起することはできません。
C(請求の趣旨)請求の趣旨で求める判決の内容を記載します。競売を命じる判決を求めるのか、代償分割の判決を求めるのか、現物分割を求めるのかのいずれかです。
通常の訴訟ですと原告が求めた請求の当否を判断すればよいのですが、共有物分割請求訴訟の場合は共有物の分け方を決める裁判ですので、そもそも共有物分割請求権がない場合や共有物分割請求権があってもこれを行使するのが権利濫用にあたる場合以外は、何らかの方法で裁判所が共有物分割の方法を決めざるを得ません。よって当事者が請求したのとは異なる内容の分割方法を命じる判決を出すこともできます。(形式的形成訴訟)
弁護士が共有物分割請求訴訟を提起した場合、判決になると(形式)競売を命じる判決が出される事案では、ほとんどのケースで初めから競売を命じる判決を求めていますので、相手方に状況を理解してもらうことによって、仮に訴訟提起をした場合で、かつ競売の場合でも判決になるとは限らず、むしろ和解で決着(=合意により競売に付する)することが多いです。共有物分割請求訴訟についてもまた、個別に説明させて頂きます。
▼共有物分割請求に関する記事はこちら▼
(3)共有物分割のための競売
共有物分割協議をしても、共有物分割請求訴訟を提起しても、共有不動産の分け方が決まらない場合に競売を命じる判決が出される(または和解が成立する)ことがあります。
競売を命じる判決が出された場合に、この判決正本を添付した上で競売申立をすることができます。これは共有不動産全体に対する競売になります。このように仮に共有者(持分権)者のうちの一人が共有不動産の処分に反対していても、競売を命じる判決(または成立した和解)に基づいて競売手続を行えば、共有持分権を失うことになります。 競売手続についてもまた、個別に説明させて頂きます。
当事務所にご相談いただいてから解決までの流れ
ご相談
弁護士により、事案を多角的に分析した上、個別・具体的なアドバイスをさせて頂きます。
方針の検討
共有物の場所や形状、使用様態、共有に至る背景事情、当事者の関係や各自の性格、資力の差等の外的事情も分析した上で、適切、妥当な分割方法を検討し、公平な解決策を追究します。
交渉
ご依頼者が誰か決まり次第、相手方と交渉を開始し、共有者全員の共同利益も模索しながら、ご依頼者様の利益の最大化を図ります。また、同時に時間的にも早期かつ円滑に、また、できるだけ感情的な「しこり」を残さないためにも、円滑な(話し合いでの)解決を試みます。
訴訟
交渉での協議が整わなかったり、合意が成立しない場合にはやむを得ず訴訟へ移行します。ただし、訴訟提起の後であっても相手方との交渉を続けることが可能な場合も多く、柔軟な解決のために和解を目指し、その結果、和解が成立するケースもあります。
共有物の分割
交渉又は訴訟により定まった分割方法(①不動産を現実に分割する(現物分割)、②共有者間にて、いわば持分を売買する(代償分割)、③第三者に売却し代金を分ける(換価分割)等)に従い、登記や代金の授受等の手続きが完了するまで弁護士が対応いたします。不動産を第三者に売却する場合には、共有者全員の利益のために極力、高額で売却できるよう、不動産業者と協力します。
当事務所の解決事例
解決事例①
横浜市近郊に所在する共有不動産(マンション)を第三者に売却し、その売買代金を共有者間で分配した事案です。この事案では、売却の方法について不動産業者と密に連携をとり、不動産広告サイト(レインズ)等にも掲載しましたが、特に売却に向けての活動時期(4月または9月からの利用を可能とするように活動)を工夫しました。その結果、より良い条件の購入者を見付けることが出来、当初の不動産査定を大幅に上回る金額で売却することができました。
解決事例②
横浜市内に所在する共有の居住物件2軒(一戸建とマンション)を、全面的価格賠償と持分の交換を混ぜた方法により、依頼者が相手方に対し賠償金を支払う形にはなりましたが、当該物件のうち高額の方を依頼者が、他方の物件を相手方がそれぞれ取得し、各自単独所有とすることで解決した事案です。本件は、ご本人同士の交渉は、感情的な対立から到底不可能だったところ、当事務所が受任し一旦は示談交渉を経ましたがやはり無理だったため、訴訟提起をして、裁判上の和解をすることで比較的早期に解決しました。また、本件2物件中の各自の持分を交換することで、依頼者が相手方に支払う賠償金の金額を低く抑えることにも成功しました。
当事務所の弁護士費用
相談料金:5,500円~11,000円(30分) ※1 ※2
※1 ただし事案によっては追加料金が発生する場合もございます。事前にお問合せください。
※2 実費は別途発生致します。
【共有物分割請求】
交渉の場合
| 着手金 | 22万円 |
| 報酬金 | 共有物分割によって得た金額等の5.5%~16.5% |
訴訟提起の場合
| 着手金 | 33万円 |
| 報酬金 | 共有物分割によって得た金額等の5.5%~16.5% |
※ 交渉から訴訟に移行した場合は33万円と22万円の差額11万円をいただくことで対応させていただきます。
共有不動産の売却・共有物分割請求に強い弁護士の法律相談
不動産を複数人で共有している場合、個々人の使用収益・処分が法律上制限されてしまう場合があります。そのため、個々の共有者において満足な利用ができず、不便を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。この場合、共有者間において共有関係の解消を目指していくことになります。しかし、共有関係の解消は予期せぬ紛争となり得る可能性がありますので、専門家である弁護士等に相談・依頼する必要があります。
当事務所では共有不動産に関するご相談を数多くいただいており、豊富な解決事例を有しています。お持ちの共有不動産をいかによりよく処分するか、法律と実務に精通した弁護士がご提案いたします。
お悩みの方はまずは当事務所までご相談ください。
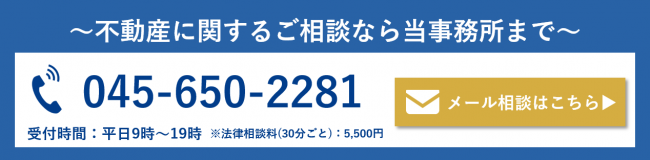
関連ページ
◆遺産共有とは
◆共有物分割請求の全面的価格賠償の要件
◆共有物分割請求とは
◆共有物分割請求の「濫用」
◆担保権が設定されている不動産の共有分割請求
◆夫婦間の共有不動産の共有物分割請求
◆共有物件の効果的な処分方法
◆建物の共有敷地のみの現金化
当事務所の共有不動産に関する解決事例はこちら
◆持分買取業者の共有物分割請求訴訟における居住者による持分買取和解事例
◆高齢の依頼者によるリバースモーゲージ活用での共有持分買取事例
投稿者プロフィール
- 弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県で約30年にわたり弁護士として活動しており、特に不動産分野に注力してきた。これまでの不動産関連のご相談は2,200件を超え、550件ものご依頼を受任。豊富な経験と知識で、常に依頼者にとって最良の結果を追求している。特に、不動産の共有関係や借地関係の解決には強い関心を持ち、複雑な問題も粘り強く解決に導く。
最新の投稿
- 2025.08.06不動産トラブルのセカンドオピニオンを検討中の方へ
- 2025.04.18不動産の使用貸借の終了に伴う立退きについて
- 2025.04.15定期借家契約の活用術
- 2025.04.15Q.自身が所有している不動産が競売にかけられているが、どうにかしたいです。